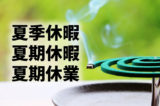スキルアップ・キャリアアップ
課長になれる人となれない人の違い5選

スポンサーリンク
課長になれる人となれない人の違い
会社勤めをする人の多くにとって、昇進は大きな関心事でしょう。部下を持たない係長になれるチャンスは、まじめに頑張ってさえいれば、それなりの確率となっています。
しかし、管理職である課長となると、そう簡単ではありません。複数の部下を動かし、責任ある仕事を任される課長には、それにふさわしい資質を持つ人が選ばれるようになっています。では、その資質とはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、課長になれる人となれない人を分ける特徴について、詳しく解説していきたいと思います。
人望の有無
課長になれる人は、「周囲からの人望がある」ことが通常です。課長になった場合、大勢の部下を使わなくてはなりませんし、さまざまな人と交渉する場も増えます。そうした時に周囲からの人望があるかどうかは、仕事の出来を大きく左右する要素となります。自然に信頼を寄せられるような人物であれば、部下は積極的に動いてくれますし、交渉の場でも、相手の柔軟な姿勢を引き出しやすくなります。こうした人であれば、会社としても課長の座を任せたいと思うでしょう。
一方、課長になれない人は、周囲からの人望が薄いことが多くなっています。同僚との協調性に欠けたり、人によって態度を変えるなどの人は、人望はなかなか得られません。こうした人は、課長はおろか係長への昇進の機会も得にくいでしょう。
意思疎通ができているかどうか
課長になれる人は、多くの場合で意思疎通の能力に長けています。前述のように、課長になると、人を使ったり接する機会が格段に増えます。そうした時に、他人に対し自ら積極的に働きかけられることは、仕事に置いて大きな武器になります。こちらの考えを的確に伝えられることで、部下も思い通りに動いてくれますし、交渉においても、積極的な意思疎通でことを有利に運びやすくなります。こうした能力を持つ人は、昇進の機会も得やすいでしょう。
一方、課長になれない人は、意思疎通が苦手な人が少なくありません。人と積極的にコミュニケートしないことにより、会社にもネガティブな印象を持たれやすくなっており、そのために課長への昇進の機会も少なくなりがちです。
計画管理能力の有無
課長になれる人は、計画管理的な能力に優れている人が多くなっています。課長という立場になると、自分1人のことだけでなく、課全体のことを考えて仕事をすることが求められます。課としていかに結果を残すかを第一に考え、そのために動かなくてはなりません。
そこで必要になるのが、目標を達成するための計画管理能力です。最初に先を見越した計画を立て、それを状況に応じて的確に管理していくことで、より効率的な目標達成が可能となります。会社側は、こうした能力を持つ社員ほど、昇進の機会を与えようとしたがるでしょう。
それに対し、課長になれない人の多くは、計画管理能力が不足しています。プラン作り自体が苦手だったり、1つのプランに固執するような人は、昇進のチャンスも得にくいのが実情です。
問題意識の有無
課長になれる人の多くには、「常に問題意識を持って仕事をする」という傾向がみられます。課長の地位にある人は、大きな単位での仕事をコントロールしなくてはなりません。そういった仕事は、まとまったスケールを持つ分、会社に与える影響も大きくなります。成功した場合のリターンが大きい反面、失敗した場合のダメージも大きくなります。そのため、課長は常に仕事の進捗状況に気を配り、問題やトラブルの発生を未然に防ぐ姿勢が求められます。ですから、普段からこうした姿勢を持つ人は、会社の目に留まりやすいと言えます。
一方、課長になれない人の大半は、こうした危機意識に欠けることが通常です。漠然と仕事に向かう姿勢は、会社からも決して良い印象は持たれないでしょう。
先のことを考えているかどうか
課長に昇進できる人の特徴として、「常に先の局面を見ている」ということもあります。仕事は、1つのものが終わればそれでおしまいというわけではありません。当然ですが、次々に新しいプロジェクトをこなしていく必要があります。会社にとっては、こうした一連の仕事を長い目で捉え、常に結果を出し続けることが、最も重要な課題となります。ですので、先々をみすえる目と、長いスパンでものを考えられる人材は、課長の座にふさわしいと思われて当然でしょう。
これに対し、課長になれない人の多くは、目先の仕事に追われるタイプとなっています。先を見ることなく、現在の仕事だけで満足している人には、なかなか昇進のチャンスは訪れないでしょう。

この記事が気に入ったら いいね!しよう