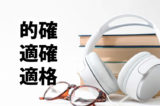一般常識
「歌う」「唄う」「謳う」「詠う」「謡う」「唱う」の意味と違い
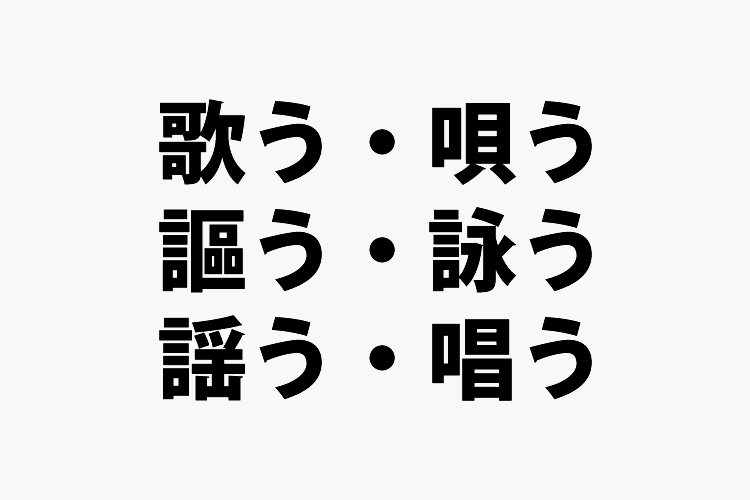
スポンサーリンク
歌う・唄う・謳う・詠う・謡う・唱うの意味と違い
「うたう」という言葉の漢字表記には、さまざまな種類があります。「歌う」「唄う」「謳う」といったものですが、これらは場合によって使い分けられるのが通常です。では、具体的にどんな使い方をされるのでしょうか。それぞれの細かい違いが知りたいところです。今回は、「歌う」「唄う」「謳う」「詠う」「謡う」「唱う」の意味と違いについて解説していきましょう。
歌うとは
「歌う」とは、「音楽的な高低、調子などをつけて声を出す」という意味の言葉です。メロディーやリズムに合わせ、言葉の連なりや特に意味のない声などを発することを言います。英語で言えば、「sing」にあたる言葉です。具体的には、「校歌を歌う」「ヒットソングを歌う」「自作の曲を歌う」のように使われます。
「歌う」はまた、「詩歌(しいか)を作る」や、「詩歌に節をつけて朗読する」という意味でも使われます。「望郷の心を詩に歌う」などの使い方です。このほかに、「鳥がさえずる」という意味で使われることもあります。この場合は、「花咲き鳥歌う」「小鳥が歌う声が響く」などのように使われます。
「歌う」の「歌」の字は、「口を開ける」「口から大声を出す」などを表す象形から成っていおり、そこから「うたう」を意味する漢字として成り立ちました。
「唄う」などとの違いについては、以下で見ていきましょう。
唄うとは
「唄う」という言葉は、「歌う」と基本的に意味の違いはありません。辞書でも、「歌う」と同じ項目に載せられています。そのため、「歌う」と置き換えて使うことも可能です。ただし、一般的な使い方においては、使い分けされることが多くなっています。
「唄う」の表記が使われるのは、「長唄」や「小唄」など、日本の伝統的な音楽(いわゆる邦楽)をうたう場合が一般的です。例えば、「民謡を唄う」「小唄を唄う」などといった具合です。
「唄」という字は、もともと「仏の行いをたたえる歌」を表しており、そこから現在のような使われ方になりました。ただ、「うたう」の読みは常用漢字音訓表に含まれないので、公用文などで使うことはできません。
謳うとは
「謳う」は「歌う」と同じ語源の言葉ですが、使われ方はかなり違います。「謳う」が表すのは、「多くの人がほめたたえる」または「あることを盛んに言い立てる」といった意味合いです。前者は「謳歌する」の意味合いで、具体的には「太平の世を謳う」「この世の楽しみを謳う」などのように使われます。一方、後者は言葉や文章で大きく主張することを意味し、「憲法では国民主権を謳っている」「効能書きが謳うような効果は、この薬からは感じられなかった」のように使われます。
「謳」の「謳」の字は、「言う」と「区切る」を表す象形から成っています。そこから「言葉に区切りをつけてうたう」の意味で使われるようになりました。ちなみに「謳」の字も、常用漢字表には含まれません。そのため、公用文などで「謳う」の表記は使えないようになっています。
詠うとは
「詠う」とは、「詩や歌につくる」または「感動を込めて述べる」という意味の言葉です。ある感慨を抱いて詩などにあらわしたり、言葉を述べることを言います。「壮大なロマンを詠った叙事詩」「愛の詩を詠う」などのように使われます。
「詠う」は、やはり「歌う」と同語源の言葉です。しかし、「詠う」はメロディーやリズムに合わせて発声するわけではなく、詩を書いたり詩的な言葉を述べることを指しています。この点は、「歌う」との違いになります。
「詠」の字は、「言う」の象形と「長く続く」の象形から成っており、「口から長く声を引くこと」を表します。そこから「(詩歌を)うたう」という意味の言葉として成り立ちました。
「唄」や「謳」同様、「うた(う)」という読みは正式にはなく、やはり公用文などでは使えない表記となっています。
謡うとは
「謡う」もまた、「歌う」と同じ意味合いを持つ言葉です。辞書においては、どちらの表記も同様に使えるようになっていますが、一般的な使い方には違いがあります。「謡う」の表記が表すのは、主に「謡曲をうたう」という意味合いです。謡曲とは、能の詞章を表します。
「謡」の字は本来、「神に供え物をしてうたう」ことを表していますが、日本では「謡曲(うたい)」という意味を持ちます。具体的には、「結婚披露宴で『高砂』を謡うのは定番だ」のように使われます。
唱うとは
「唱う」もやはり、基本的な意味は「歌う」と違いはありませんが、通常の使われ方は異なります。「唱う」の表記が主に表すのは、「声に出して読み上げる」ということです。「唱」は「となえる」という意味を持っており、音階の抑揚をあまりつけず、詩歌や祈りの文句などを声に出して読むことを指します。
「唱」の字は、「口」の象形と「日の光」を表す象形から成っています。その意味は「すばらしくさかんな声」というもので、そこから「となえる」や「うたう」を意味する漢字として成り立ちました。
ただ、「唱」もまた常用漢字表に「うた(う)」という読みはないので、公用文などでは使えません。また、一般的な使用例も、「歌う」に比べてかなり少なくなっています。
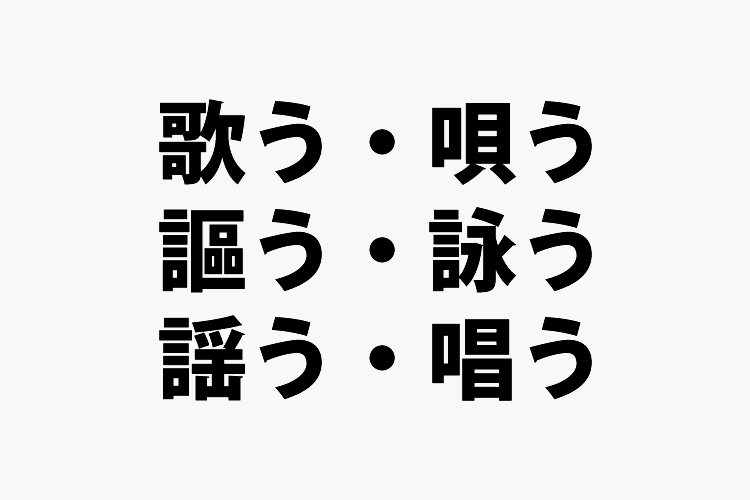
この記事が気に入ったら いいね!しよう