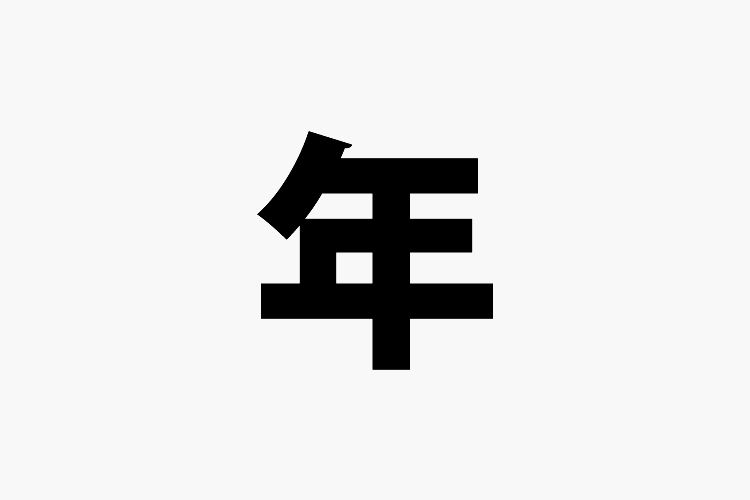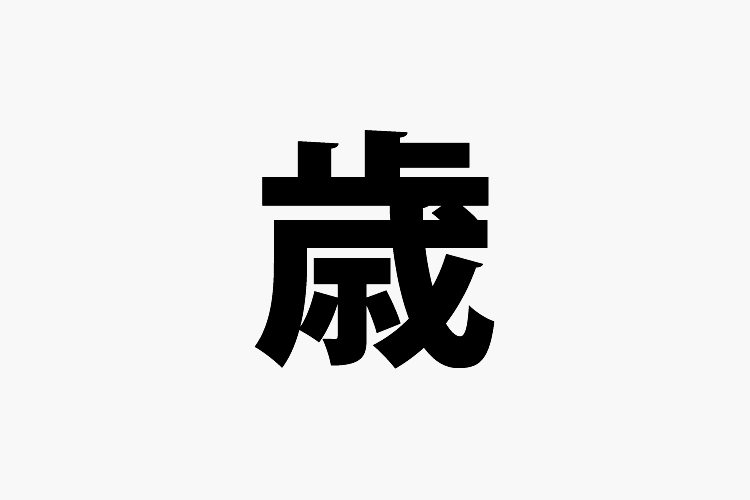一般常識
「年」「歳」の意味と違い
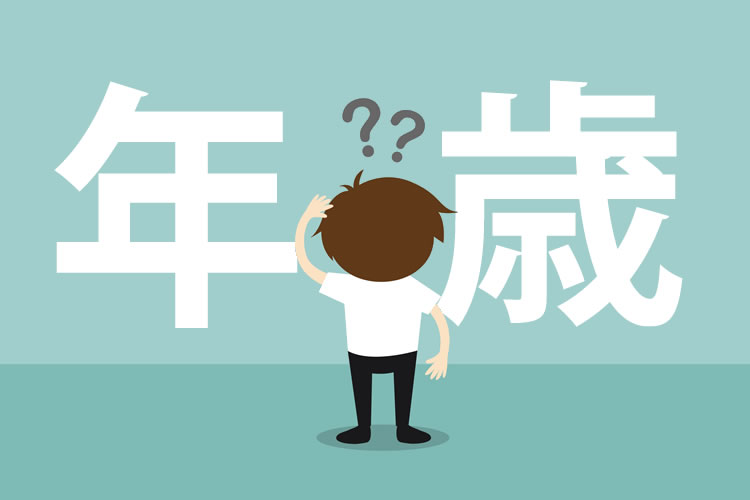
スポンサーリンク
「年」「歳」の意味と違いとは
「“とし”が明ける」「“とし”を取る」などという場合の「とし」には、「年」と「歳」の2つの漢字を当てはめることができます。この2つはどちらも同じことを表しているようですが、何か違いなどはあるのでしょうか。
今回は、「年」と「歳」の意味や違い、使い分けのポイントなどについて解説していきましょう。
「年」とは
「年(とし)」とは時間の単位で、「1月1日からはじまり、12月31日で終わる12ヵ月間」を意味する言葉です。例えば「年が明ける」という場合は、「1月1日になって、新しい12ヵ月間が始まる」という意味になります。また、「多くの歳月」や「年齢」といった意味もあり、それぞれ「年を経た建物」「祖父はまったく年を感じさせない」のように使われます。
「年」の字は、もともと「成熟した穀物」を意味していますが、1回の穀物の収穫には1年かかることから、時間の単位として使われるようになりました。
「歳」との主な違いは、常用漢字であるため公用文で使えるという点にあります。また、「としを取る」などと言う場合は、「年」では「年齢(年月)を加える」という「回数」のニュアンスが強調される点も、「歳」との違いになります。
「歳」とは
「歳(とし)」とは、「一か年」という意味の言葉です。1月1日から12月31日までのことを言い、「歳が暮れる」「歳の瀬」のように使われます。また、「年月」「年齢」の意味もあり、この場合は「歳を重ねる」「歳を取る」のように使われます。
「歳」という字は、「歩む」「まさかり」の象形から成り、「1年ごとにまさかりでいけにえを裂いて祭る儀式」を表しています。そこから「1か年」を意味する言葉として使われるようになりました。
「年」と「歳」の意味の違いは、基本的にありません。ただ、常用漢字表では「歳」に「とし」という読みはないため、公用文では上記のように、「年」のみを使うことができます。また、「年を取る」が「年月を順当に重ねる」というニュアンスを持つのに対し、「歳を取る」では「時間が過ぎ去っていく」「老齢になる」という「経過」のニュアンスが強くなる点も、両者を使い分ける際のポイントとなります。
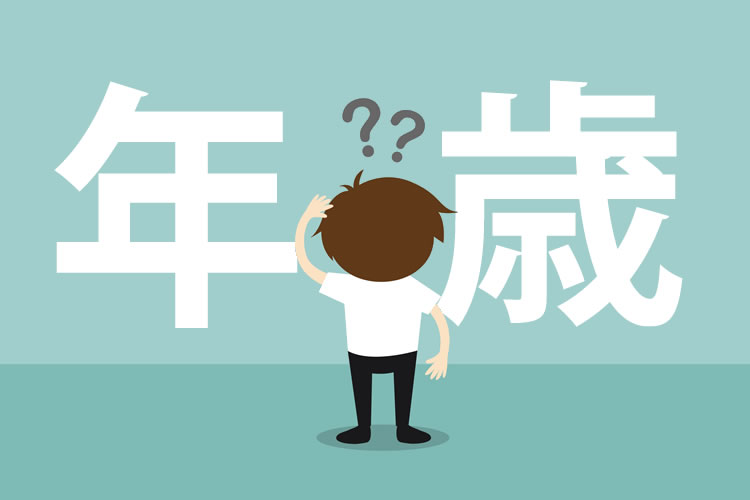
この記事が気に入ったら いいね!しよう