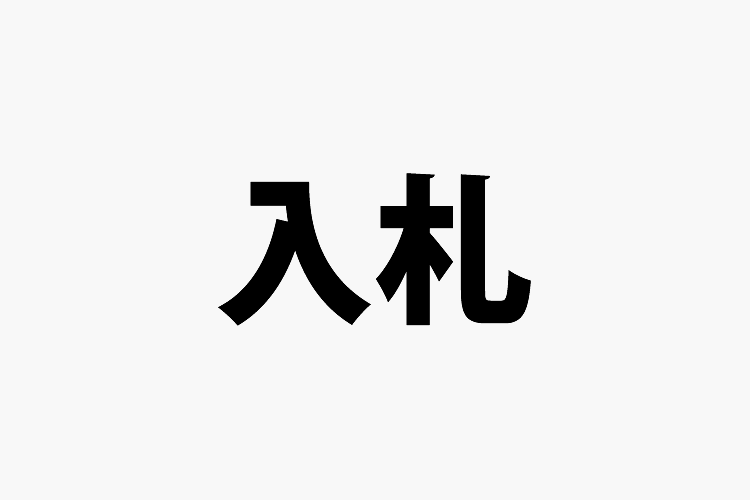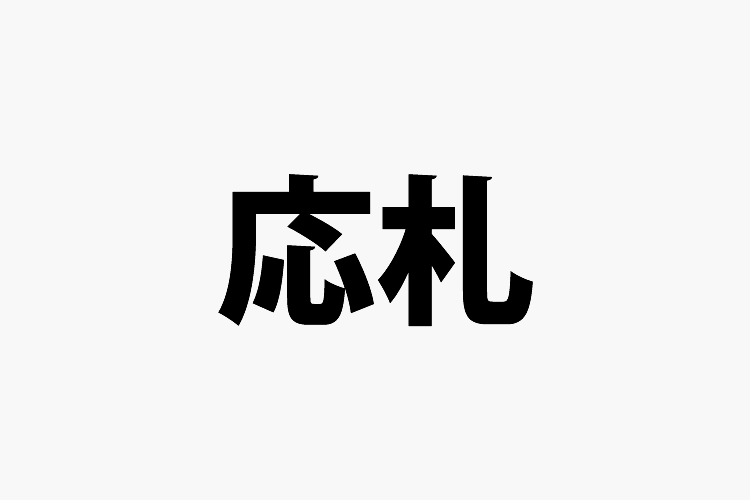ビジネス用語
「入札」「応札」の意味と違い

スポンサーリンク
「入札」「応札」の意味と違いとは
「入札」という言葉は、オークションや公共工事などでおなじみのものです。一方、これと似た言葉に「応札」というものがありますが、両者の違いは一体どこにあるのでしょうか。詳しく説明できる人は、そう多くないでしょう。
そこで今回は、「入札」と「応札」の意味の違いについて解説していきたいと思います。
「入札」とは
「入札」とは、物品の売買や工事の請負などに際して、契約を望む者が複数ある場合、金額などの条件について文書で示させ、その内容を比較して契約相手を決定することを指す言葉です。また、契約希望者がその文書を提出することについても言います。読み方は「にゅうさつ」で、「公共事業の入札に参加する」「オークションの入札者」のように使われます。会計法においては、国が結ぶ契約は原則として「入札」によると規定されており、「一般競争入札(入札者を特定しない入札)」と「指名入札(入札者を指名する入札)」の2種類に分かれます。
「入札」の「入」は「いれる」を意味し、「札」はこの場合、「文字などが書かれた紙」を意味しています。昔は投票などの行為を「入れ札(いれふだ)」と呼んだことから、この名で呼ばれています。
「応札」との違いは、後述するように、「一般的な用語で使われ方も幅広い」点にあります。
「応札」とは
「応札」とは、「競争入札に加わること」という意味の言葉です。より狭義には、入札書を入札箱に投函する行為について言います。読み方は「おうさつ」で、「落札の決定については、応札したすべての企業に連絡される」「入札価格を十分検討した上で応札することが大事だ」のように使われます。
「応札」の「応」という字は、「呼びかけや問いかけにこたえる」「外からの求めなどを受けて動く」の意味を持ちます。
「入札」との意味の違いは分かりにくいところですが、「応札」の方が使われ方が限定される点が違います。「応札」は、「競争入札への参加」や「入札書を入札箱に入れる行為」について言う専門用語で、一般ではあまり使われません。それに対し「入札」は、公共事業やオークションなどで幅広く使われ、一般にも浸透している点で使い分けできます。

この記事が気に入ったら いいね!しよう