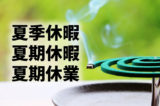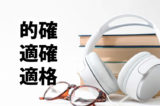ビジネス知識
「判子(ハンコ)」「印鑑」「印章」の意味の違い

スポンサーリンク
判子(ハンコ)・印鑑・印章の意味の違い
生活の中で欠かせないものはいくつもありますが、「判子(ハンコ)」はその代表的なものでしょう。さまざまな場面で必要とされる「判子」ですが、場合によっては「印鑑」と呼ばれることもあります。この2つは同じものなのでしょうか。「印章」との違いも気になるところです。そこで今回は、「判子(ハンコ)」「印鑑」「印章」の意味の違いについて、詳しく解説していきます。
判子(ハンコ)とは
「判子(ハンコ)」とは、個人や組織がその当事者であることを証明するためのしるしのことです。木や鉱物、金属、角(つの)などで作られた棒状のもので、先端に文字や図形が彫刻されており、そこへ印肉をつけて文書等に押し付けることで、自らの証明とするものを意味します。使い方はさまざまで、会社内で回覧用の文書などに使ったり、個人で宅配の受け取りに認印として使う、重要な契約に実印として使うなどがあります。「判子を押す」「判子をもらう」などのように表現します。
「ハンコ」という呼び方は、実際には正式なものではありません。「版行(はんこう)」の読みが変化したもので、「判子」は当て字になります。「判(はん)」や「印判(いんばん)」などとも呼ばれます。
「印鑑」などとの違いについては、以下で見ていきましょう。
印鑑とは
「印鑑」は、「判子」と同一視されることもありますが、実際には意味が異なります。「判子」は判を押すための器具のことですが、「印鑑」は判を押した際、紙や書類に残る文字等の印(しるし)を意味します。つまり、「印影」と同義の言葉です。法令では、あらかじめ官庁や取引先などに届け出ておき、後で真偽を照合するための実印の印影を指します。「印形(いんぎょう)」とも呼ばれます。「印(いん)」はいわゆる「判子」のことで、「鑑」は「身分や資格を見分ける証拠」を意味します。
現在は「判子」と「印鑑」はほとんど同じものとして扱われていますが、実際にはこのような違いがあります。そのため、「印鑑を押す」という表現は、本来は間違いであることになります。
印章とは
「印章」はあまり耳慣れない言葉ですが、自分の身分などを証明するための、印を押す器具のことです。つまり、意味合いとしては「判子」と違いはありません。読み方は、「いんしょう」です。やはり「判」や「印判」などと呼ばれることもあります。
「印章」の使用は世界中で古くから行われており、日本でも中国の影響で古代から使われていました。明治以降は署名の代わりに記名捺印するのが一般的となり、印章が重要視されるようになったという経緯があります。
このように、「印章」は「判子」と同義のため、「印鑑を押す」はNGでも、「印章を押す」という表現はOKとなっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう