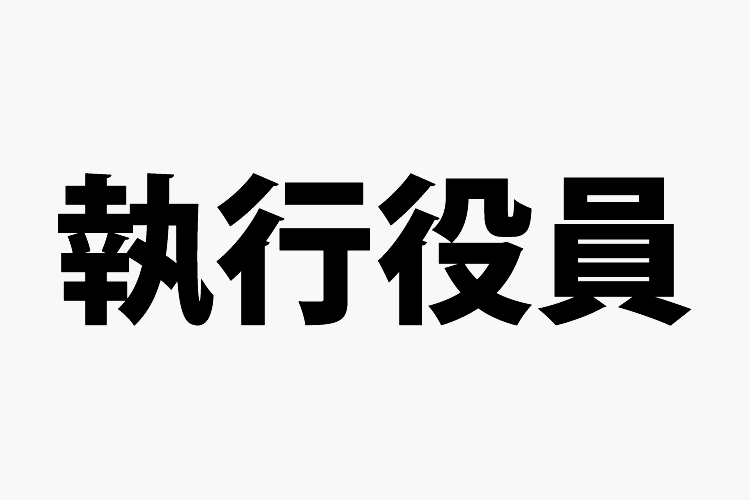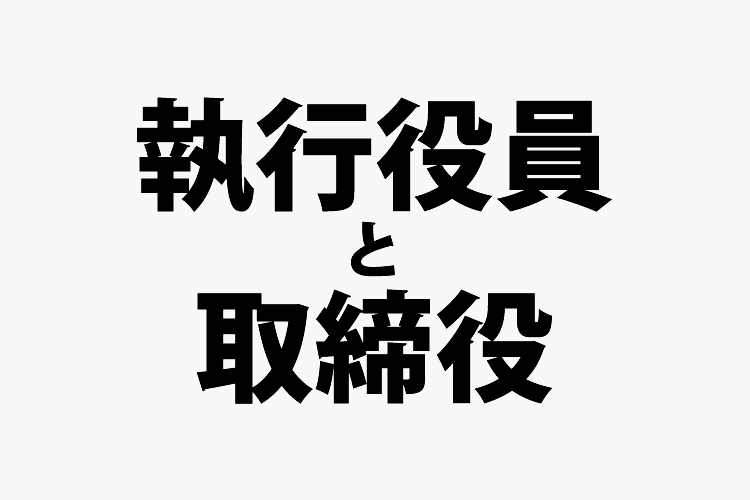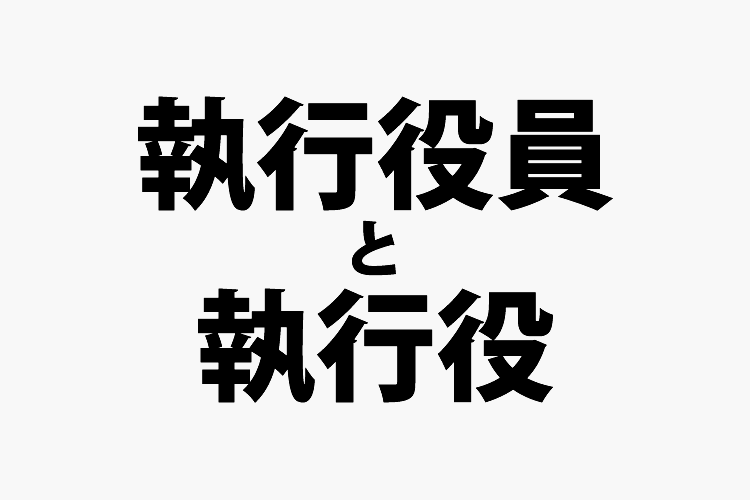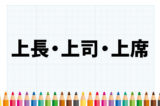ビジネス知識
執行役員の意味とは?メリット・デメリットと執行役員と取締役・執行役の違い

スポンサーリンク
会社の中には、さまざまな肩書を持つ人が存在します。「部長」や「課長」などであれば、一般社員にとってはなじみがありますが、トップの方になると、正直なところその意味や役割が分かりにくいものも多くなってきます。
「執行役員」という役職も、耳にはしたことがあるものの、実際にどのような業務を行っているのか、またどのような権限があるかを正確に理解している方は少ないと思います。
本記事では、意外に分かりにくい「執行役員」の意味やメリット・デメリット、また取締役や執行役などとの違いについても解説していきます。
執行役員の意味とは?
特に上場会社など、規模の大きい会社においては、執行役員制度が導入されています。
まずは「執行役員」の意味や設置する目的、会社内での役割について見ていきましょう。
執行役員の意味とは?
「執行役員」という単語は、法律で定義されてはおりませんが、一般的には、「取締役が決めた方針に従い、重要な業務執行に当たるポスト」を意味するものと考えられています。
そもそも執行役員というポストは、「会社の経営・監督と、業務執行を分けたい」というニーズから生まれたものと解されています。ソニー株式会社が1997年に最初に導入して、以降、多くの会社に執行役員制度が広がっていったようです。
当時、多くの上場会社では、取締役の人数が多くなりすぎており、会社の重要な意思決定を行うための「取締役会」が十分に機能しない状況に陥っていました。人数が多い会議で、1つのことを決定するのは非常に大変です。
取締役会を十分に機能させるためには、取締役を一定数に減らす必要がありますが、単に「取締役から外れる」こととなれば、この方々は当然会社から離れてしまうでしょう。
そこで、元々取締役であった方々の「受け皿」的な立ち位置として、執行役員というポストが生まれました。
上記の経緯からも分かりますが、執行役員は、「役員」という名前はついているものの、いわゆる「取締役」ではないことが多いです。ただ、実際には、執行役員が取締役を兼ねているケースも一定数見られるため、一義的に定義するのは中々難しいのが実情です。
執行役員と取締役との違いは、後で述べます。
執行役員の役割
先ほど見た定義との関係で重要なのが、
「取締役が決めた方針に従い」
「重要な業務執行に当たる」
という点です。
まず、先に述べた通り、執行役員は、「役員」という名前はついているものの、いわゆる「取締役」ではないことが多いです。そのため、会社の重要な意思決定、要は経営方針等については、基本的には取締役らが決定します。
そして、執行役員は、取締役らが決定した方針に従って、会社の業務執行を行うことになります。ただ、役職としてはほぼ最上位のポストではあるため、通常の業務対応というよりは、事業や部門を統括する役割を担っているケースが多いです。
なお、執行役員という単語は、法律上で定義されているものではなく、執行役員を置くか、置く場合に何人置くか、執行役員にどのような業務をしてもらうかは、各社が任意に決定することができます。そのため、A社における執行役員の役割と、B社における執行役員の役割とが大きく異なっていることもありますので、少し注意が必要です。
執行役員制度のメリット・デメリット
では、執行役員制度があることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。また、反対にどんなデメリットはあるのでしょうか。
メリット
先ほど見た通り、執行役員は、取締役らが決定した方針に従って、会社の業務執行を行うことになります。
仮に「執行役員」がいなければ、会社の重要な意思決定を行う取締役が、業務の執行についても行わなければなりません。特に中小企業においては、経営者が実務対応も行わなければならないケースが非常に多いですが、これでは経営に専念することは難しいです。
執行役員制度があることにより、取締役は、会社の重要な意思決定やその監督に専念・集中することができます。また、執行役員は、意思決定を行うポジションから離れ、業務の執行に専念・集中することができます。
執行役員制度を導入する一番のメリットは、まさにこの部分にあるでしょう。要は、「会社の意思決定・監督と、業務執行との役割を分担できる」点が、執行役員制度の一番のメリットかと思います。
その他、執行役員制度があることにより、人材の流出を防ぐことができる(可能性がある)というメリットも挙げられます。執行役員が人材の「受け皿」として機能するわけです。
会社の中の最上位のポストは「取締役」と考えられるのが通常ですが、取締役の人数にも限りがあります。優秀な人材が社内で出世し、どんどん上位職になっていくのに、上が詰まっていて取締役にはなれない…こういう状況は、従業員の不満を生み、人材の流出に繋がってしまいます。
一般従業員や通常の職務系統とは異なる「執行役員」というポストがあることにより、優秀な人材を社内に留めておくことができるという側面はあるでしょう。
デメリット
執行役員制度を導入する企業は増えている一方で、一度導入した執行役員制度を廃止している会社もあります。
明確なデメリットとまで言えるかは別としても、
・「幹部側」の従業員が増えすぎることによるアンバランスさ
・指揮系統が複雑になってしまうことの問題
が挙げられることがあります。
前者は企業規模によっても異なるため一概には言えませんが、後者は、「執行役員」の役割が不明確なことに起因して生じ得る問題です。
一般従業員からすると、取締役と執行役員との明確な違いは、中々理解し辛い部分がありますし、執行役員に就任した人も、「自分が何を期待されて執行役員になったのか、執行役員として何を行わなければいけないか」を正確に理解できていないケースもあるでしょう。「執行役員という制度をとりあえず設けてみた」という会社も一定数あることは否定できず、このような場合だと、会社も、執行役員も、指示を受ける一般従業員側も皆混乱してしまいます。
執行役員と取締役・執行役の違い
執行役員と似た肩書に、「取締役」と「執行役」というものがあります。混同されがちなこの3つですが、それぞれどのような違いを持つのでしょうか。以下の項目では、執行役員と取締役・執行役との違いについて見ていきましょう。
執行役員と取締役の違い
執行役員は、「役員」という名前はついているものの、いわゆる「取締役」ではないことが多いです。ただ、実際には、執行役員が取締役を兼ねているケースも一定数見られるため、一義的に定義するのは中々難しいのが実情です。
「執行役員の意味とは?」という箇所で、このように説明しました。
つまり、「取締役を兼務している執行役員」と、「取締役は兼ねていない、単なる執行役員」との2種類があるわけです。
ここでは分かりやすさの観点から、「単なる執行役員」と取締役との違いを説明します。
執行役員の特徴などをまとめると、以下の通りです。
- 執行役員=取締役が決めた方針に従い、重要な業務執行に当たるポスト
- 法律上で定義されているわけではない
- 執行役員を置くか、置く場合に何人置くか、執行役員にどのような業務をしてもらうかは、基本的には各社が任意に決定することができる
この執行役員の特徴と比較する形で、取締役の特徴を記載すると、以下の通りとなります。
- 取締役:会社の重要な意思決定や業務執行を行うポスト
- 法律上(会社法)で明確に定義されている
- 全ての会社は必ず取締役を設置しなければならず、会社の組織構造や規模に応じて、設置しなければならない人数なども決まっており、取締役の業務内容も法律で定義されている
「法律上で定義されているか」により、様々な違いが生じています。
ただ、何度かお話した通り、執行役員が取締役を兼ねているケースもあるため、この場合には、「取締役の通常の業務内容+各社が決定した執行役員の業務内容」を行うことになりますので、会社の重要な意思決定に加えて、業務執行まで行うことも期待されているのが通常でしょう。
執行役員と執行役の違い
執行役員と執行役は1文字しか違いませんが、全く意味合いが異なります。
執行役員はこれまで十分に説明したので、以下簡単に執行役の役割を説明します。
「執行役」は、「指名委員会等設置会社」に限り設置が義務付けられているポジションで、法律上も明確に、設置しなければならない人数や役割・責任などが定義されています。
ここでは詳細な説明は省略しますが、執行役は、会社の一定の経営方針を決定することと、業務の執行を行う役割を有しており、「執行役員」に通常期待される役割と被る部分もあります。
ただ、先に見た通り、「法律上定義されているか」という大きな違いがあり、これにより、両者が法律上負う責任や義務にも違いが出ています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう