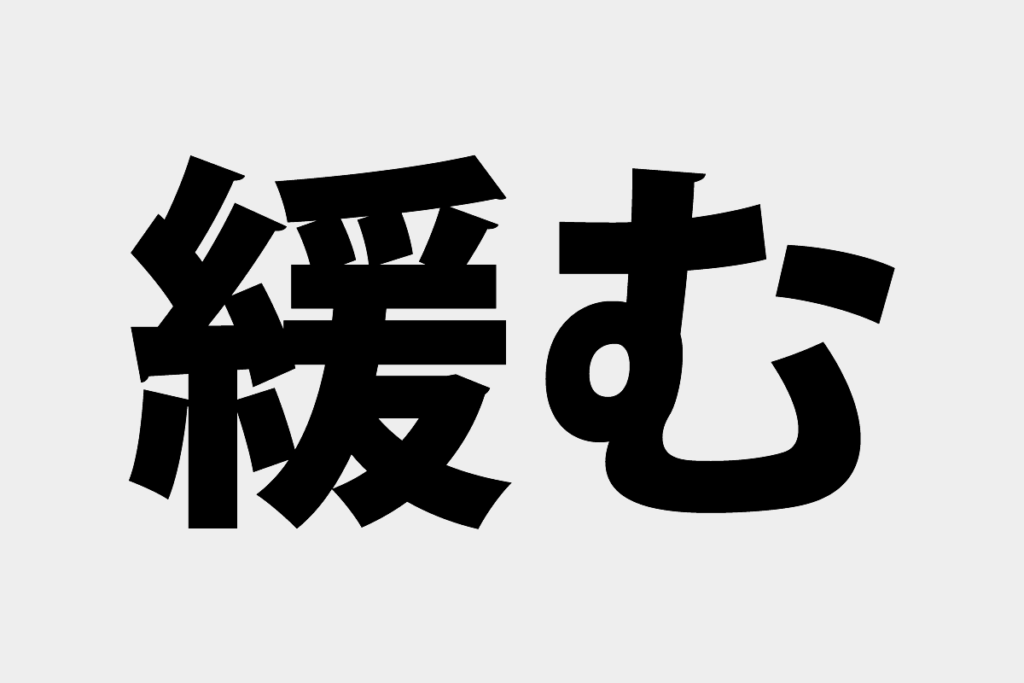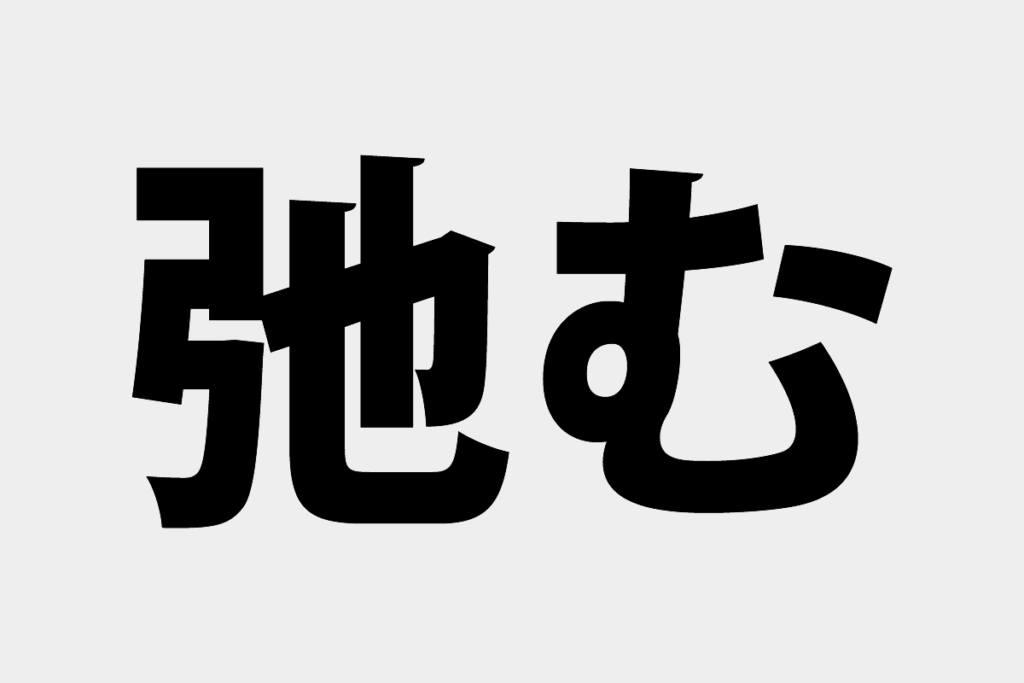一般常識
「緩む」「弛む」の意味と違い
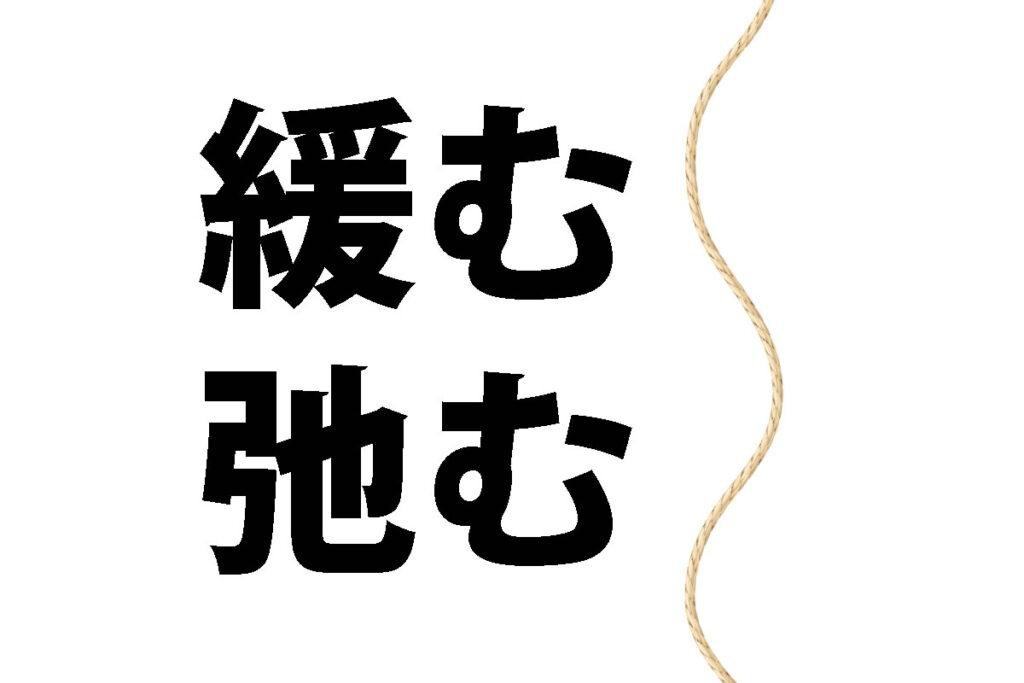
スポンサーリンク
「緩む」「弛む」の意味と違い
「緊張が一気にゆるむ」などのように、「ゆるむ」という言葉は日常生活でも比較的よく使われるものです。しかし、この言葉を漢字で表そうとすると、「緩む」と「弛む」の2つが候補に上がってくることに気付きます。読みは同じでも字は全く異なるため、それぞれ使い分けできそうに感じられますが、実際のところはどうなのでしょうか。
今回は、「緩む」と「弛む」の意味や違いを詳しく解説していきますので、両者の区別について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
「緩む」とは
「緩む」とは、「ピンと張ったものがたるむ」という意味の言葉です。あるものの締め具合が弱くなることを言います。「ねじが緩む」「ひもが緩む」などのように使われます。
また、「緩む」には、「気が緩む」のように「緊張がほぐれる」「油断する」の意味や、「寒さが緩む」のように「厳しかった状態・程度がゆるやかになる」、「頬が緩む」のように「固いものがやわらかくなる」などの意味もあります。さらに、「速度が減ずる(スピードが緩む)」の意味合いも持ちます。
「緩む」と「弛む」は、基本的に同じ言葉で、特に違いなどはありません。使い分けもそれほど気にする必要はありませんが、「弛」は常用漢字表に含まれないため、一般的には「緩む」の表記を使うのが無難と言えます。
「弛む」とは
「弛む」の意味は、やはり「張りつめたものがたるむ」「緊張がほぐれる」「状態や程度の厳しさがゆるやかになる」「堅いものがやわらかくなる」「速度が落ちる」といったもので、「緩む」と同様です。使い方も、「ひもが弛む」「気が弛む」「取り締まりが弛む」「氷が弛む」「スピードが弛む」のようになります。
このように、「緩む」と「弛む」は同じ言葉の異なる表記で、意味に違いなどはありません。「緩」は「糸をゆるめる」さまを、「弛」は「弓のつるがゆるむ」さまを示しており、共に「張り具合や締め具合が弱くなる」といった意味を表します。
ただ、上記のように「弛」の字は常用外であるため、一般的な使用頻度は「緩む」の方が高い傾向があります。また、「弛む」は「たるむ」とも読めるのに対し、「緩む」は「ゆるむ」以外の読みを持たない点も、細かな違いにあたります。
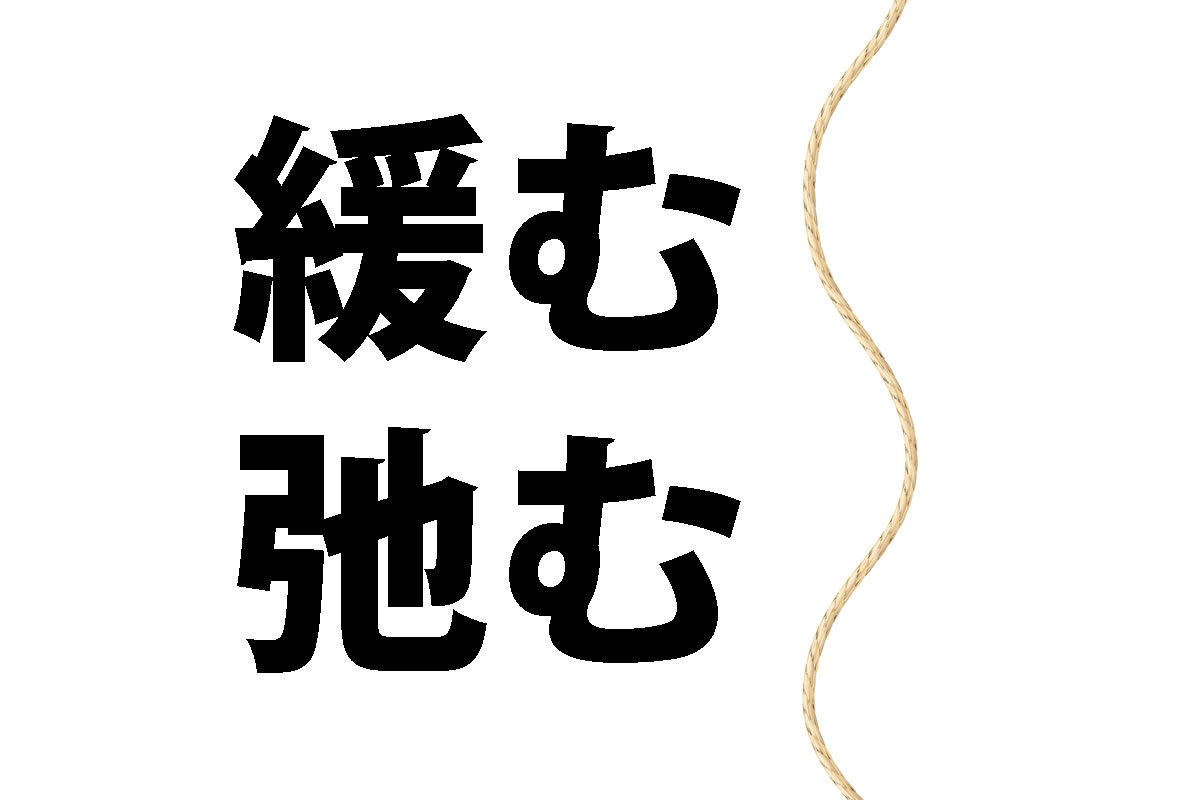
この記事が気に入ったら いいね!しよう