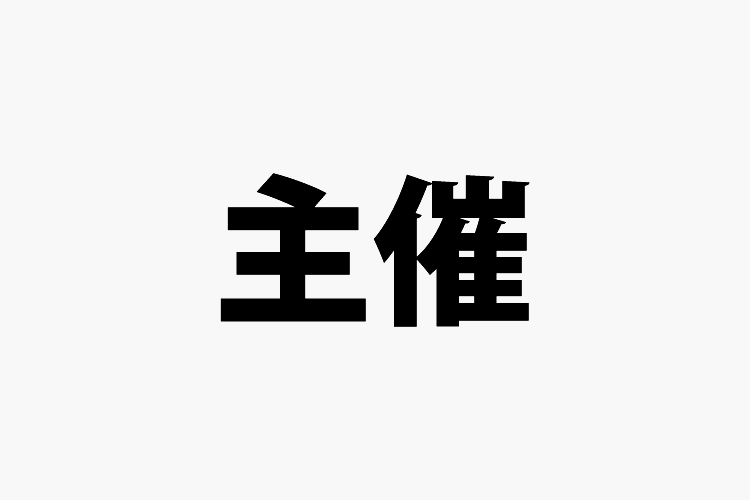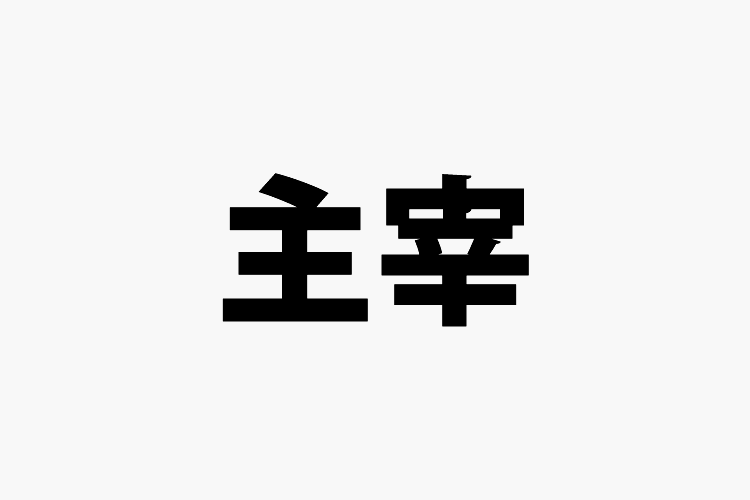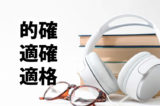一般常識
「主催」「主宰」の意味と違い

スポンサーリンク
主催・主宰の意味と違いとは
読みが同じで意味合いも似ていることから、使い方を混同しがちな言葉は多くあります。「主催」と「主宰」の2語も、そうした言葉の一種でしょう。共に「人をあつめて何かを行う」といった意味を持ちますが、具体的にはどういった点が異なるのでしょうか。
今回は、「主催」と「主宰」の意味と違い、使い分け方などについて解説していきましょう。
主催とは
「主催」とは、「中心となって事をもよおすこと」という意味の言葉です。パーティーやイベントなどの会合、行事といったものを、中心となって行うことを言います。また、そうした人や団体についても指します。「今夜のパーティーを主催したのは、彼女の友達だ」「新聞社主催によるマラソン大会」「主催者不在のイベント」のように使われます。
「主催」の「主」という字は、もともと「動かない火」を表していましたが、そこから「中心的な存在=ぬし・あるじ」という意味で使われるようになりました。「催」の字は、「人」「おしすすめる」の象形から成り、「行事などを行う」「人を呼び集める」などの意味を持ちます。
「主宰」との違いについては、以下で見てみましょう。
主宰とは
「主宰」の意味は、「全体をまとめること」というものです。ある集団において、人々の中心となって指導したり、全体を取り仕切ったりすることを言います。また、そうした人についても言います。「劇団の主宰者」「俳句結社の主宰」「プロジェクトを主宰する○○氏」のように使われます。
「主宰」の「宰」の字は、「祭事などのために調理する」さまを表しており、「つかさ」や「おさ」「統率者」といった意味を持ちます。
「主催」との違いが分かりにくいところですが、主な違いは「人の上に立つかどうか」という点にあります。「主催」の場合は、ものごとの中心にはなるものの、他人を指導したりするわけではありません。一方「主宰」の場合は、明らかにほかより立場が上で、ある種の権力を持つのが特徴となっています。この点に気をつけると、使い分けがしやすくなるはずです。

この記事が気に入ったら いいね!しよう