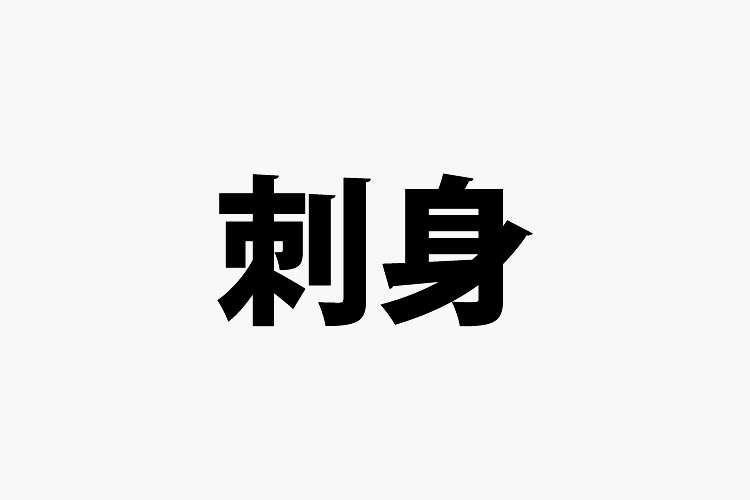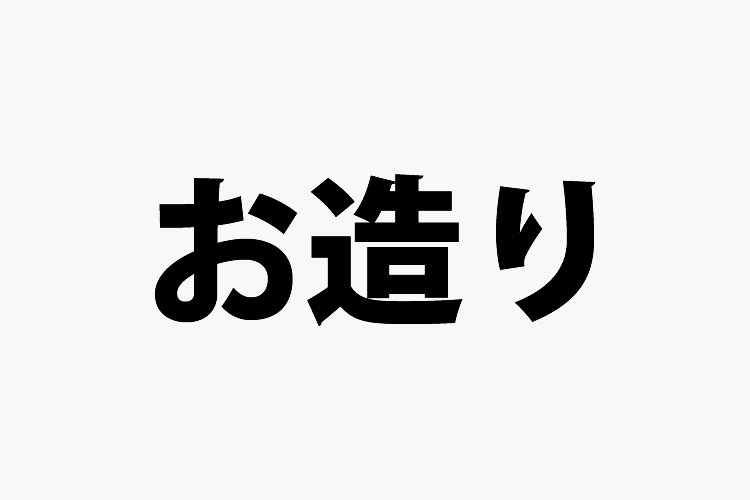一般常識
「刺身」「お造り」の意味と違い

スポンサーリンク
「刺身」「お造り」の意味と違いとは
「刺身」は、現在は日本に限らず、海外でも人気の料理となっています。その「刺身」と似た料理に「お造り」と呼ばれるものがありますが、両者がどのように違うのかご存知でしょうか。おそらく多くの人が首をかしげるところでしょう。
そこで今回は、「刺身」と「お造り」の意味や違いについて解説していきたいと思います。
「刺身」とは
「刺身」とは、簡単に言うと、「魚の切り身」という意味の言葉です。新鮮な魚介類を、手を加えず生のまま薄く切り、しょう油やわさびを付けて食べる料理を言います。読み方は「さしみ」で、「刺身をつまみに酒を飲む」「まぐろの刺身に目がない」のように使われます。
魚の切り身自体は室町時代から食べられていましたが、江戸時代にしょう油が一般に普及したことにより、庶民の間にも広まりました。「刺」の字が使われるようになった由来は、魚の種類が分かるようにその魚の尾ひれを切り身に刺して示したことにあると言われています。また、「切り身」の「切」の字が武士にとって忌み言葉であったため、「刺」の字に変えたという説もあります。
「お造り」との違いは、以下で詳しく説明しましょう。
「お造り」とは
「お造り」とは、関西での「刺身」の呼び名ですが、現在は特に、「魚介類の切り身を盛りつけた料理」の意味で使われるのが通常です。読み方は「おつくり」で、「お作り」「作り身」などとも呼ばれます。「豪勢な鯛のお造りを用意する」「イカのお造りを味わう」のように使われます。
「お造り」は、上記のように「刺身」の関西での呼び名で、魚を切ることを「つくる」と表現したことに由来する女性言葉です。ただ、関西でも儀式料理については、正式には「刺身」と呼んでいました。現在ではもともとの意味合いとはやや違い、「造る」という言葉の語感から、「刺身」をきれいに盛りつけたものを「お造り」と呼ぶようになっています。これについては関東も違いはなく、簡素な魚の切り身を「刺身」、きれいに飾り付けた切り身を「お造り」と呼んで使い分けるのが通常です。

この記事が気に入ったら いいね!しよう