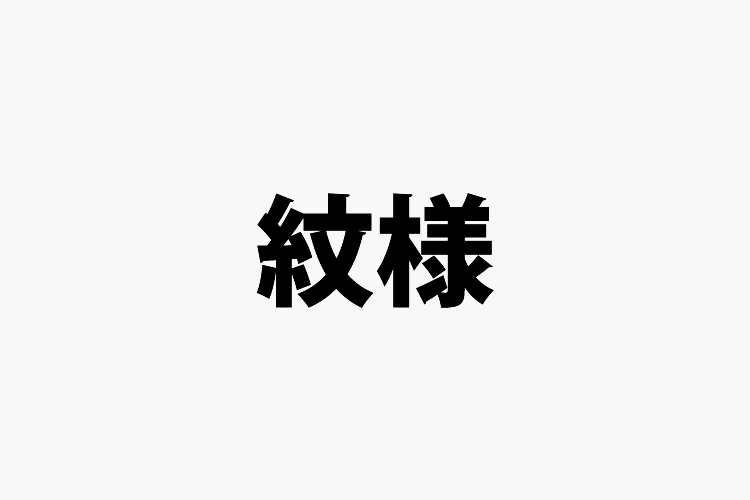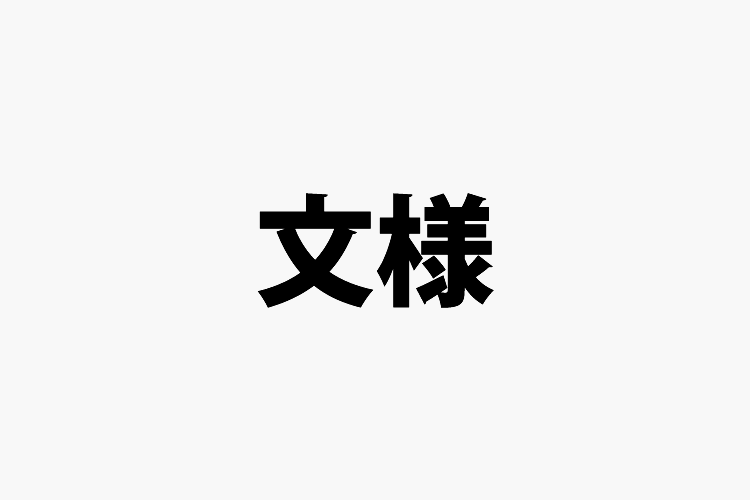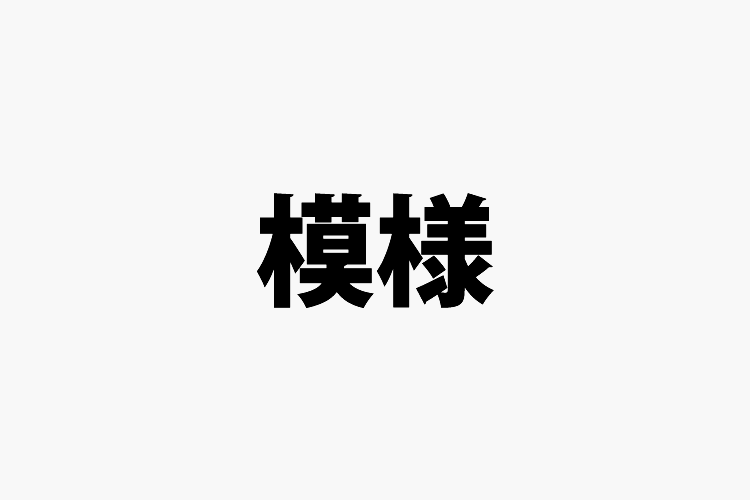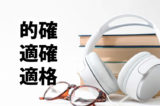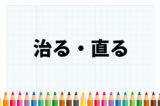一般常識
「紋様」「文様」「模様」の意味と違い
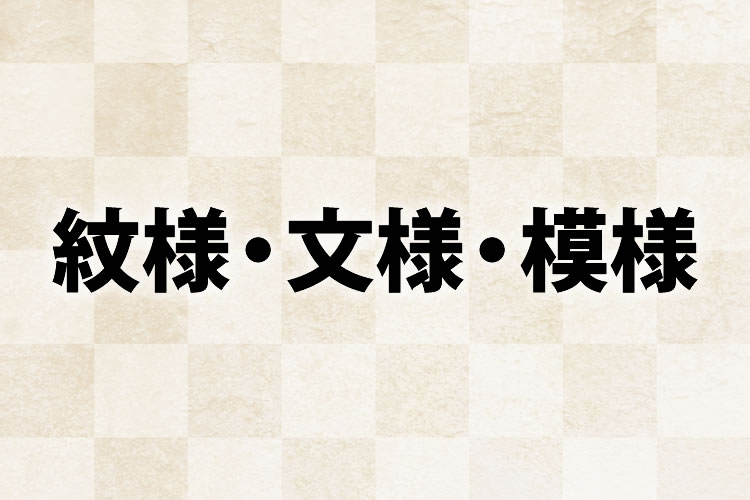
スポンサーリンク
紋様・文様・模様の意味と違いとは
何かの表面にあらわれた図形やパターンを表す時に、「模様」という言葉がよく使われます。しかし、他にも同じような意味合いの言葉として、「紋様」や「文様」といったものもあります。一体この3つには、どういった違いがあるのでしょうか。使い分けの仕方なども気になるところです。
そこで今回は、「紋様」「文様」「模様」という3つの言葉について、その意味や違いを探っていきたいと思います。
紋様とは
「紋様」とは、「模様」の一種にあたるもので、あるものの表面に施された図形を指して言います。
「紋様」の「紋」という字は、「入れ墨を入れる」を表す象形から成っており、「模様」を表しています。一方「様」は、「羊の首」などの象形から成り、「姿」「ありさま」などを意味します。
「紋様」と「文様」は、辞書においては同じ意味の言葉として記載されています。しかし、一般的な使われ方には違いがあります。「紋様」の表記が使われるのは、かなり限定された場面です。具体的には、「蝶の羽の紋様」や「小紋の紋様」など、伝統的に「紋様」の表記が使われてきた場合となっています。また、「波の紋様」などのように、自然にできあがった平面的な図柄に関して使われることもあります。
このように「紋様」は、慣用的な使用が定着している、特定の場合に限って使われる表現となっています。
文様とは
「文様」とは、鏡や寝台、食器などの調度や器具類、また、衣服などの表面に装飾された図形を言います。さまざまな種類がありますが、多くは同じ図柄を反復的に繰り返したものとなっています。
「文様」の「文」もまた、「入れ墨を入れる」の象形から成り、「模様」を意味する漢字となっています。
前述のように、「文様」と「紋様」は辞書においては同じ言葉ですが、一般的な使われ方は違います。「文様」の表記が指すのは、美術品や工芸品といった、人工物にあしらわれた図柄が主です。ですので、「皿の文様」や「壺の文様」といった使い方はされますが、「波の文様」などの使い方はほとんどされません。
模様とは
「模様」とは、「ものの表面の図形」といった意味の言葉です。織物や染め物、工芸品などに装飾としてあしらわれた図柄や、木目など自然物の表面にあらわれた図形を指します。
「模様」の「模」は、「木」や「くさむら」などの象形から成り、「かたち」や「ありさま」などの意味を持ちます。
「模様」という言葉は、「紋様」と「文様」の両方の意味を含むのが特徴です。「壁紙の模様」や「ドレスの模様」、「砂浜の模様」など、幅広く使える点が「紋様」「文様」との違いとなっています。ですので、一般的な意味で「ものの表面の図形・パターン」を表したい場合は、「模様」を使うのが無難ということになります。また、「人間模様」などの使い方ができるのも、「紋様」などとの違いになります。
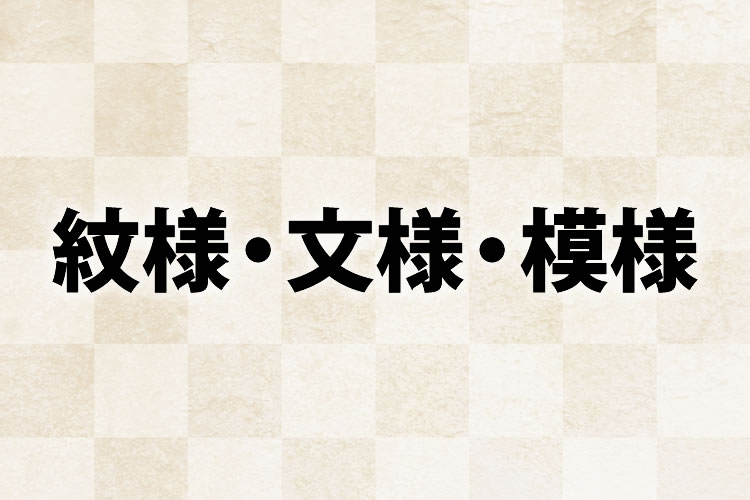
この記事が気に入ったら いいね!しよう