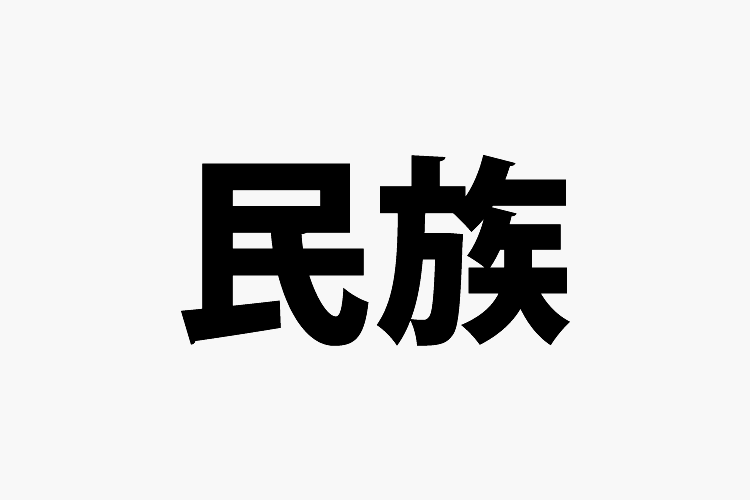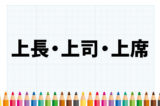一般常識
「民俗」「民族」の意味と違い
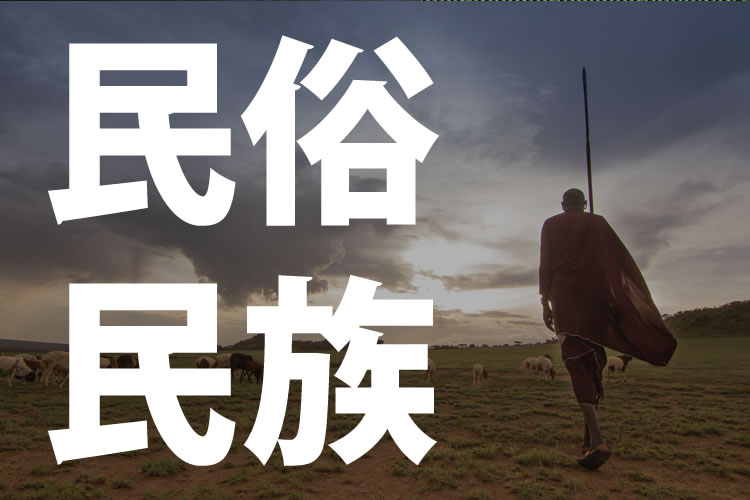
スポンサーリンク
「民俗」「民族」の意味と違いとは
日本語は同音異義語が多いことで知られていますが、「民俗」と「民族」も、そうしたものの1つです。どちらも「みんぞく」と読み、字の一部も重なることから、使い方を混同されるケースも少なくありません。しかし、両者の意味は明確に異なります。では、具体的にどのような点で区別されるのでしょうか。
今回は、「民俗」と「民族」の意味や違い、使い分けのポイントなどについて解説していきましょう。
「民俗」とは
「民俗」とは、「古くから民間に伝承してきた風俗や習慣」という意味の言葉です。ある集団などに昔から伝わるならわしを指します。「地域の民俗」「民俗芸能」「民俗学」のように使われます。「民俗芸能」とは、地域の祭礼などで代々受け継がれてきた、歌や踊りなどのことです。一方「民俗学」とは、民間伝承の調査を通して、庶民の生活・文化の発展の歴史を調べる学問を指します。
「民俗」の「俗」の字は、「ならい」や「ならわし」を意味しています。
「民族」との違いは、「風俗」や「習俗」を指す点にあります。これに対し「民族」は、後述するように「集団」を指す点で使い分けられます。
「民族」とは
「民族」とは、「言語や人種、文化、歴史観などを共有し、同族意識で結ばれた人々の集団」という意味の言葉です。長期間にわたり一定地域で共同の生活を営み、文化や歴史についての認識を共有する人たちを指します。人類学の用語で言えば、「集団帰属意識(エスニック・アイデンティティ)で結ばれた人々の集団」ということになります。似たような概念に「種族」や「部族」がありますが、「民族」は文化共同体としての意味合いが強い点が、これらとの違いになります。「ゲルマン民族」「民族運動」「少数民族」などのように使われます。
「民俗」との違いは、上記のように「集団」を指す点にあります。文化的な共通項で結ばれた集団の単位が「民族」であり、庶民のならわしを指す「民俗」とは異なります。両者を使い分ける際は、この点に留意しましょう。
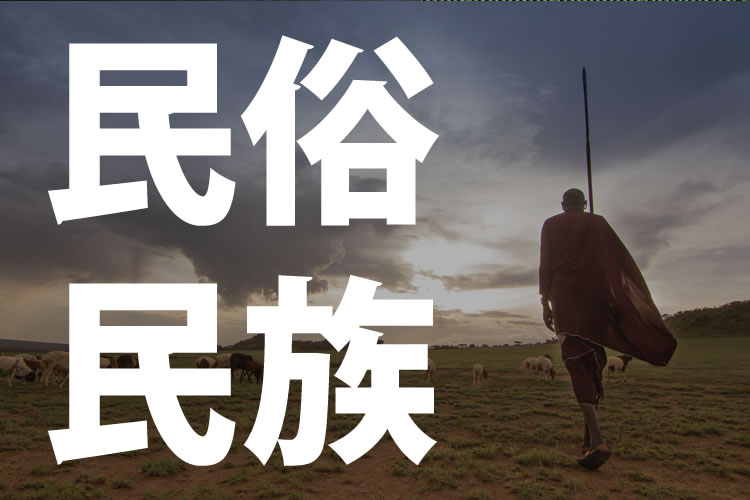
この記事が気に入ったら いいね!しよう