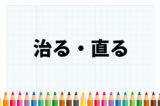一般常識
「傘」「笠」の意味と違い

スポンサーリンク
「傘」「笠」の意味と違いとは
「傘」と「笠」は、どちらも「かさ」と読む漢字です。しかもどちらも似たような役割を持っているため、場合によっては混同して使ってしまうこともあります。しかし、両者には明確な違いがあり、はっきりと使い分けることが可能です。
今回は、「傘」と「笠」の意味や違いについて解説していきましょう。
「傘」とは
「傘」とは、「雨や雪、日光などが体に当たらないよう、頭上にかざして用いる道具」という意味の言葉です。「折り畳み傘」「ビニール傘」「日傘」「唐傘」「こうもり傘」のように使われます。「傘」の字は、「頭の上でひろげるかさ」の象形から成っています。
「傘」と「笠」は、「雨や日光などをさえぎる」という役割においては違いはありません。しかし、その形状や使い方には違いがあります。「笠」の特徴などについては後述しますが、「傘」の場合は、複数の細い骨組みの間に布などを貼って表面を覆い、それに柄をすえた作りのものを指すのが通常です。開閉できる仕組みになっており、使用時には頭上にかざす形で用います。「笠」との区別のために、「さしがさ」と呼ぶ場合もあります。
「笠」とは
「笠」とは、「日光や雨、雪などが直接当たらないよう、頭にかぶるもの」という意味の言葉です。一般に低い円錐形をしており、イグサや藁などの材料から作られます。「編笠」「組笠」「縫笠」「塗笠」などの種類があり、このうち「組笠」には「網代笠」や「檜笠」が、「縫笠」には「菅笠」や「三度笠」などがあります。
「笠」の字は、「竹」「立つ」の象形から成り、「柄がなくて安定しているかさ」を意味しています。
「笠」と「傘」は、同じ語源から来ている言葉です。上記のように、どちらも役割の点では違いはありません。ただ、「笠」は「帽子のように頭にかぶる形で使用する」という点で、「傘」と使い分けることができます。発音による混同を避けるために、「かぶりがさ」と呼んで区別することもあります。
ちなみにキノコの頭やランプのシェードを「かさ」と表現しますが、形状の点では本来「笠」の字が適当であるものの、現在では「傘」と書かれることが多く、どちらも使っても間違いとは言えなくなっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう