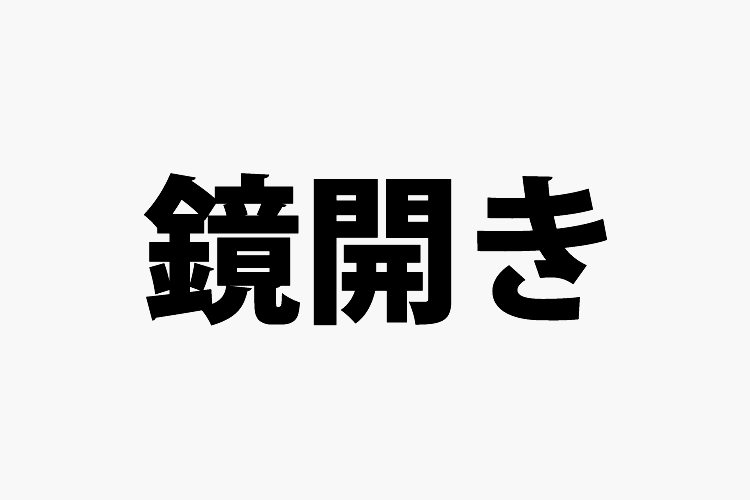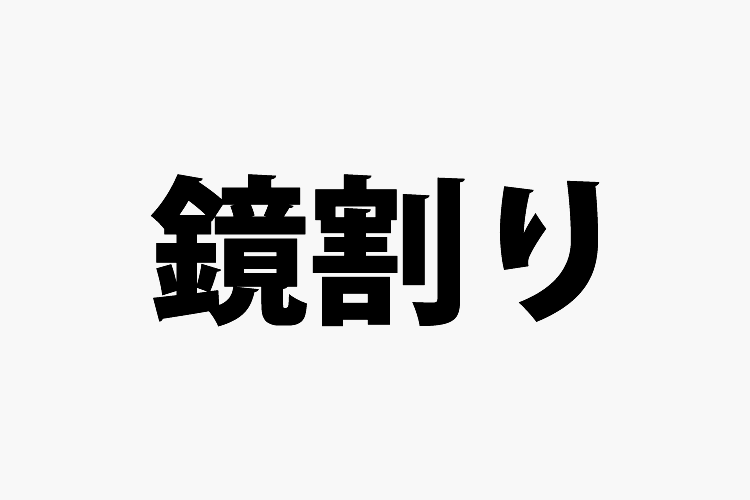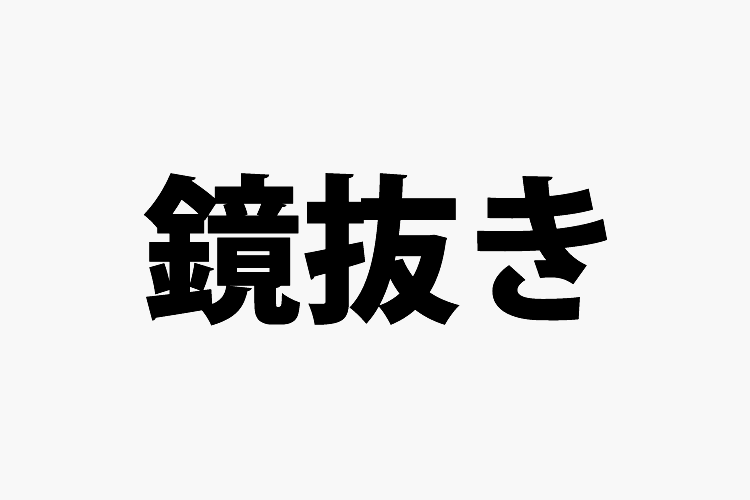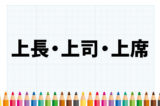一般常識
「鏡開き」「鏡割り」「鏡抜き」の意味と違い

スポンサーリンク
「鏡開き」「鏡割り」「鏡抜き」の意味と違いとは
「鏡開き」「鏡割り」「鏡抜き」という3つの言葉は、すべて同じ行事を指して使われることがあります。しかし、本来の意味からすると、これは決して正確ではありません。では、この3つの言葉は、正しくはどんなことに使うべきなのでしょうか。
今回は、「鏡開き」「鏡割り」「鏡抜き」の意味と違い、使い分けのポイントなどについて解説していきたいと思います。
「鏡開き」とは
「鏡開き」とは、正月行事の1つで、鏡餅をこわして食べることを言います。正月の11日に、それまで飾っていた鏡餅を下ろし、細かく砕いて雑煮や汁粉などに入れ、食べることを意味する言葉です。読み方は、「かがみびらき」になります。
「鏡餅」の由来は諸説ありますが、「丸い餅が鏡(銅鏡)の形に似ていたから」とも言われています。
「鏡開き」の風習は、江戸時代から始まったものです。武家社会では正月の11日(もとは20日)に、男子は具足にそなえた餅を、女子は鏡台にそなえた餅を手や槌で割って、汁粉などにして食していました。その後この風習が庶民の間にも広まり、現在まで続いているという経緯があります。「開く」の語が使われているのは、「割る」の語が縁起が悪いとされるためです。
「鏡割り」とは、後述するように意味の違いはありません。
「鏡割り」とは
「鏡割り」とは、「正月の11日に、鏡餅をくだいて食べること」という意味の言葉です。正月飾りの時期が過ぎた鏡餅を細かく砕き、汁粉などに入れて食べることを言います。読み方は、「かがみわり」になります。「鏡」の字は、「鏡餅」を表しています。
「鏡割り」と「鏡開き」は、上記のように同じ意味の言葉です。どちらも正月11日に鏡餅をこわして食べることを指しており、内容に違いはありません。辞書でも、「鏡割り=鏡開き」としています。そのため、基本的に使い分けの必要もありませんが、一般的には「鏡開き」を使う方が望ましいとされています。その理由は、これも上で述べたように、「割る」の語に良くないイメージが含まれることにあります。
「鏡抜き」とは
「鏡抜き」とは、「祝宴などで、酒樽のふたを木槌などで割って開くこと」という意味の言葉です。結婚式や竣工式などの式典で、出席者にふるまうための日本酒を入れた酒樽の上蓋を、木槌でこわすことを言います。読み方は、「かがみぬき」になります。
「鏡抜き」の「鏡」は、この場合「酒樽のふた」を意味します。これもやはり、丸い形を鏡に見立てたものと言われています。
「鏡抜き」の「抜き」の語感が良くないということで、同じ行為を指して「鏡開き」や「鏡割り」と表現することもありますが、本来はこちらの用法は間違いにあたります。上記のように「鏡開き」「鏡割り」は、「鏡抜き」とは違い、「鏡餅をこわして食べること」を指しています。
一方、報道においては、「鏡抜き」や「鏡開き」の語は使わず、「酒樽を開ける」などと表現することも多くなっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう