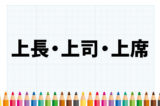一般常識
「稼働率」「稼動率」「可動率」の意味と違い
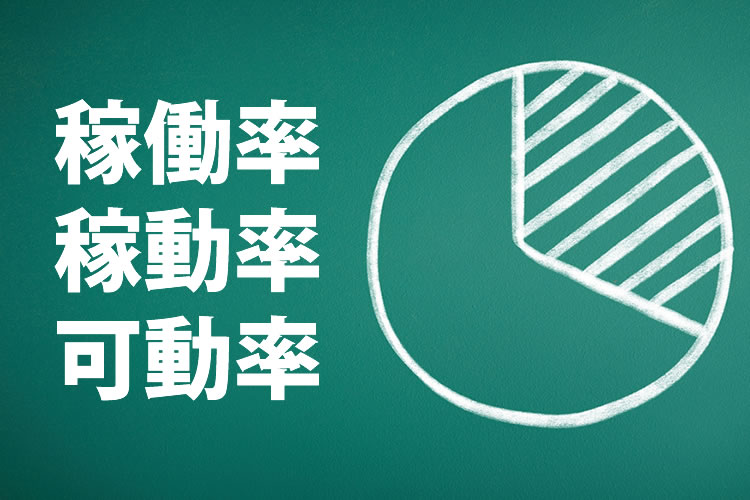
スポンサーリンク
稼働率・稼動率・可動率の意味と違いとは
「稼働率」という言葉は、工場などの製造業においてはよく聞かれるものです。この「稼働率」には、ほかにも「稼動率」という表記があり、どちらが正しいのか迷ってしまう人も多いでしょう。しかも、同じ発音で「可動率」という表記もあるため、ますますややこしくなっています。
そこで今回は、「稼働率」「稼動率」「可動率」の意味と違いについて詳しく解説していきます。
稼働率とは
「稼働率」とは、一般的には「生産実績に対する生産能力の割合」を意味しています。「操業率」とも言います。「稼働率が高い」「稼働率が下がっている」などと使われます。
「稼働率」は工場でよく使われる言葉で、製品がどのくらい効率的につくられているかを表す指標となっています。一般的には、一定時間内でよりたくさんのモノを作れる工場は、稼働率が高いと表現できます。
「稼働率」の求め方は、次のようになります。例えば、1日最大2万4千個の缶詰を作れる工場で、ある日の生産個数が2万個であったとすると、「稼働率」は2万÷2万4千×100=83%となります。つまり、実際に生産した数量を、本来作れるはずの数量で割ったものが、「稼働率」となるわけです。このほかにも、「実際の稼働時間を本来稼動すべき時間で割る」という求め方もあります。
「稼動率」との違いについては、以下で見ていきましょう。
稼動率とは
「稼動率」の意味合いも、「稼働率」と違いはありません。やはり、「生産実績(実際に作ったモノの数)を生産能力(本来作れるはずのモノの数)で割った値」を指します。
このように、「稼働率」と「稼動率」は同じ意味を表しています。「稼働」と「稼動」は、どちらも「かせぎはたらくこと」と「機械が動いて仕事をすること」を指す言葉です。つまり、基本的にはどちらの表記を使っても間違いではありません。
しかし、それでは混乱するということで、報道機関では「稼働」の表記に統一されています。したがって、一般的にはどちらかというと、「稼働率」の方が目にする機会が多くなっています。
可動率とは
「可動率」とは、「機械設備を、必要な時に問題なく動かせる割合」という意味の言葉です。読み方は「かどうりつ」ですが、「稼働率」と区別するために、「べきどうりつ」と読む場合もあります。「可動率を高めるためには、異常の早期検出が必要だ」のように使われます。
「可動率」は、設備の信頼性を表す指標です。例えば、本来設備を動かすはずだった時間が8時間だったのに対し、実際にはトラブルなどにより6時間しか運転できなかったとすると、「可動率」は6時間÷8時間×100=75%ということになります。
このように、「可動率」は設備の運転効率を表すもので、実際に製品が作られる効率を示す「稼働率」とは、意味合いが違います。
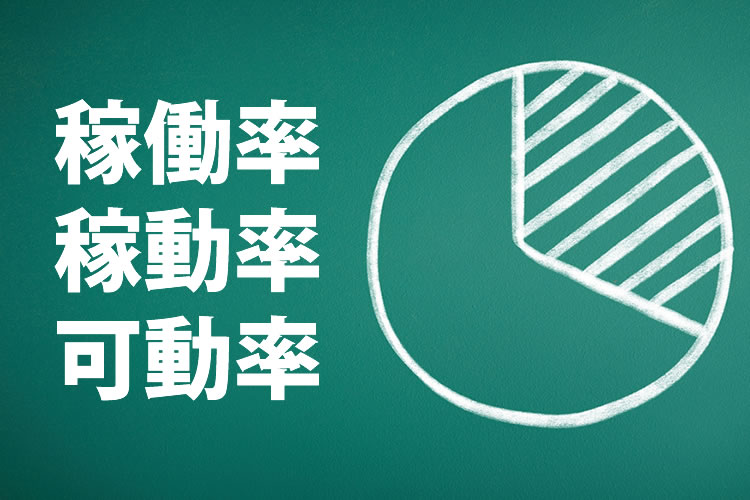
この記事が気に入ったら いいね!しよう