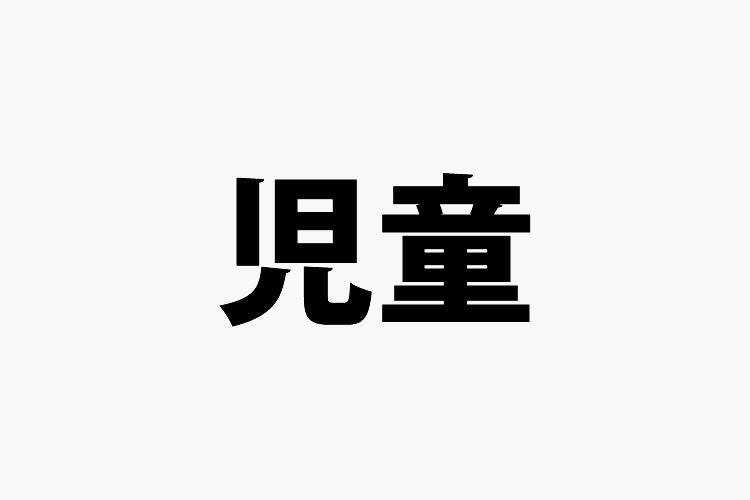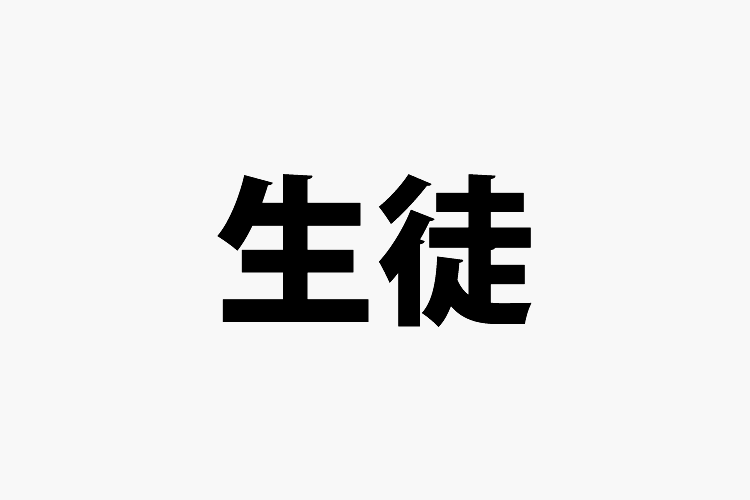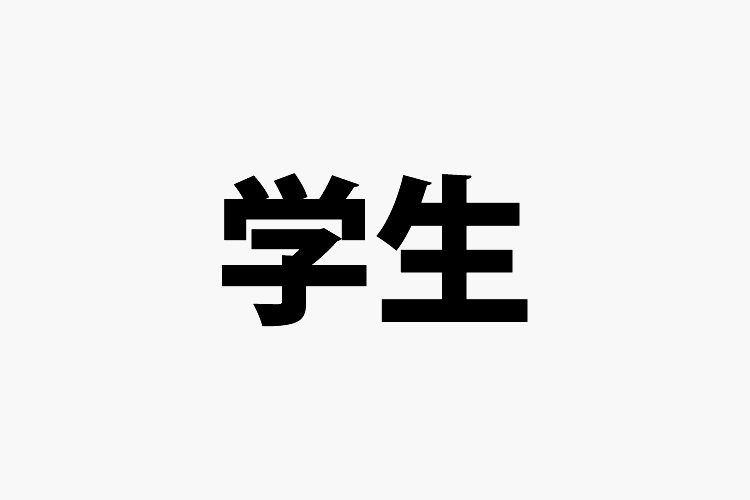一般常識
「児童」「生徒」「学生」の意味と違い

スポンサーリンク
「児童」「生徒」「学生」の意味と違いとは
学校に通っている者を指す言葉に、「児童」「生徒」「学生」の3つがあります。これらはそれぞれ意味するところが違いますが、その違いをきちんと説明できる人は、意外に少ないかもしれません。では、これら3つの言葉は、どのように使い分けるのが正しいのでしょうか。今回は、「児童」「生徒」「学生」の意味と違いについて解説していきましょう。
「児童」とは
「児童」は「心身ともに未発達の子供」を意味する言葉ですが、年齢層としては「幼児」と「青年」の中間、大体6~16歳くらいまでを指すようになっています。読み方は「じどう」で、「児童がのびのびと育てる環境」「児童福祉の理念に合わない」のように使われます。
「児童」の「児」と「童」は、ともに「子供(未成年)」を意味する漢字です。
「児童」は前述のように、一般的な意味では単に「子供」を指しますが、法律では明確に年齢が区切られています。学校教育法における「児童」は、「満6歳から12歳までの、小学校に通っている者」を指すようになっています。つまり、「小学生(特別支援学校の小学部在籍者も含む)=児童」と言うことができます。
「生徒」「学生」との違いについては、以下で見ていきましょう。
「生徒」とは
「生徒」の一般的な意味は、「学校や塾などで教えを受ける者」というものです。読み方は「せいと」で、「彼は非常に優秀な生徒だ」「私はあまりできの良い生徒ではなかった」のように使われます。
「生徒」の「生」の字は、この場合、学者などの呼び名としての役割になります。一方「徒」の字は、「門人」「弟子」の意味になります。
「生徒」も「児童」と同様に、学校教育法で明確に規定されています。それによると、「中学校・高等学校で教育を受ける者」が「生徒」ということになります。
このように、法律における「生徒」と「児童」の違いは、「生徒=中学生、高校生」、「児童=小学生」という点にあります。
「学生」とは
「学生」とは、一般的には「学問をしている人」という意味の言葉です。読み方は「がくせい」で、「学生時代がなつかしい」「まだ学生なのに、考えがしっかりしている」のように使われます。一方これとは違い、「がくしょう」と読むこともありますが、この場合は律令制の大学等で学ぶ者や、寺で学問修行をする僧といった意味合いになります。
「学生」もやはり、法律による明確な規定があります。それによると、「高等教育を受けている者」が、「学生」にあたるとされています。具体的には、大学(短大、大学院も含む)や高等専門学校に在籍している者(聴講生などを除く)が、「学生」ということになります。
このように、「学生」は「大学や高専で教育を受けている者」を指す点が、「児童」や「生徒」との違いになります。以上のような点を踏まえると、3つの使い分けがしやすくなるでしょう。

この記事が気に入ったら いいね!しよう