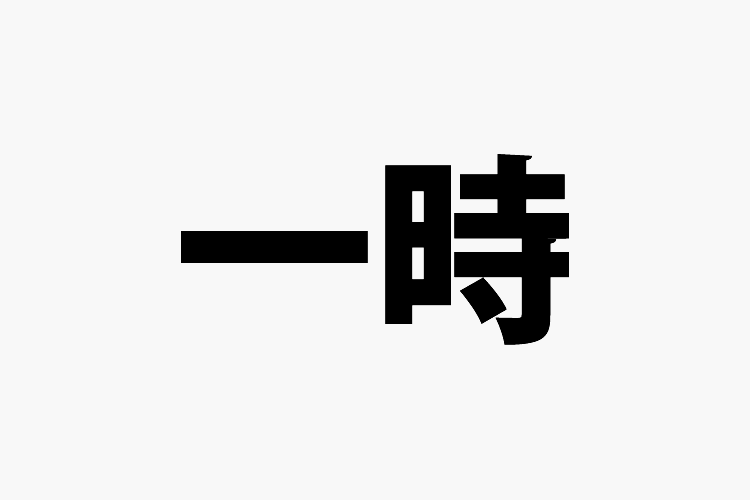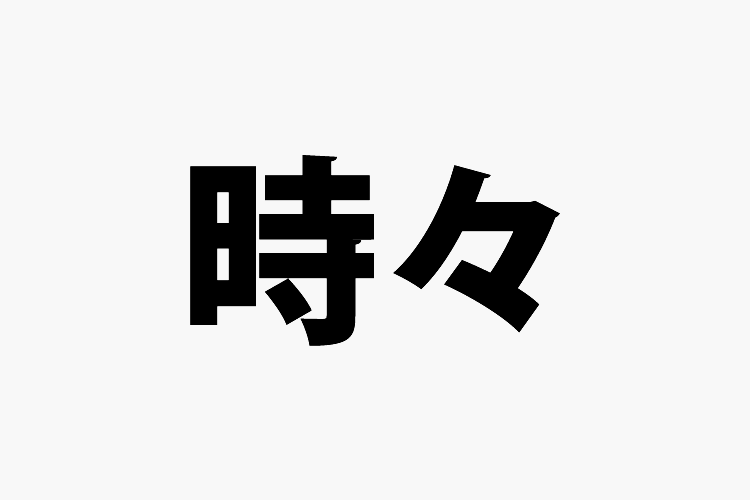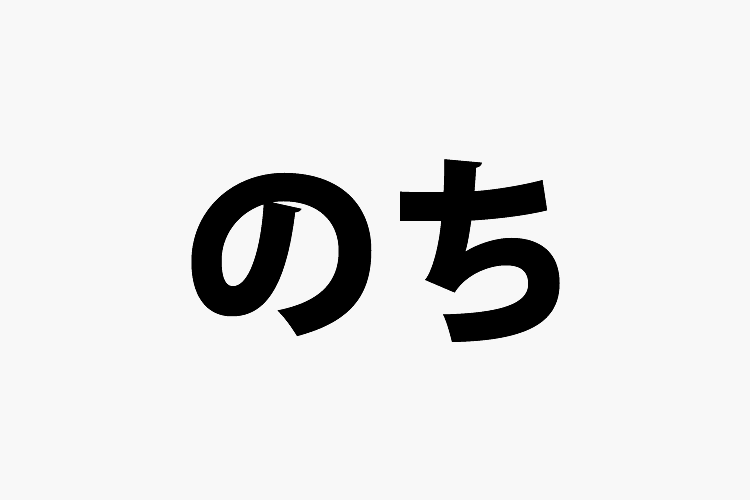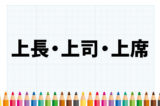一般常識
「一時」「時々」「のち」の意味と違い

スポンサーリンク
「一時」「時々」「のち」の意味と違いとは
天気予報では頻繁に使われるフレーズがいくつかありますが、その代表的なものが、「一時」「時々」「のち」の3つです。「曇り一時雨」「晴れ時々雨」といった具合ですが、これらの言葉は具体的に何を表しているのでしょうか。わかるようで分からないという人もたくさんいるでしょう。
そこで今回は、天気予報における「一時」「時々」「のち」の意味や違いなどについて、詳しく解説していきたいと思います。
「一時」とは
「一時(いちじ)」とは、「ある短い間」「しばらくの間」という意味の言葉ですが、天気予報においては、予報期間の4分の1未満の時間、その現象が連続する際に使われるようになっています。
例えば、明日の予報において「曇り一時雨」という場合は、「明日の24時間のうち4分の1(6時間)に満たない時間、連続して雨が降る」という意味になります。
「一時」と「時々」の違いについては混乱しやすいところですが、その現象が「連続的」か「断続的」かという点で使い分けられます。「時々」は後述するように、雨や雪などの現象が断続的に現れる際に使われますが、「一時」は上記のように、現象が連続して現れる際に使われます。
「時々」とは
「時々(ときどき)」とは、「ある時間を置いて繰り返されるさま」という意味の言葉です。「ときおり」と同じ意味になります。天気予報での意味合いもこれと同様ですが、詳しく言うと、「現象が断続的に起こり、その現象の発現期間の合計が予報期間の2分の1未満のとき」に使われる言葉ということになります。
例えば、明日1日についての「曇り時々雨」という予報の場合、「24時間のうち2分の1(12時間)以上は曇りで、そのほかの間は断続的に雨が降る状態」を指すことになります。
「時々」と「一時」の主な違いは、上で述べたように、「現象の現れ方」にあります。「一時」が連続してその現象が現れることを指すのに対し、「時々」は、現象が断続的に発現することを指します。また、両者は現象の発現時間においても違いがあります。「一時」の場合は、予報期間全体の4分の1未満ですが、「時々」の場合は、予報期間の2分の1未満となっています。
「のち」とは
「のち」とは、「ある時点から後」という意味の言葉です。ある事柄があった後のことについて述べる際に使われ、天気予報においてもこのような意味合いになります。例えば、明日1日についての予報で「曇りのち晴れ」という場合は、「1日のうち途中までの時間はずっと曇りで、その後は晴れが続く」という意味になります。
「のち」の場合は、「一時」や「時々」とはややニュアンスが違います。「一時」「時々」は、「現象の現れ方」と「予報期間における発現時間の割合」を示していましたが、「のち」は「現象が起こる順番」を指す言葉となっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう