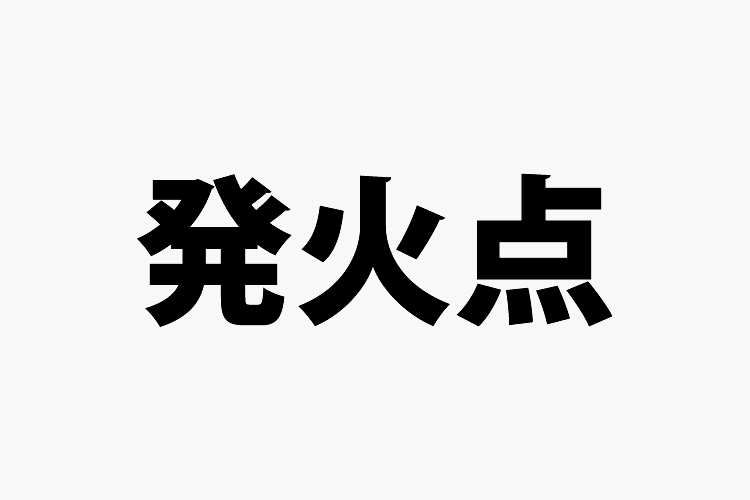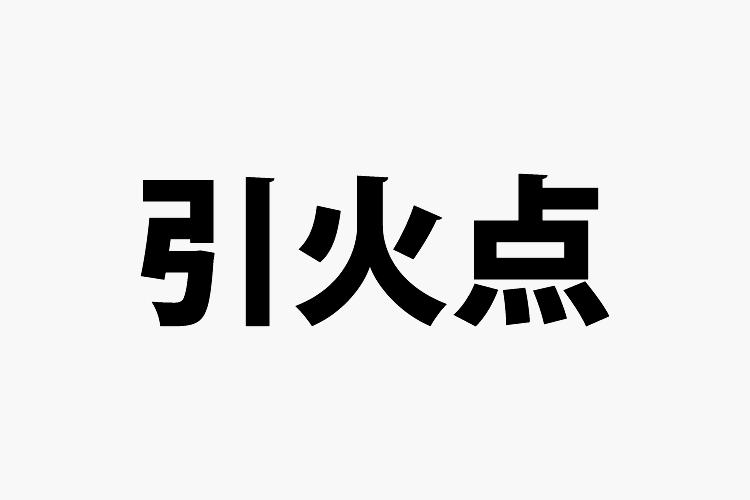一般常識
「発火点」「引火点」の意味と違い

スポンサーリンク
「発火点」「引火点」の意味と違いとは
「発火点」と「引火点」は、どちらも化学に関する用語です。日常で頻繁に使われることはないものの、たまに耳にすることもあるでしょう。しかし、この2つがどのように違うのかは、化学の知識がないとなかなか分かりません。
そこで今回は、「発火点」と「引火点」の意味や違いについて、分かりやすく解説していきたいと思います。
「発火点」とは
「発火点」とは、「物質が空気中で自然に燃え始める最低温度」という意味の言葉です。可燃性物質を空気あるいは酸素中で加熱した時に、火炎を近づけなくても自然に燃焼し始める最低温度を言います。「発火温度」とも呼ばれ、固体燃料の場合には通常「着火点」と言います。読み方は、「はっかてん」になります。
「発火点」は、同じ物質でもその形状や測定法によって大きく異なります。大まかな値では、乾燥した木材が225℃、石炭が335℃、木炭が360℃、ガソリンが300℃などとなっています。
「発火点」と「引火点」は、意味合いも使われ方も全く違います。「引火点」の意味については後述しますが、「発火点」の場合は火を近づけることなく、自然に発火する温度を指す点で使い分けられます。
「引火点」とは
「引火点」とは、「可燃性の物質を加熱していき、これに火を近づけた時引火するのに必要な濃度の蒸気を発生する最低温度」という意味の言葉です。簡単に言えば、物質(主に液体)に火を近づけた際、その物質が燃えだす最低の温度を指します。読み方は、「いんかてん」です。例えばガソリンの引火点は-40℃以下で、灯油は30℃以上となっています。
「引火点」と「発火点」は、上記のように意味合いは全く違います。「発火点」が火を近づけなくても物質が燃え上がる最低温度を指すのに対し、「引火点」は、火を近づけた際に物質が燃え上がる最低温度を指しています。また、「発火点」では物質の形状は特に決まっていないのに対し、「引火点」は主として液体に対し使われるという点も、両者の違いとなっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう