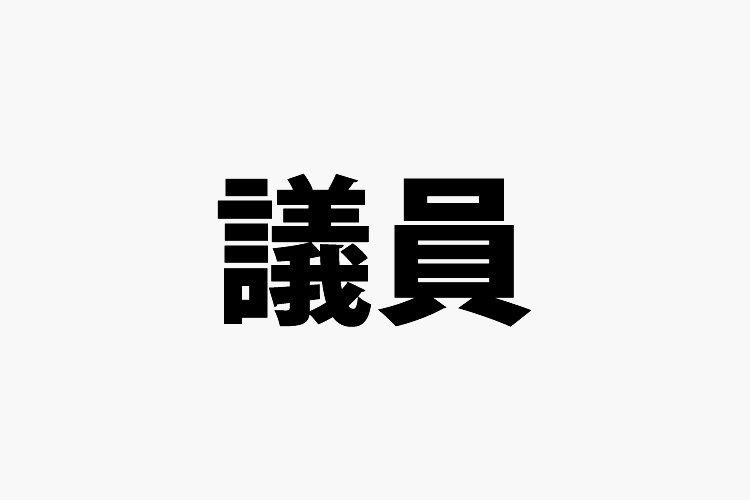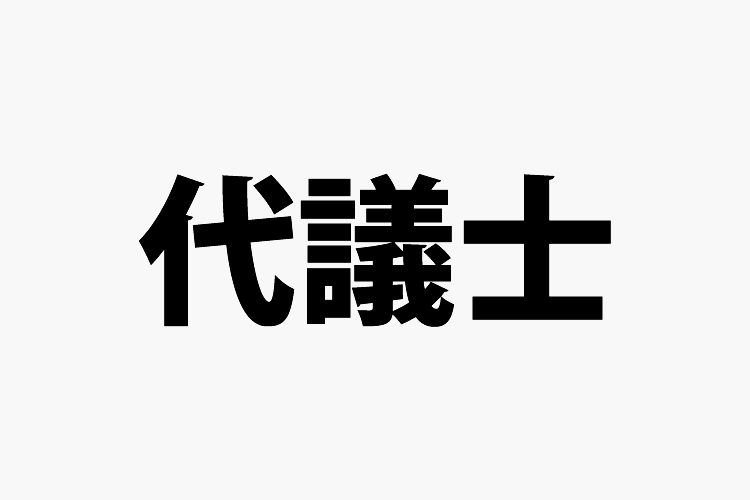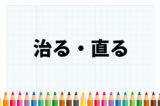一般常識
「議員」「代議士」の意味と違い

スポンサーリンク
「議員」「代議士」の意味と違いとは
「議員」と「代議士」という2つの言葉は、共によく似たイメージを持っています。実際に、この2つを同義の言葉と思っている人も多くいますが、正確には同じではありません。では、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
今回は、「議員」と「代議士」の意味や違いについて、詳しく解説していきましょう。
「議員」とは
「議員」とは、広義には「合議機関の構成員」を意味する言葉ですが、一般的には「国会や地方議会の構成員」という意味合いで使われています。「国会や地方議会等の議会を構成し、かつ議決権を持つ者」の意味で使われるのが通常です。読み方は「ぎいん」で、「参議院議員に立候補する」「市会議員を3期務めた」のように使われます。
「議員」の「議」は、「はかる」「言う」「意見」などの意味を持ちます。一方「員」の字は、この場合「かかり」「つかさ」などを意味しています。
「議員」と「代議士」は、どちらも選挙で選ばれる議会の構成員という点で違いはありません。しかし、それぞれが表す範囲には違いがあります。「議員」の場合、国会の衆参両議員をはじめ、市会議員や町会議員などの地方議員まで含めたものを指す点が特徴です。
「代議士」とは
「代議士」とは、「直接選挙で選ばれ、国民の代表として国政を議する(審議する)人」という意味の言葉ですが、一般的には「国会議員」、特に「衆議院議員」を指して使われるようになっています。読み方は「だいぎし」で、「代議士の○○先生に挨拶をお願いする」「彼の家系は代議士を多く輩出している」のように使われます。
「代議士」の「代議」とは、「他人に代わって議すること」を意味しており、この場合は「国民の代表」という意味合いになります。
このように、「代議士」と「議員」は、「衆議院議員以外も含むかどうか」という点で使い分けられます。「議員」とは違い、「代議士」は衆議院議員のみを指すのが通常です。
「代議士」が衆議院議員の俗称となった由来は、大日本帝国憲法時代の政治システムにあります。当時は議会が貴族院と衆議院に分かれていましたが、そのうち選挙で選ばれていたのが衆議院議員のみだったため、「衆院議員=代議士」と呼ばれるようになりました。

この記事が気に入ったら いいね!しよう