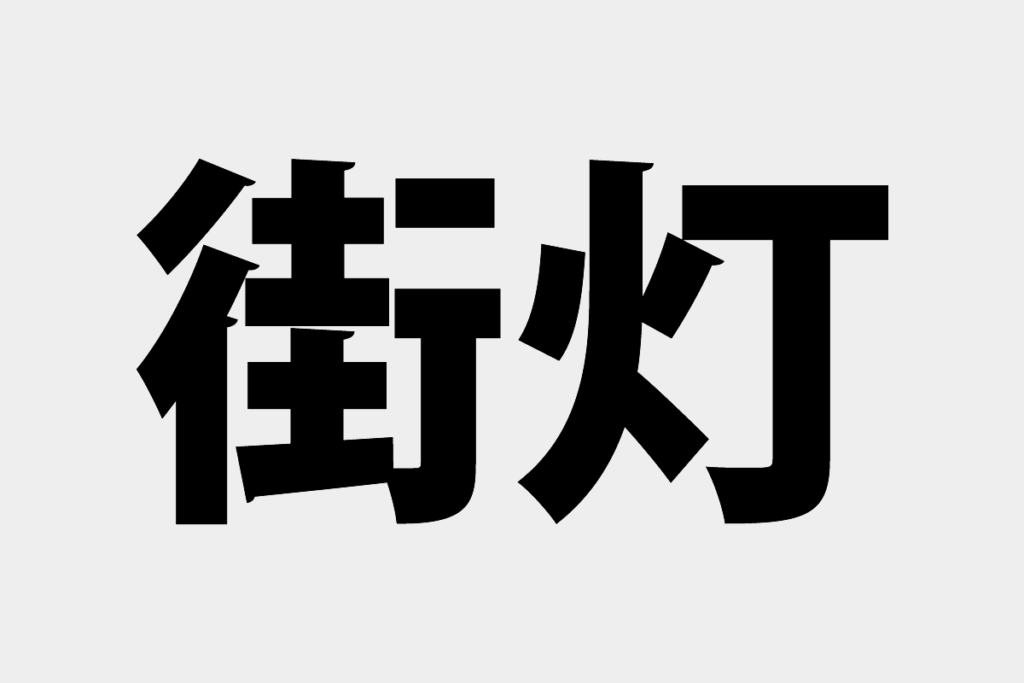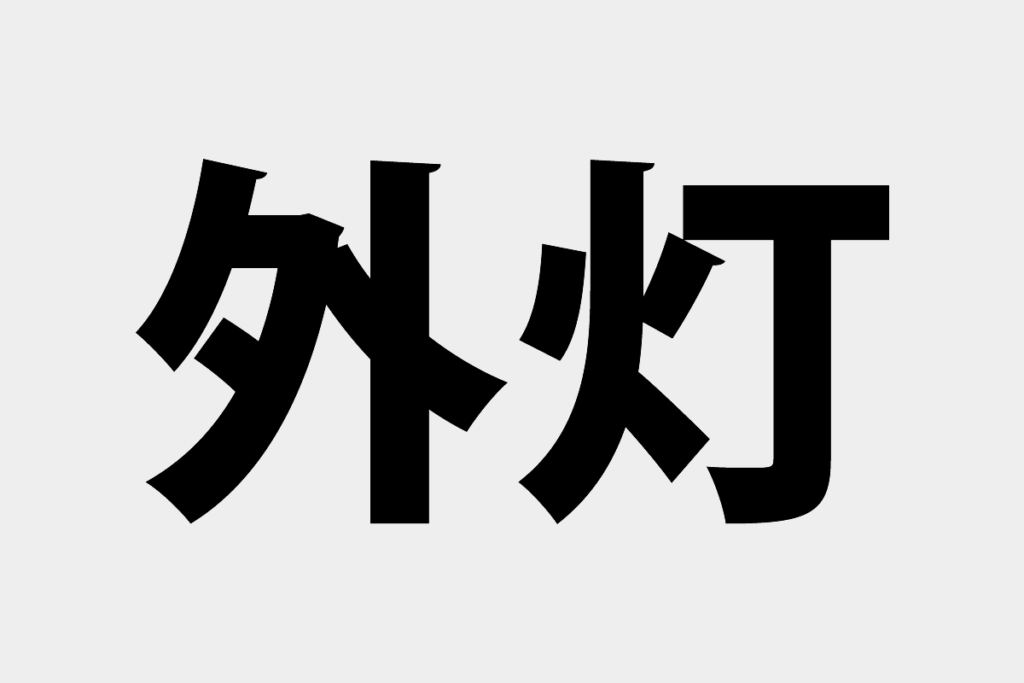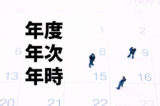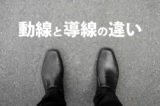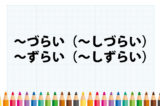一般常識
「街灯」と「外灯」の意味と違い

スポンサーリンク
街灯・外灯の意味と違いとは
「街灯」と「外灯」は、どちらも「がいとう」と読む熟語です。読みだけでなく、共に「灯」の字が入っていることから、意味合いを混同してしまうことも多いでしょう。しかし実際には、この2つは別の種類の明かりを指しています。では、具体的にそれぞれどういった照明を意味するのでしょうか。
今回は、「街灯」と「外灯」の意味や違いについて解説したいと思います。
街灯とは
「街灯」とは、「街路を明るくするための電灯」という意味の言葉です。主に防犯上の目的から、市街の道路上に設けられた照明を言います。道路だけでなく、広場や公園などの場所に設けられたものについても、「街灯」と呼ばれます。また、目的も防犯だけに限らず、交通安全用や都市の美観用としても用いられます。
「街灯」の起源は古く、古代ローマ時代までさかのぼります。アンティオキアでは、浴場や盛り場などの近辺に、ロープに吊るされる形でランプの照明が設けられていました。またローマにおいては、競技の実施のため、公共広場の夜間照明も行われていました。さらに16世紀のパリでは、街頭での泥棒や放火に対処するため、街路に面した家の窓の前を、夜間照明し続けるよう命令が出されるなどしています。
「外灯」との違いについては、以下で見てみましょう。
外灯とは
「外灯」とは、「建物の外に取り付けた電灯」という意味の言葉です。屋外に取り付ける照明ということから、「外灯」の名がつけられています。「屋外灯」「エクステリアライト」などとも呼ばれます。具体的には、玄関やエントランスに設置されて、表札や入り口を照らす役割などを持ちます。「外灯」があるおかげで、建物の美観が整うだけでなく、夜間でも安心して家の周辺を歩くことができます。また、センサー付きのスポットライトなど、防犯上の役割も持ちます。
このように、「外灯」は主に個人の敷地に設置されるものを指す点が、「街灯」との違いになります。こうした違いを踏まえておくと、使い分けに困らずにすむでしょう。

この記事が気に入ったら いいね!しよう