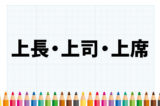一般常識
「同志」「同士」「有志」「仲間」の違い

スポンサーリンク
同志・同士・有志・仲間の違い
「共通した何かを持つ人」という意味の言葉には、さまざまなものがあります。「同士」や「同志」といったものがそれですが、これらはそもそも、どのような違いを持つのでしょうか。それぞれの細かい意味合いについて知りたいところです。
そこで今回は、「同志」「同士」「有志」「仲間」という4つの言葉について、それらの意味や違いを詳しく解説していきます。
同志とは
「同志」とは、「主義・主張を同じくすること、またはそういった人」という意味の言葉です。文字通り、同じこころざしを持つ人物のことを言います。読み方は「どうし」となります。
「同」は「ひとしい」や「一緒」といった意味を持ち、「志」は「ある方向を目指す気持ち」「目的」といった意味を持ちます。「同志が集う」「同志打ち」「同志を得る」などのように使われます。
「同志」と「同士」は、辞書では同じ意味合いの言葉として載せられていますが、実際には場面に応じて使い分けがされます。「同志」のポイントは「こころざし」という点にあり、信条や信念といった、気持ちの面で一体となった人たちを指して使われるのが通常です。
一方、「同士」との違いについては、以下で見てみましょう。
同士とは
「同士」とは、「お互いにある共通した境遇に置かれた人」という意味の言葉です。読み方は、やはり「どうし」で変わりません。
「同」の意味は上で紹介した通りで、「士」は「つわもの(兵隊)」や「役人」などさまざまな意味を持ちますが、この場合は「立派な人(男子)」といった意味合いになります。
「同士」は上記のように、「同志」とは使われ方に違いがあります。「同士」の場合、「置かれた環境がなんとなく似ている」というだけの人も含み、特に目的や主義主張が同じとは限りません。こうした範囲の広さは、「同志」との大きな違いと言えます。また「同士」は、他の名詞の下について、接尾語として使われることが多いという点も特徴です。例えば、「隣人同士」「恋人同士」のような具合です。
有志とは
「有志」とは、「ものごとを一緒に行おうという意思、もしくはそうした気持ちを持つ人」という意味の言葉です。読み方は、「ゆうし」になります。
「志」は上で見た通りの意味合いで、「有」は「ある」「持っている」という意味になります。「有志を募る」「有志者」などのように使われます。
「有志」は、「同じ目的や気持ちを持つ人」という意味では、「同志」と似ています。しかし、使われ方には明確な違いがあります。「有志」が使われるシチュエーションは、共同で贈り物をする時や香典を出す時、また飲み会を開く時などが主です。贈り物の場合は「有志一同」などと書き、香典には「株式会社○○ 有志」などと書くのが一般的です。
仲間とは
「仲間」とは、「一緒に何かのものごとを行う人」を意味する言葉です。「なかま」と読まれます。「仲」は「人と人との間柄」を表し、「間」は「人と人との相互の関係」を表します。
「仲間」は、もともと江戸時代の組合のようなものを指す言葉ですが、現在ではより広い意味合いで使われています。現代の使われ方としては、仕事や共通の目的に対し、一緒に取り組んでいる人を指すのが通常です。単なる友達も含みますが、使命感や目的意識といったものを共有しているというニュアンスが強くなっています。その意味では「同志」と近くなっていますが、「仲間」の方がよりカジュアルに幅広く使われるという違いがあります。

この記事が気に入ったら いいね!しよう