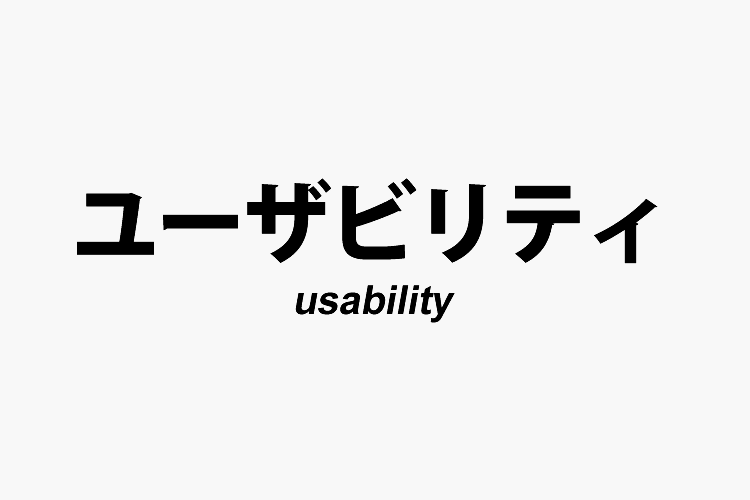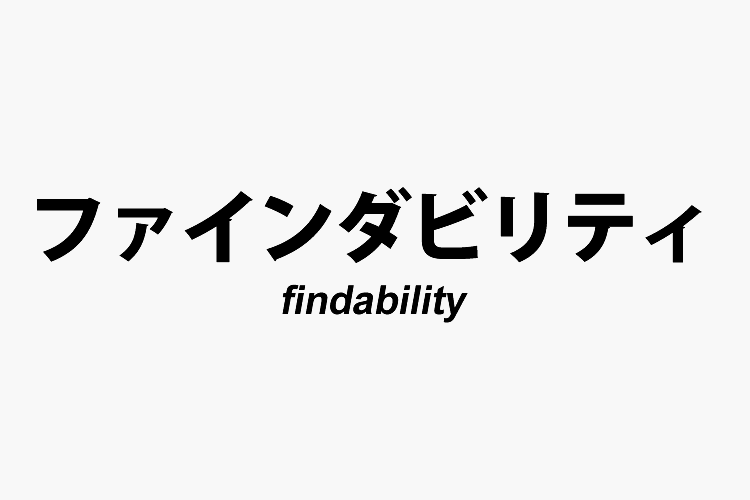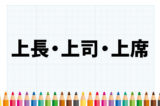インターネット
「ユーザビリティ」「アクセシビリティ」「ファインダビリティ」の意味と違い
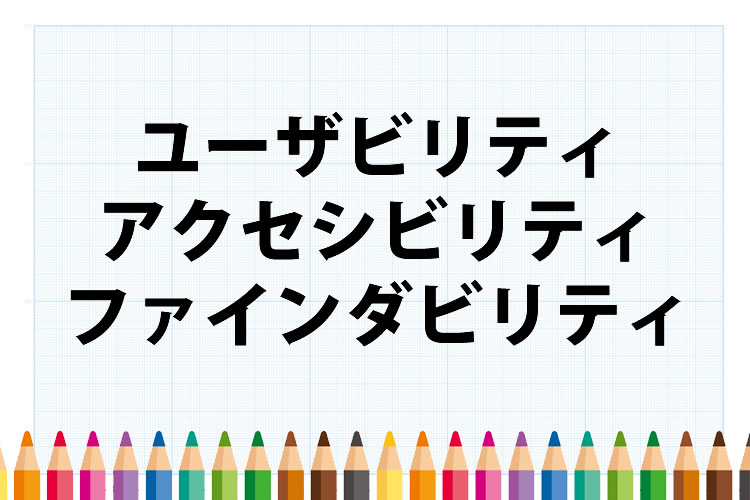
スポンサーリンク
「ユーザビリティ」「アクセシビリティ」「ファインダビリティ」の意味と違いとは
「ユーザビリティ」や「アクセシビリティ」という言葉は、インターネット関連の用語としてよく聞かれます。しかし、あまり詳しくない人にとっては、今一つ違いが分かりにくいところでしょう。一体これらは、具体的にどのような意味を持つのでしょうか。
今回はこの2つの語の意味や違いに加え、「ファインダビリティ」との違いについても詳しく解説していきます。
「ユーザビリティ」とは
「ユーザビリティ」とは、「使いやすさ」を意味する英語「usability」から来ている外来語です。文字通り「ある物の使い勝手の良さ」を指しますが、一般的には「Webサイトやソフトウェアなどの操作性や使いやすさ」の意味で使われることが多くなっています。
具体的には、ユーザーにストレスを与えない操作性やデザインの分かりやすさ、目標達成までの労力の少なさなどを指します。「このWebサイトはユーザビリティが高い」「ユーザビリティ検証サービス」などのように使われます。
「アクセシビリティ」や「ファインダビリティ」との違いについては、以下で詳しく見ていきましょう。
「アクセシビリティ」とは
「アクセシビリティ」とは、「近づきやすさ」の意味を持つ英語「accessibility」から来ている外来語です。IT分野においては、「身体や能力の違いによらず、機器やソフトウェア、情報などがさまざまな人から同じように利用できる状態」という意味になりますが、一般的には「インターネットへのアクセスのしやすさ(Webアクセシビリティ)」の意味で使われることが多くなっています。「どのような環境でも、誰もが平等にインターネットにアクセスできる状態」が、理想の「アクセシビリティ」であるとされます。
このように、「ユーザビリティ」は「ユーザーにとっての使いやすさ」を表し、「アクセシビリティ」は「ユーザーのインターネットへのアクセスのしやすさ」を表す点が、両者の違いとなっています。別の言い方をすれば、「ユーザビリティ」は「アクセシビリティ」を構成する一要素ということになります。
「ファインダビリティ」とは
「ファインダビリティ」とは、「見つけやすさ」を意味する英語「findability」に由来する外来語です。簡単に言えば「ネット上の情報の見つけやすさ」のことで、ユーザーがコンテンツなどの情報を探す上で、どれだけ見つけやすく作られているかを測る指標となっています。「ファインダビリティを高める」などのように使われます。
「ファインダビリティ」が向上すれば、それだけ情報がスムーズに見つかり、ユーザーの使い勝手が増すことになります。つまり「ファインダビリティ」は、「ユーザビリティ」の一要素と言うことができます。以上のような違いを踏まえると、3つの語の使い分けがしやすくなるはずです。
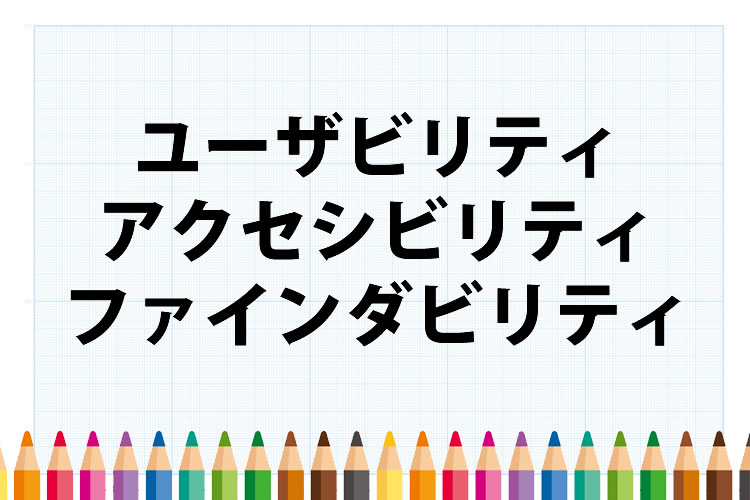
この記事が気に入ったら いいね!しよう