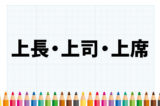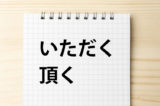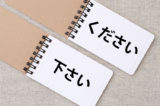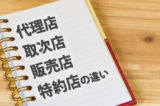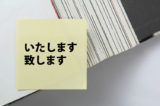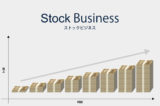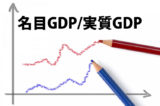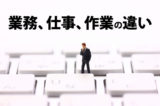ビジネス用語
「ナレッジ」の意味とは?使い方や例文、「ノウハウ」との違い

スポンサーリンク
「ナレッジ」の意味とは?使い方や例文、「ノウハウ」との違い
ビジネス用語として使われるカタカナ言葉の中には、本来の意味合いからすると、やや特殊な使われ方をしているものがあります。「ナレッジ」もその1つですが、一体どんな意味を表しているのでしょうか。
今回は、ビジネスシーンで使われる「ナレッジ」の意味や用法などについて、詳しく解説していきましょう。
「ナレッジ」の意味
ビジネスでの「ナレッジ」の意味
「ナレッジ」は、一般的には「知識」や「情報」を指す言葉です。しかし、ビジネスシーンで使われる場合には、やや異なる意味を持ちます。ビジネス用語としての「ナレッジ」が指すのは、「企業にとって有益な、個人が持つ知識や経験、ノウハウ、スキルなどを集めて体系化した情報」といった意味です。
例えば、長年クレーム対応で培ってきた知識やスキルをまとめてマニュアルにするといったことが、「ナレッジ」にあたります。
「ナレッジ」の由来
カタカナ語の「ナレッジ」は、英語の「knowledge」に由来しています。「knowledge」は動詞「know(知る、知っている)」の名詞形で、「知っていること」「知識」「情報」「学識」などを意味します。例えば「a fund of knowledge」という場合には、「薀蓄」の意味になり、「hunt after knowledge」という場合には、「知識をあさる」の意味になります。
「ナレッジ」の使い方・例文
「ナレッジ」の意味について分かったところで、実際の使い方についても見ておきましょう。ビジネス用語としての「ナレッジ」は、以下の例文のように使われます。
- 例文:「ナレッジを活用して生産性を向上させることは、働き方改革の観点から見ても重要だ」
- 例文:「業績低迷の一因として、ナレッジの共有がうまくいっていないことが挙げられる」
- 例文:「いかに個々の社員が持つナレッジを組織に循環させるかが、後進の育成にとっても大きな意味を持つ」
「ナレッジマネジメント」とは
「ナレッジ」という言葉は、ビジネスシーンでは「ナレッジマネジメント」という形で使われることが多くなっています。ここでは、「ナレッジマネジメント」の意味などについて見ていきましょう。
「ナレッジマネジメント」の意味
「ナレッジマネジメント」とは、個人やグループが持つ知識や、社内の各部門に蓄積された知識情報を、組織全体で共有し活用する仕組みを指します。また、そうした経営手法についても言います。日本語では「知識管理」などと訳され、英語表記(knowledge management)の頭文字を取って、「KM」と呼ばれることもあります。
「ナレッジマネジメント」の手法
「ナレッジマネジメント」には、大きく分けて4つの手法があります。1つは「経営資本・戦略策定型」と呼ばれるもので、社内の知識を多角的に分析し、経営戦略に活かすという手法になります。2つ目は「顧客知識共有型」で、顧客と共通の経験をしてノウハウなどを共有することで、顧客に対しより価値ある知識の提供を可能にしようという手法になります。
3つ目は、「ベストプラクティス共有型」で、こちらは模範的な社員の思考や行動を形式知化し、全体で共有することで、会社全体のスキルを上げるという手法です。4つ目は「専門知識型」で、これは「ノウフー(know who=社内で誰がどんな知識を持つかを検索できる仕組み)」と呼ばれるシステムを基礎に、社内の専門家の知識を総合的に活用しようという手法になります。
「ナレッジ」と「ノウハウ」の違い
ところで、「ナレッジ」と似た言葉に「ノウハウ」というものがあります。これらはビジネスシーンでどのように区別されて使われているのでしょうか。この項目では、その点について見ていきましょう。
「ノウハウ」とは
「ノウハウ」とは、英語の「know how」をカタカナ化した言葉です。もともとの意味は「方法を知ること」といったものですが、そこから転じて「実際的、専門的な知識・技術やその蓄積」の意味で使われるようになりました。「先輩の仕事ぶりから細かいノウハウを吸収した」のように使われます。
「ナレッジ」との違い
「ノウハウ」は「知識・技術」を指す点で「ナレッジ」と同様ですが、「実際的、専門的」という意味合いが入るのが特徴です。言い換えれば、「ノウハウ」は「ある作業などについての具体的な方法や手順を知っていること」を指すことになります。これに対し、「ナレッジ」は前述のように、「企業経営に有益となる体系化された情報」を指します。
こうしたことからわかるように、「ナレッジ」は「ノウハウ」よりも広い概念であり、「ナレッジ」の中に「ノウハウ」が含まれると言うことができます。
最後に
以上、ビジネス用語としての「ナレッジ」の意味や使い方などについて、例文付きでいろいろと紹介してきました。
このように、「ナレッジ」という言葉はビジネスにおいて、「個人が持つ知識や技術を体系化した、企業にとって有益な情報」という意味を持ちます。単なる知識や技術とは異なるので、その点はよく踏まえておきましょう。また、「ナレッジマネジメント」も頻出する用語なので、一緒に覚えておくと便利です。

この記事が気に入ったら いいね!しよう