コミュニケーション
「いただく」と「頂く」の正しい使い分け方と違い
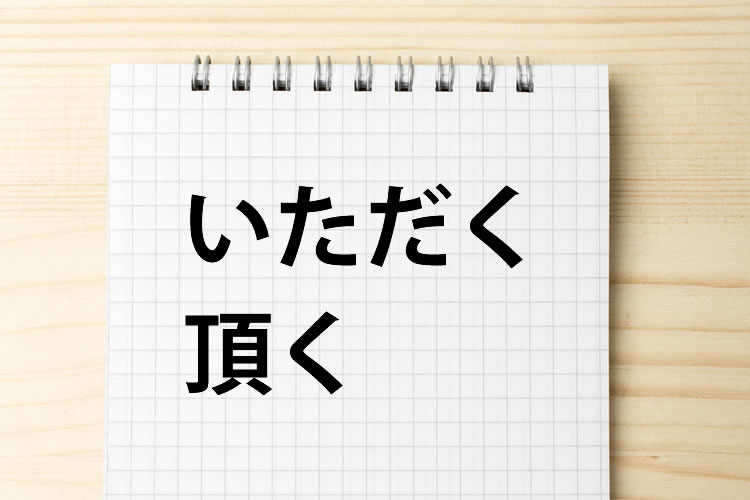
スポンサーリンク
「いただく」と「頂く」の正しい使い分け方と違いについて
「いただく」と「頂く」の違い
日本語での「イタダク」という言葉には、主に「いただく」と「頂く」の二つの表記が使われます。どちらも同じ意味を表していそうですが、実際には明確な違いが存在します。
まずはそれぞれの意味について見ていきましょう。
「いただく」の意味
ひらがなで「いただく」と書く際は、補助動詞として使う場合が主です。補助動詞とは、文章の付属として補助的な意味を持つようになった動詞のことで、補助動詞をひらがなにすることは、文部科学省の定めによります。
「いただく」の場合は、言葉の後ろに付くことで、「何かを~してもらう」という意味を持つようになっています。具体的には、「お越しいただく」「お呼びいただく」「ご覧いただく」などのような使い方になります。
「頂く」の意味
漢字表記で「頂く」と書く場合には、動詞としての使い方が一般的です。こちらの場合、主に「食べる、飲む」「もらう」の謙譲語といった意味を持ちます。具体的には、「ごはんを頂く」「褒美を頂く」「お土産を頂く」などのように使います。「頂戴する」の「頂」と考えると、覚えやすいでしょう。
「いただく」と「頂く」の使い方と例文
「いただく」と「頂く」の意味や使い方の違いについては、上記の通りです。ここではそれぞれの詳しい使い方について、例文を挙げて紹介していきましょう。
「いただく」の使い方
「いただく」は前述のように、補助動詞として「~をしてもらう」という意味合いを持つようになっています。動詞の後に付いて、「~ていただく」や「お(ご)~いただく」「~させていただく」などの形で使われます。具体的には、以下のような使い方になります。
- 例文:後で会議室まで来ていただけますか
- 例文:大変申し訳ございませんが、本日は病気のため欠席させていただきます
「頂く」の使い方
漢字表記の「頂く」の場合、これも前述のように、動詞として「もらう」「食べる、飲む」の謙譲語となります。具体的には、以下のように使われます。
- 例文:先日のお土産の品は、スタッフ全員でおいしく頂きました
- 例文:皆さまから温かい励ましを頂き、感謝の念に堪えません
最後に
以上、「いただく」と「頂く」の意味や使い方の違いについて紹介してきました。
「いただく」は補助動詞としての使い方で、「~して(させて)もらう」という意味になります。一方漢字表記の「頂く」では、「もらう」や「食べる、飲む」の謙譲語としての働きとなります。「~させて頂く」などのような使い方は誤用となりますから、両者を正しい表記で使い分けるよう心がけましょう。
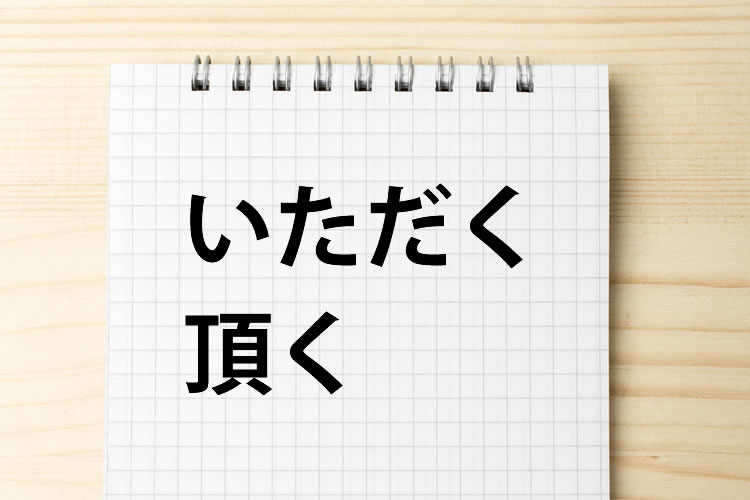
この記事が気に入ったら いいね!しよう


























