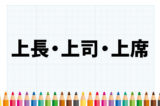ビジネス知識
「定価」「希望小売価格」「オープン価格」の違い
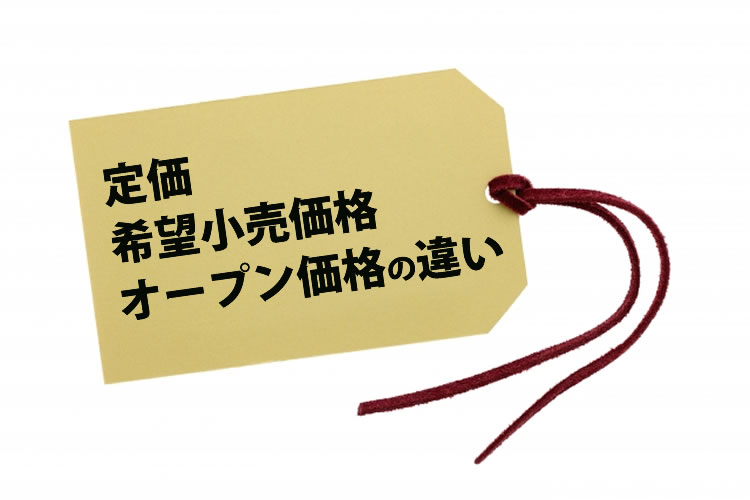
スポンサーリンク
定価・希望小売価格・オープン価格の違いとは
どんな商品にも必ずついている価格ですが、その呼び名は一定ではありません。「定価」や「希望小売価格」など、さまざまなものがあります。
それらの意味は知っているようでいて、実は詳しく説明できないという人も少なくないでしょう。
そこで今回は、「定価」「希望小売価格」「オープン価格」という3つの言葉の意味と違いについて解説していきます。
定価とは
定価とは、文字通り「定まった価格」を意味する言葉です。物の価格は場合によって変動することもありますが、定価とついている場合は、どんな状況でも変わることはありません。いつでもどこでも、同じ一定の価格となっています。
定価という言葉は、以前は必ずしもこうした意味合いではなく、かつてはメーカーが小売業者へ品物を卸す際の価格、つまりメーカーが小売業者へ販売する際に商品につけられた価格に対して言われることがほとんどでした。
しかし現在では、メーカーが指定した商品の価格を、小売業者に対し一貫して守らせることという意味合いで使われるのが一般的です。つまり、小売業者はこの定価以外の価格をつけることができず定価で商品を販売することとなります。
これは「再販売価格維持」や「再販行為」などと呼ばれるもので、書籍やCDなどの著作物や、タバコに対して適用されます。
一方、「希望小売価格」などとの違いについては、以下で見ていきましょう。
希望小売価格とは
希望小売価格とは、メーカーが小売業者に対して示した商品の価格という意味の言葉です。文字通りメーカー側が希望する価格で、小売業者にその値段で販売するよう求めるためのものになります。
希望小売価格と定価との違いは、小売業者側が価格を変えられるかどうかという点にあります。定価では、前述のようにメーカー側が決めた価格を、小売店が勝手に変えることはできません。それに対し希望小売価格では、小売業者はメーカーの要望に沿わなくても良いようになっています。
つまり、小売業者側の判断で、自由に価格を変えられるわけです。これは独占禁止法に基づく権利として、再販制度が適用されるものを除いた、すべての商品に当てはまるようになっています。
オープン価格とは
オープン価格とは、メーカーが小売業者に対し価格の提示をせず、販売価格の設定を一任するという意味の言葉です。メーカー側は出荷価格だけを決め、実際に店頭で販売する価格は、小売業者が自由に決めることができます。
この説明では、希望小売価格との違いが分かりづらいところですが、オープン価格が広まったのにはいくつか理由があります。
1つは、1980年代に激化した家電の値下げ競争により、希望小売価格が有名無実化(存在はするが実際には意味がないこと)してしまったことです。そのため公正取引委員会から、製品の価格を実際の市場価格に近付けるよう通達が行われ、オープン価格の採用が広がりました。
もう1つはメーカー側の理由ですが、オープン価格にすることで希望小売価格と実際の販売価格とのギャップがなくなるため、ブランドイメージを守りやすくなることからです。
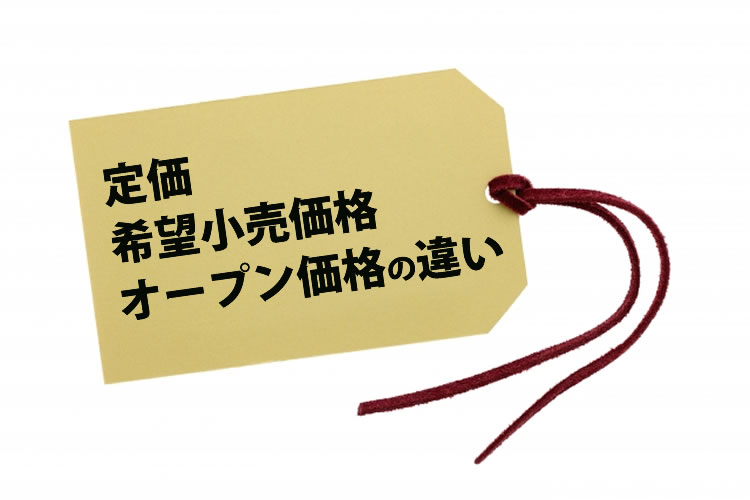
この記事が気に入ったら いいね!しよう