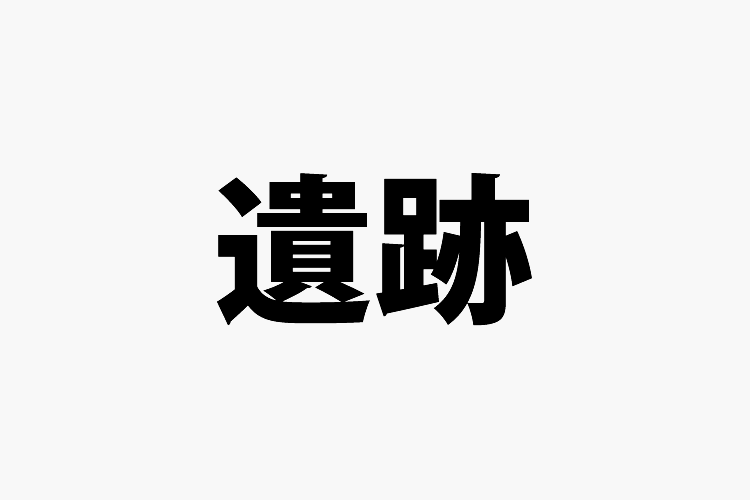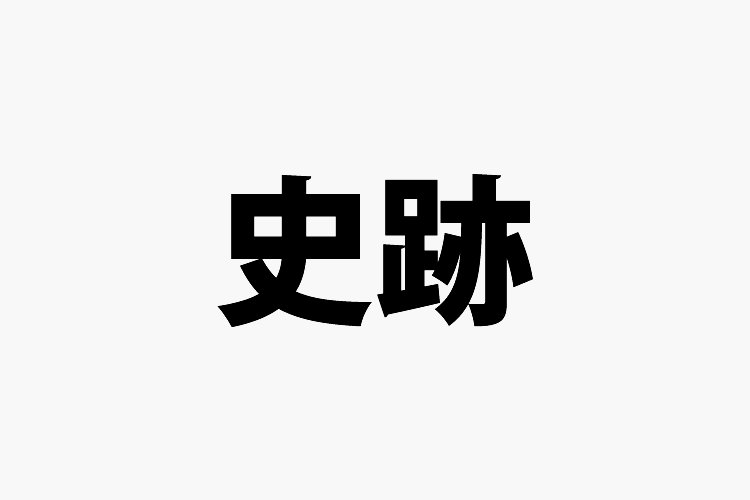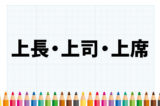一般常識
「遺跡」「史跡」の意味と違い

スポンサーリンク
「遺跡」「史跡」の意味と違いとは
古墳や貝塚のような「遺跡」の存在は、歴史を知る上で貴重な手掛かりです。ところで、この「遺跡」と似た言葉に「史跡」がありますが、両者の違いはどこにあるのでしょうか。歴史ファン以外の人にとっては、かなり難しい問題かもしれません。
そこで今回は、「遺跡」と「史跡」の意味や違いについて、詳しく解説していきたいと思います。
「遺跡」とは
「遺跡」とは、「過去の人間の活動の跡が残されていることが確認できる場所」という意味の言葉です。かつての人類の生活や活動の痕跡が残る場所を言い、具体的には貝塚や古墳、集落跡といった、遺構や遺物の残る場所がそれにあたります。読み方は、「いせき」になります。具体例としては、奈良県の「纏向遺跡」、佐賀県の「吉野ケ里遺跡」、カンボジアの「アンコール・ワット」、ヨルダンの「ペトラ遺跡」などが挙げられます。
「遺跡」の「遺」の字は、「残る」「とどめる」を意味し、「跡」の字は「以前に何かがあったしるし」を意味します。
「遺跡」と「史跡」は、広い意味での違いは特にありません。ただ、「法律による指定保護の有無」という点で使い分ける場合もあります。「遺跡」の場合、「史跡とは」違い、法律で指定保護されないものを指すケースが多くなっています。
「史跡」とは
「史跡」は、広義には「過去から現代にいたるまでの、人類の活動を示す痕跡の残る場所」を意味しますが、狭義には「遺跡のうち、特に法律にもとづいて指定保護されるもの」の意味になります。古墳や集落跡、城跡などのうち、特に歴史的・学術的な価値が高いと法律や条令で認定されたものを、「史跡」と呼ぶことが一般的です。読み方は「しせき」で、北海道の「五稜郭」や栃木県の「大谷磨崖仏」などがそれにあたります。
「史跡」の「史」は、「歴史の書」を意味する漢字です。
「史跡」と「遺跡」は、もともとは意味の違いなく使われていました。しかし、現在では上記のように、特に学術的な価値の高いものを「史跡」と呼び、それ以外のものを「遺跡」と呼んで区別する傾向が強くなっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう