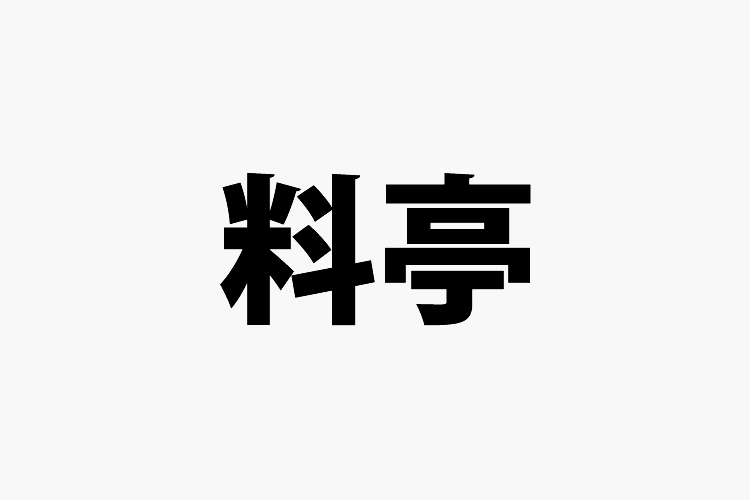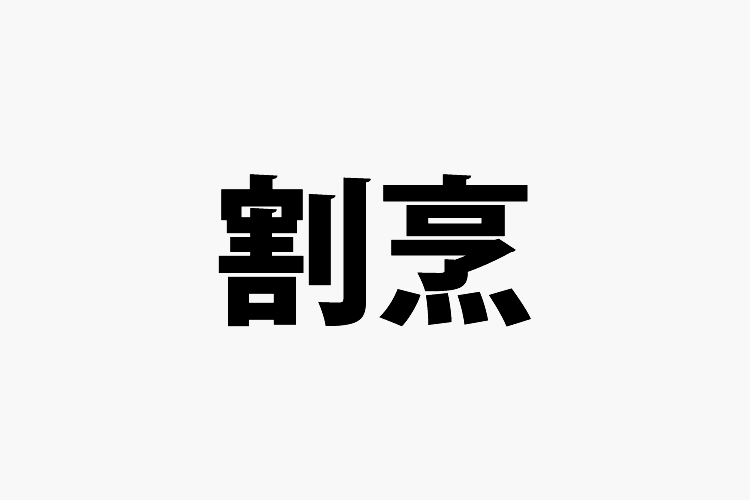違い
「料亭」と「割烹」の意味と違い

スポンサーリンク
料亭と割烹の意味と違いとは
伝統的な日本料理を提供するお店に「料亭」がありますが、同じく和食のお店として、「割烹」と名の付く料理店もあります。この2つはどちらも同じ意味のようですが、細かい違いなどはあるのでしょうか。使い分けのポイントが知りたいところです。
そこで今回は、「料亭」と「割烹」の意味や違いなどについて解説していきたいと思います。
「料亭」とは
「料亭」の大まかな意味合いは、「日本料理をメインとして提供する高級料理店」というものです。読み方は、「りょうてい」になります。
「あの料理人は、有名料亭での修業経験がある」「料亭政治と呼ばれたような文化は、今ではあまり見られない」のように使われます。
「料亭」の「料」は、元は「はかる」という意味の字ですが、「食べ物を切ったりして分けること」の意味でも使われます。「亭」の字は、「あずまや」や「飲食などを提供する建物」の意味があります。
「料亭」の主な特徴は、料理を個室の座敷で提供し、調理場は別の場所に置かれているという点にあります。また、接客には専門の中居がおり、芸妓を呼ぶなどができる点も、「料亭」の特徴です。
こうした点は、後述する「割烹」との大きな違いとなっています。
「割烹」とは
「割烹」には2つの意味があり、1つは「食べ物を調理すること」を指します。これは、「割」が「肉を割く」を指し、「烹」が「ものを煮る」を指すことから来ています。一般的には、伝統的な日本料理について使われる言葉です。読み方は「かっぽう」で、「割烹料理」「割烹着」のように使われます。
「割烹」のもう1つの意味は、「割烹店」というものです。「割烹店」とは、日本料理を主に提供する飲食店を指す言葉で、大まかな意味では「料亭」と違いはありません。その一方で、「割烹店」はカウンター席やテーブル席が中心であり、調理場も客席と同じ空間にあることが多いという特徴があります。また、板前が客の注文を直接受け付けて料理を作るなどの点も、「料亭」との違いに挙げられます。
使い分ける際は、こうした特徴を踏まえると分かりやすくなるはずです。
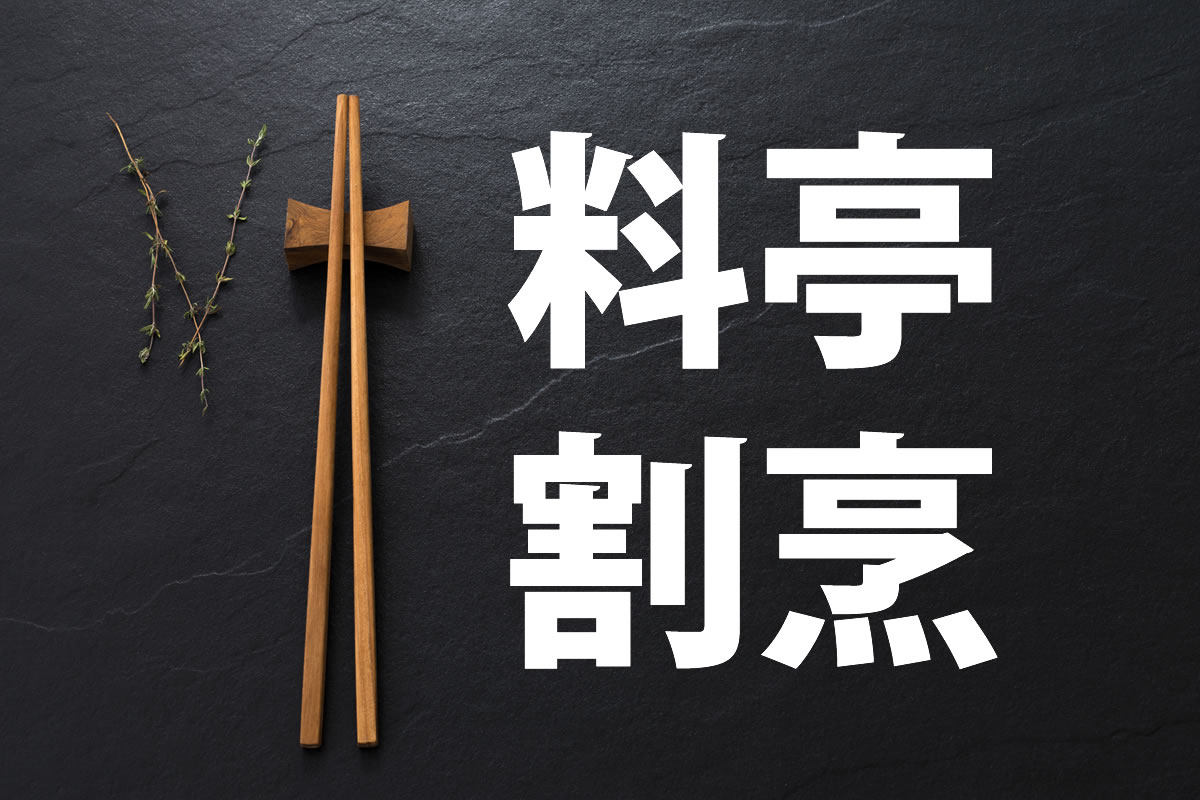
この記事が気に入ったら いいね!しよう