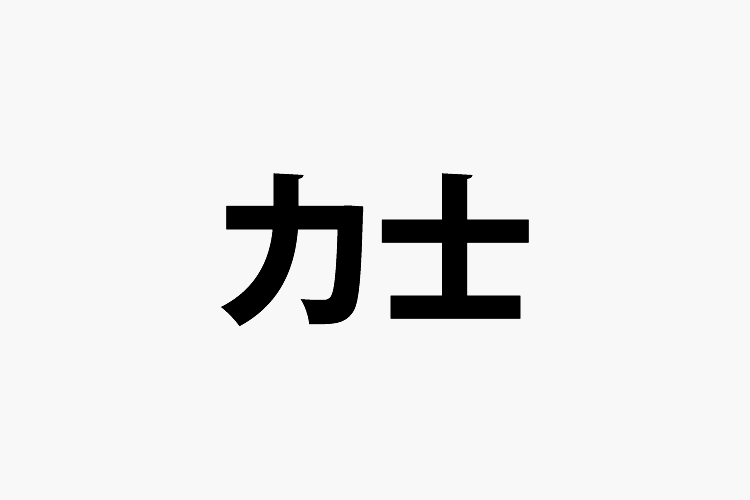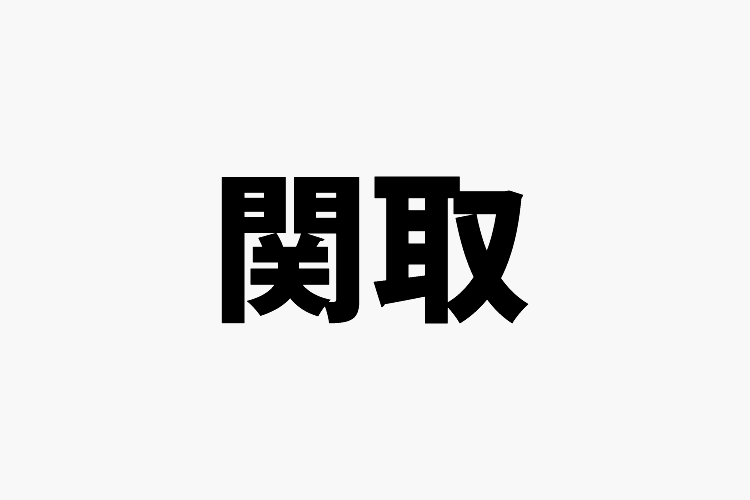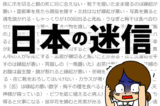違い
「力士」と「関取」の意味と違い

スポンサーリンク
「力士」と「関取」の意味と違いとは
相撲は日本の国技として、現在でも高い人気を誇っています。白熱した土俵上の闘いには誰もが興奮しますが、その相撲を取る人を指してよく使われるのが、「力士」と「関取」という呼び名です。この「力士」と「関取」は、どちらも同じ意味のようでいて、実は微妙な違いがあるのをご存知でしょうか。その違いとは一体どんなものなのか、今回はその点について詳しく解説したいと思います。
「力士」とは
「力士」とは、いわゆる「相撲取り」のことです。「相撲を取ることを職業とする者」を意味します。読み方は「りきし」で、「力の強い人」の意味もあります。
「力士がずらりと並んだ光景は圧巻だ」「子供のころから力士のような体型だった」のように使われます。
「力士」の名の由来は、仏教における仏の守護神である「金剛力士」にあります。この語は14世紀ごろから使われていましたが、「相撲取り」を指して使われるようになったのは、彼らが大名に抱えられて士分格に取り立てられるようになった、江戸時代中期ごろからです。
「力士」は大相撲で相撲を取っている者の総称であり、相撲部屋に所属して「四股名(しこな)」を持っていれば、誰でも当てはまります。この点は、後述する「関取」との大きな違いになります。
「関取」とは
「関取」とは、「十両以上の力士」という意味の言葉です。「相撲取り」の中で、番付が十両から上の者を指します。読み方は、「せきとり」です。「今場所から関取に昇進した」「彼は元関取だ」のように使われます。
大相撲の力士は、それぞれの実力に応じて「番付」と呼ばれる階級に振り分けられますが、番付には大きく分けて「幕内」と「十両」、そして「力士養成員(幕下以下)」の2つがあります。「関取」と呼ばれるのは、このうち前者の者だけです。「関取」になると一人前の「力士」と認められ、給料が支払われるほかに、羽織りや袴の着用などが許されるようになります。
このように、「力士」との違いは、番付が十両以上のものにしか使われないという点にあります。この違いを踏まえると、両者の使い分けがしやすくなるはずです。

この記事が気に入ったら いいね!しよう