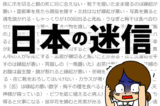違い
豚汁とけんちん汁の違いとは?

スポンサーリンク
豚汁とけんちん汁の違いとは
家庭の食卓を彩ってくれる汁物のひとつが豚汁。豚肉と野菜がたっぷり入っているので、おかずにもなる汁ものです。豚汁と似ている汁物として思い浮かぶのがけんちん汁です。けんちん汁は、豚汁と具材に大きな違いがなく、具沢山な点も似ています。
それでは、豚汁とけんちん汁は、同じ種類の汁物を意味しているのでしょうか。そこで、豚汁とけんちん汁は、それぞれどのような料理なのか、定義、発祥、レシピに注目しながら、比較してみたいと思います。
豚汁は豚肉を使った味噌汁の一種
豚汁とは、豚肉と野菜を煮込んで作った料理です。味噌で味付けすることから、味噌汁の一種として位置づけられています。
今から1000年以上前に「肉食禁止令」が出されてから、江戸時代が終わるまでのあいだ、日本では肉類は食べられませんでした。そのため豚汁は、明治時代ごろに登場したと考えられます。豚汁の始まりは、ぼたん鍋やさつま汁をアレンジした、北海道開拓民の「屯田兵の汁」が広まったなど諸説がありますが、定かではありません。
豚汁には必ず豚肉が使われ、味噌で味付けされます。具材は地域ごとに違いがありますが、にんじん、だいこん、ゴボウなどの根菜類、しいたけなどのキノコ類、豆腐、油揚げ、こんにゃくなどを入れるのが一般的です。肉と野菜は、油でいためることはせず、そのまま煮込みます。
けんちん汁は野菜を使った精進料理
けんちん汁とは、だし汁で野菜を煮込んで作った、すまし汁の一種です。けんちん汁は肉類を一切使わない点が、豚汁との決定的な違いです。
けんちん汁は、建長寺の汁物を意味するという説が有力です。建長寺とは、鎌倉時代に建てられた禅寺。「建長寺の汁」が「けんちんのしる」となり、さらに短縮されて「けんちん汁」となりました。けんちん汁は、お寺の精進料理のひとつだったため、肉類は使わないのです。
けんちん汁の具材は野菜類が中心で、味付けはダシと醤油が基本です。具材は、豚汁と基本的に変わりませんが、作り方に違いがあります。豚汁はそのまま煮込みますが、けんちん汁はゴマ油などで具材を炒めてから煮込みます。最近は、味噌味のけんちん汁も増えてきましたが、基本的にけんちん汁は具材を炒めると言った工程があります。

この記事が気に入ったら いいね!しよう