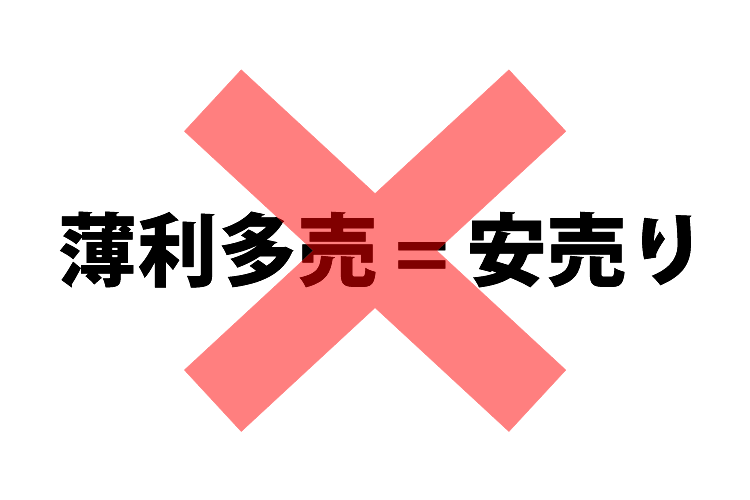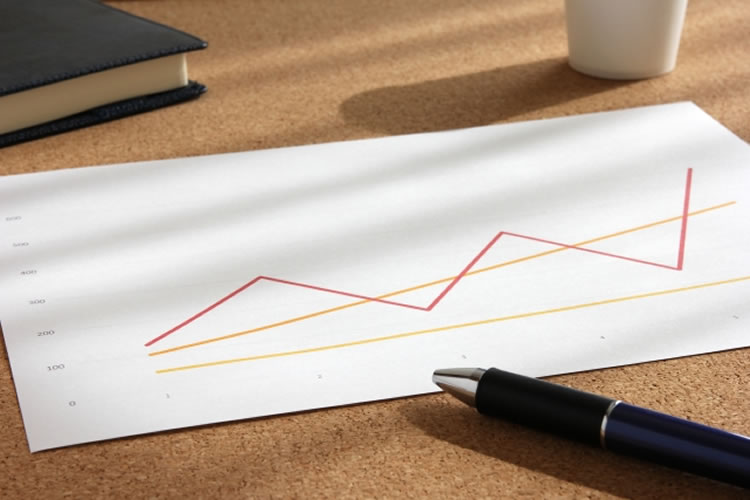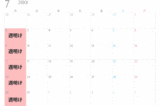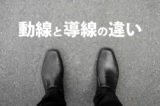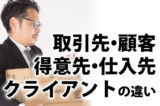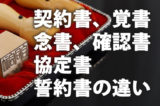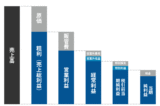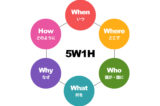ビジネス
薄利多売の意味とは?反対語と5つのメリット・デメリット

スポンサーリンク
薄利多売の意味とは?薄利多売の反対語とメリット・デメリット
ビジネスモデルや利益、売上などの話をしていると「多売薄利」と言った言葉を耳にする機会があります。意味が分かると言う方も少なくはないと思いますが、正確な意味が分からないと言った方や反対語、メリット、デメリットについてはっきりと説明できると言った方は少ないと思います。
ここでは社会人として最低限知っておくべき薄利多売について解説していきます。
薄利多売の意味とは
薄利多売とは利益の少ない商品やサービスを大量に販売することを意味する言葉です。1つ1つの利益は少なくとも大量に販売することで多くの利益を上げることができます。
薄利多売は「薄利」と「多売」の両方が成り立つ必要があり、仮に「薄利」であったとしても「多売」でなかったり「多売」であっても「薄利」でなければ薄利多売とはなりません。
「5種類の利益の違い(粗利、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益)」にも記載したように利益には様々な物がありますが、薄利多売の利益は基本的に粗利を指す場合が多くなります。つまり、売上から仕入れ値や原材料を差し引いた粗利を指しますので、人件費や宣伝広告費などを考慮しない利益のことを意味します。
また、薄利多売は粗利率が○%以下や粗利が○○円以下と言ったような明確な基準があるわけではありません。
例えば、1つの商品を販売することで10万円と言った利益が出るビジネスでもマンションやアパートなどを販売するビジネスでは薄利となりますし、仕入れなどの原価のかからない(粗利率100%)ウェブ制作も100万円で請け負っている会社からすれば5万円で大量に請け負う制作ビジネスは薄利多売となります。
薄利多売だから単価が安い物を販売するとは限らない
「薄利多売=安いものを売る商売」や「薄利多売=安売り」と言ったイメージをお持ちの方も多いと思いますが、必ずしもそうであるとは限りません。
上記の意味でも触れたように薄利多売とは、あくまでも利益の少ない商品を大量に売ることです。そのため、例えば1本10万円の高級ワインを1円の利益しか乗せずに大量に販売しても薄利多売のビジネスとなります。
薄利多売の反対語は
薄利多売の反対語(対義語)は一般的に厚利少売となっています。厚利少売は「こうりしょうばい」と読み、たくさんの数が出る商品やサービスではないが1つ1つの利益率は高い物などを販売するビジネスを意味します。
ただし、厚利少売と言った言葉は元々存在していた言葉ではなく、薄利多売の反対語として作られた造語です。
薄利多売のメリット
薄利多売には様々なメリットがありますが、主なメリットを2つご紹介していきます。
多少の顧客離れが起きても売上や利益が大きく変動しない
薄利多売には多少の顧客離れが起きても売上や利益が大きく変動しない・しにくいと言ったメリットがあります。
例えば、継続性がある商品を1つ1万円で1000人に販売し年間1000万円の利益を出すビジネスと1つ100万円の商品を10人に販売し同じ年間1000万円のビジネスを比較した場合、仮に1人の顧客離れが発生したとすると、前者の利益は0.1%しか低下しませんが、後者は10%の利益が低下してしまいます。
多くの顧客を獲得できる
ビジネスの世界では「1・5の法則」とよく言われ、新規の顧客獲得には既存顧客へのリピート販売の5倍のコストがかかると言われています。
もちろん業種や販売する商品によって異なるため、必ずしもこの法則が成り立つ訳ではありませんが、やはり新規の顧客獲得には労力を要します。
そのため薄利多売によりたくさんの商品を沢山の人に売ることで貴社の顧客を増やすことは大きなメリットが生まれます。
大量の既存顧客を獲得することで、コストを抑えて再度商品を販売することも可能ですし、別の高利益商品を別途販売することも可能となります。
薄利多売のデメリット
薄利多売には上記のようなメリットがありますが、デメリットも存在しています。ここからは薄利多売のデメリットについてご紹介していきます。
大量の商品を仕入れる・製造する必要がある
薄利多売には大量の商品を仕入れる・製造する必要があると言ったデメリットがあります。
たくさんの商品を販売するにはそれだけ商品を仕入れなければなりません。もちろん、アプリ販売やソフトウェア販売と言ったように販売する商品やサービスによって必ずしも仕入れが発生する訳ではありませんが、物販など物を売るビジネスの場合には必ず必要となります。
しかし、必ずしも商品が売れるとは限らないため在庫を抱えてしまうと言ったデメリットが発生する可能性もあります。
人件費や在庫の管理費などの費用が膨大にかかりやすい
2つ目に人件費や在庫の管理費などの費用が膨大にかかりやすいと言ったデメリットがあります。
上記で触れたように大量の商品を仕入れれば、保管費用や運搬費用にもコストがかかってきますし、管理したり、流通させるのにも人件費などの費用がかかってきます。
また、商品ではなくサービスを販売するビジネスにおいてもサービスを提供するための人員が必要となるためそれだけ人件費がかかるようになります。
仕入れ値の変動に販売価格が影響を受けやすい
極端な例ですが1000円の商品を900円で仕入れるビジネスと100円で仕入れるビジネスにおいて、仮に仕入れ値が100円上がったとすると前者では利益がなくなってしまい、現在の販売価格のまま商品を販売し続けることはできなくなります。もちろん、後者も仕入れ値が上がるためそのままでは利益率が減少してしまいますが、現在の販売価格のまま商品を提供し続けると言った選択をすることはできます。
つまり薄利多売のデメリットには仕入れ値の変動によって販売価格が変動しやすいと言ったことがあります。

この記事が気に入ったら いいね!しよう