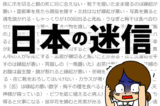違い
「おしるこ」と「ぜんざい」の意味と違い

スポンサーリンク
「おしるこ」と「ぜんざい」の意味と違いとは
甘いものに目がない人にとって、「おしるこ」や「ぜんざい」はたまらないごちそうでしょう。ところでこの「おしるこ」と「ぜんざい」ですが、こまかい違いをご存知でしょうか。甘党の人でも、意外に知らない人が多いと思います。
そこで今回は、「おしるこ」と「ぜんざい」の意味や違いについて解説していきたいと思います。
「おしるこ」とは
「おしるこ」とは、小豆を砂糖で甘く煮たてた餡に、餅や白玉団子などの材料を入れたものを言います。「お汁粉」「汁粉」などとも書かれます。
「おしるこ」は江戸時代の後期から流行しだした食べ物で、その当時は、切り餅や含め栗などを入れていました。焼いた小餅などを入れるようになったのは、かなりあとのこととされています。また、江戸時代のものは砂糖を入れず、塩で調理されており、酒のつまみとして出されていました。
「おしるこ」と「ぜんざい」は、地域によって区別の仕方が違います。例えば関東においては、汁気のあるもの全般を「おしるこ」と呼んでいますが、関西では「こしあん」を使った汁気のあるものを「おしるこ」と呼んでいます。「ぜんざい」との使い分けについては、以下で見てみましょう。
「ぜんざい」とは
「ぜんざい」は、上で述べたように、地域によって指すものが違います。関東における「ぜんざい」は、汁気のない餅に餡を添えたものについて言いますが、関西では、粒あんを用いた汁気のあるものについて言うようになっています。つまり、関東では「汁気のあるなし」、関西では「餡の種類」によって、「おしるこ」と「ぜんざい」が区別されることになります。
こうした地域ごとの違いの一方で、別の区別も存在します。一般的には、餡を水で溶いて作った汁に餅などの材料を入れたものを「おしるこ」、水に小豆や砂糖を加えて作った汁に餅などを入れたものを「ぜんざい」と呼ぶ地域も多くあります。基本的に、小豆の粒がないものに関しては、「ぜんざい」とは呼ばれません。このように、両者は通常、作り方の工程によって区別されるようになっています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう