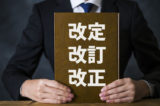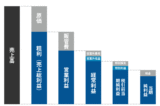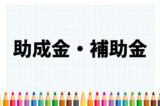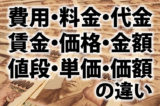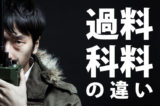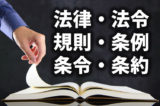監修記事
小切手と手形(約束手形と為替手形)の違い
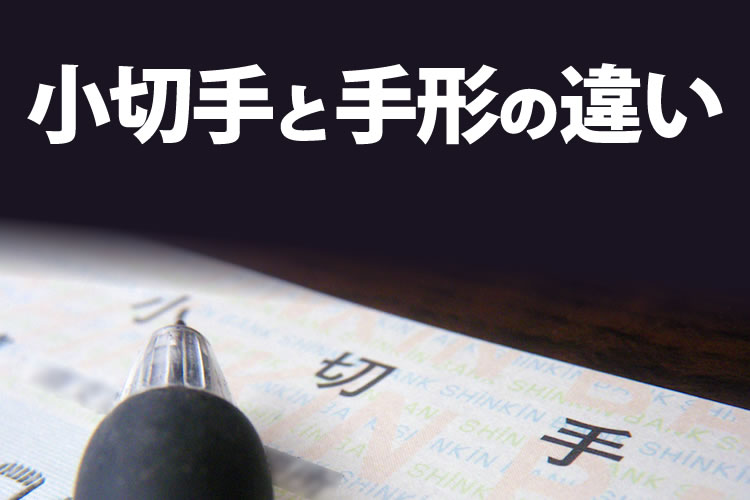
スポンサーリンク
小切手と手形の違い
「小切手」と「手形」。会計や経理などの勉強をしていなければ、その違いを学ぶ機会は少ないでしょう。また、経理などを担当していても、取り扱う機会が少ない、またはまったくない、と言った業種も多いため、小切手や手形を見たこともない方も多いと思います。
小切手と手形は、どちらもお金の代わりになる有価証券(商品券や株券と同じ)であり、所定の方法をとることでどちらも現金に変えることができます。
ここでは小切手と手形の違い、また、約束手形と為替手形と言った2種類の手形の違いについてご紹介していきます。
小切手とは
小切手とは、記載された金額分だけ現金と同等の価値を持つ有価証券のことです。
つまり、小切手の振出人は小切手に金額などを書き、現金の代わりに相手に渡す形でお金の支払いをすることができ、受取人は受け取った小切手を銀行などに持っていくことで現金に変えることができます。
支払いのために多額の現金を持ち運ぶ必要がないため、現代のようにクレジットカードなどが無かった頃の安全な取引方法でした。
また、小切手が手形と大きく異なる点があり、それは現金化できるタイミングです。
小切手は小切手に記載されている振出日(通常は渡された日の日付)の当日でも銀行に持っていくことで現金に代えることができます。手形のように満期を待たなくてもよいのです。
ただし、注意が必要で振出日の翌日から数えて10日までが換金の期日となります。10日を過ぎてしまった場合でも現金化は可能ですが、振出人が「支払委託の取消」を行うと銀行は受取人に支払いをすることができなくなってしまいます。
そのため、振出の翌日から数えて10日以内に換金するのが安全です。
さて、ここまでの話を聞くと、「今はネットバンキングもあるし、振込でいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
振込の場合、振込金額に応じて手数料がかかります。最も高い場合で、880円~990円ほどの振込手数料がかかることが多いようです。
一方、小切手の場合、金融機関によっては換金に手数料がかからないことがあります。手数料がかかる金融機関では、660~1100円程度かかることが多いようです。また、小切手用紙は銀行で購入する必要がありますが、だいたいの銀行で50枚つづりのものを1万1000円程度で購入することができます。1枚ずつでも買うことができて、この場合の代金は220円程度です。
つまり、取引1回あたりについてみると、小切手のほうが振込よりも手数料が安くなる場面もたしかにあります。しかし、小切手の使用には慣れていない人が多いため、金額の大きな取引では、数百円程度の差は気にせず、慣れた決済方法である振込を選ぶ人が多いのではないでしょうか。
やはり便利な決済手段がある現代では、ほとんどの場合「振込でいい」という結論に至るのかもしれません。
手形とは
手形は小切手と似ています。大きな違いは、小切手がすぐに現金化できるのに対して手形はある一定の期間後に銀行に持っていくことで現金化できるという点です。
つまり手形の振出人からすれば、その時にお金が無くても、満期までにお金を用意すればよく、猶予があるということになります。その一方で、手形を交付することで現金の代わりにいますぐ支払いをすることができるというメリットがあります。
現金化できる支払期日は一般的には1ヶ月後から最大でも120日後程度の支払期日とする場合が多く、小切手同様に手数料はかかりません。
また、「手形の割引」といった方法を使うことで、受取人も支払期日よりも前に換金し現金を手にすることができます。しかし、手形の割引には審査がある上に、支払期日までの利子と手数料を差し引かれた金額しか受け取ることができません。
約束手形とは
上記で説明したように株式会社A社から株式会社B社に手形を渡し、期日を迎えると株式会社B社は銀行に手形を持っていくことで現金を手にすることができます。
これまで説明した上記のやり方が約束手形になります。
為替手形とは
一方、為替手形とは約束手形とは違い、さらに株式会社C社を含めて3社で手形のやり取りをすることになります。
株式会社A社が株式会社B社より商品を購入し、現金の代わりに手形で支払いたいとしまう。
しかし株式会社B社は株式会社C社と別の取引で株式会社C社へ支払いをしければならない時にA社からもらう手形に「代わりにC社へ払ってください」と記載することで株式会社A社は株式会社B社ではなく株式会社C社へ支払うことができるため、全ての会社の支払いを簡素化することができます。
これが為替手形になります。
約束手形とは違い3社間でのやり取りになるため少し複雑ですが、あまり利用される機会はありませんので、こういった方法もあることだけ覚えておけば問題ないかと思います。
小切手と手形のデメリット
小切手と手形に違いはあるものの、手数料がかからない上に、手形に関しては今は現金がなくても支払いができるなどのメリットもあります。しかしメリットばかりではなくデメリットもあります。
受取人が指定の期日内に小切手または手形を持って銀行に行き、現金化をしようとしても振出人の口座にお金がない場合には現金化することはできません。
また、そうなる状態を「不渡り」と言い、小切手や手形を振出した方も不渡りを半年以内に2回を出してしまうと銀行取引が一切できなくなる「取引停止処分」を受けてしまいます。
銀行との取引が一切できなくなれば、小切手や手形以外でも他の会社との取引ができなくなるため、どんなに儲かっていようが「事実上の倒産」となってしまいます。
小切手と手形の違いのまとめ
どちらも専用の用紙に金額や日付を書くことで現金の代わりになる有価証券ではありますが、小切手はすぐに現金化できるのに対して、手形は指定の期日まで現金化できない(支払いを先延ばしにできる)、と言った違いがあります。
また、最後になってしまいましたが、手形のやり取りには普通預金口座ではなく、当座預金口座が必要になります。
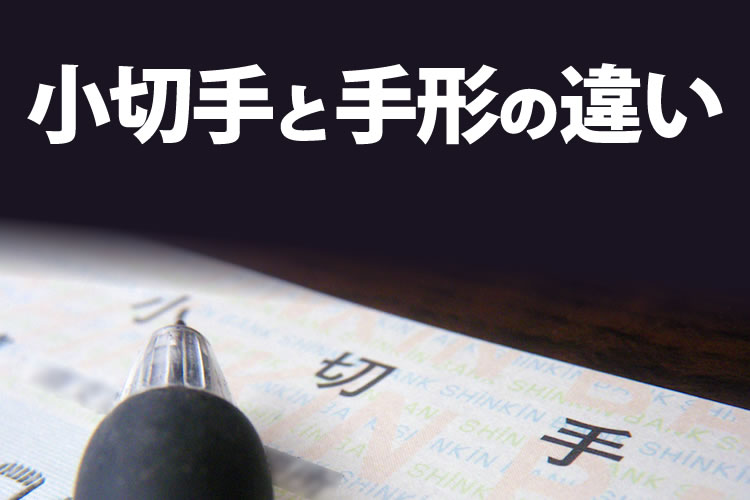
この記事が気に入ったら いいね!しよう