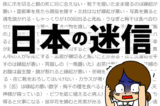違い
そうめんと冷麦の違いとは?

スポンサーリンク
そうめんと冷麦の違いとは
夏の風物詩であるそうめん。夏バテ気味で食欲がないときでも、さっぱりと食べられるのでとても便利です。また、冷麦も、そうめんと同じく夏の定番メニュー。コンビニのお弁当コーナーで見かけることも多い麺です。そうめんと冷麦は、どちらも白くて細い麺であり、さっぱりした味わいが特徴で、冷たい麺つゆを付けて食べるなど食べ方にも多くの共通点があります。
それでは、そうめんと冷麦は同じ食材を意味しているのでしょうか。そこで、製法と麺の太さに注目しながら、そうめんと冷麦の違いについて解説します。
そうめんと冷麦の製法の違い
そうめんとは、小麦粉、食塩、水を練り、引き伸ばして乾燥・熟成させた麺のこと。その起源は唐の時代の中国にさかのぼります。索餅(さくべい)と呼ばれる、小麦粉と米粉を練って、縄のようにねじった唐菓子が、奈良時代の日本に伝わりました。鎌倉時代から室町時代にかけて、麺を手延べする方法が中国から伝わると、索餅は素麺へと進化しました。
冷麦の主原料は、小麦粉、食塩、水と、そうめんと基本的に違いがありません。異なるのはその起源です。冷麦とは、室町時代に食べられるようになった切麦の食べ方のひとつで、切麦とは、うどんを細く切った麺を意味します。冷たい状態で食べるのは冷麦、熱い状態で食べるのは熱麦と呼ばれました。つまり冷麦は、うどんの一種となります。
そうめんと冷麦の太さの違い
そうめんは唐菓子に起源があり、冷麦はうどんの一種。主原料に大きな違いはないものの、別々に進化しているため、意味づけが異なりますが、明治時代に同一の製麺機が使われるようになると、そうめんと冷麦の違いがはっきりしなくなります。
この問題を解決するために、そうめんと冷麦を麺の太さから定義するようになりました。日本農林規格(JAS)によると、長径1.3mm未満であればそうめん、1.3mm以上1.7mm未満であれば冷麦に該当します。この定義は、機械製麺である場合に限定されます。
伝統的な手延べそうめんの場合、JASの規格に当てはまらないケースが出てきます。たとえば徳島県に伝わる半田そうめんは、一般的なそうめんよりも麺が太く、JASの規格では冷麦になってしまいます。そこで手延べの場合に限り、1.7mm未満であれば、そうめんと冷麦のどちらを名乗ることもできます。

この記事が気に入ったら いいね!しよう