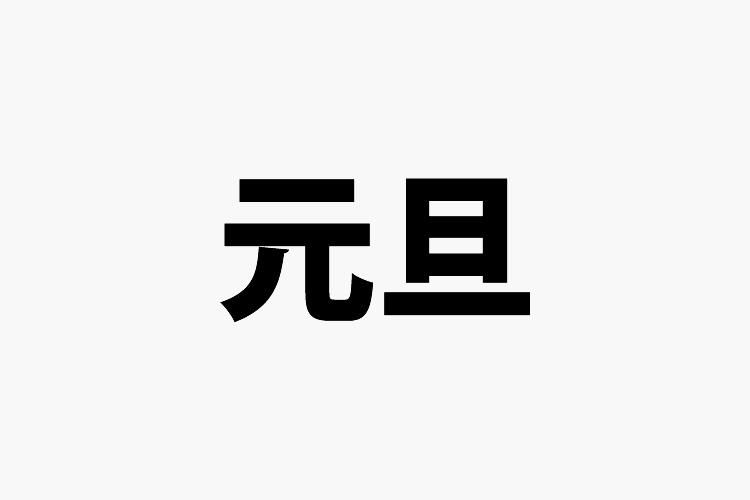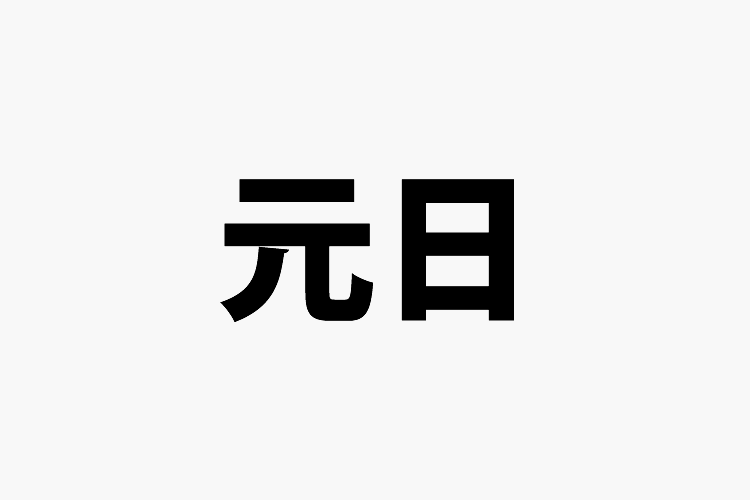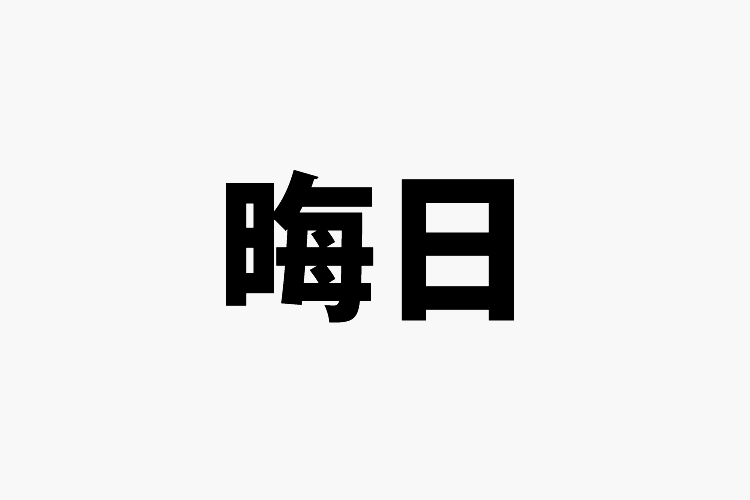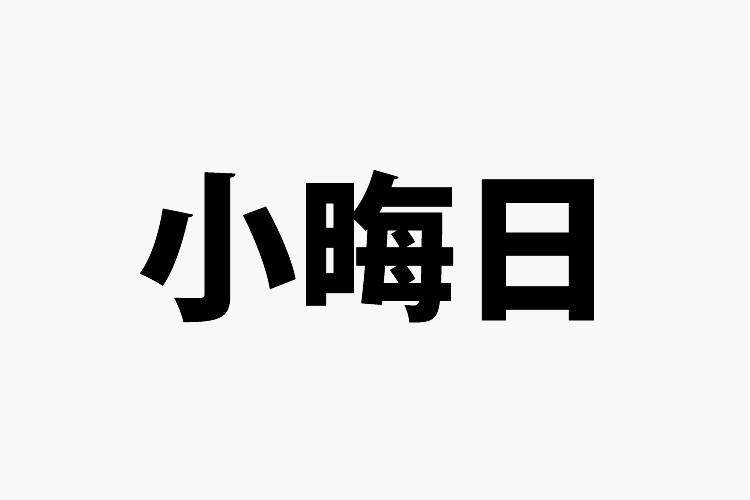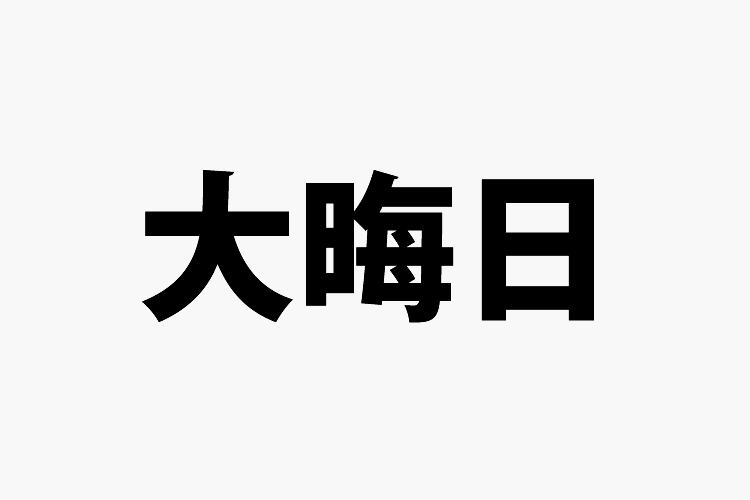一般常識
元旦・元日・正月・晦日・小晦日・大晦日の違い

スポンサーリンク
元旦・元日・正月・晦日・小晦日・大晦日の違いについて
年の瀬が近づくと、年越しや年賀状の準備に忙しくなります。
この時期には、「元旦」や「元日」、あるいは「大晦日」「晦日(みそか)」という言葉をよく使うようになりますが、これらの違いについて詳しく言えるという人は、それほど多くないでしょう。しかし、あらたまった挨拶をする時などのために、それぞれの正しい意味を知っておくことも必要です。
そこで今回は、「元旦」「正月」「晦日」「小晦日」「大晦日」の違いについて、詳しく解説していきます。
元旦
元旦とは、元日の朝を指します。
元旦の元は「最初の」という意味がありますが、この場合は、1年のスタートの日である1月1日を指しています。一方、旦という字は、地平線から太陽が覗く様を表しており、「朝」「夜明け」といった意味があります。
つまり元旦という言葉は、「1月1日の朝」を表していることになります。
元旦は、つい元日と同じ意味で使ってしまいがちですが、本来の意味では違います。ただ、かなり古くから元日と混同されている上に、旦は時間帯だけでなく「1年の夜明け」を指すという解釈もあります。
そのため、両者を同じ意味で使っても、決して間違いとは言えません。とは言え、やはり本来の意味を押さえておくと、挨拶の際などで恥をかくことはなくなるはずです。
元日
元日とは、「1月1日」を指す言葉です。
前述のように、元は始まりを意味していますから、1年の始まりの日である1月1日がこれにあたります。
元旦は上で見たように、主に1月1日の朝を指していますが、元日はそれとは違い、一部の時間帯に限りません。1月1日であれば、どの時間帯でも元日という言葉を使うことができます。
ただ実際には、これも前述のように、両者は同じ意味で使うことも多くなっています。
このように、元日は1月1日を指して言う言葉ですから、この日を過ぎると使えません。そのため、年賀状に元日と書く場合には注意が必要です。1月1日より後に配達される可能性がある場合には、元日より「新年」を使った方が無難でしょう。
正月
正月とは、1月全体のことを指しています。「3が日」という言葉から、正月というと1月3日までと認識している人も多いようですが、本来の意味は違います。本来は、1月1日から31日までの、1月全てを正月と呼ぶのが正しいとされています。
しかし実際には、3が日が正月であるとする説や、7日までを正月とする説、15日までを正月とする説など、諸説あるのが実情です。また、現在では1月全体を指して正月ということは、現実的にはほとんどありません。多くは3が日か、あるいは松の内までを正月と呼ぶようになっています。
ちなみに松の内とは、門松などの飾りを飾っておく期間のことで、関東は7日まで、関西は15日までと、地域によって異なります。
晦日
晦日(みそか)とは、月の最終日を表す言葉です。「みそか」のほかにも「つごもり」と読んだり、「かいじつ」と読む場合もあります。
晦日という言葉の由来は「三十日(みそか)」で、もともと「月の30番目の日」という意味でした。しかし実際には、特に30日だけが晦日というわけではなく、月末を表す言葉となっています。
例えば29日までしかない月であっても、月の最終日であれば、晦日ということになります。このように、晦日は1年に複数回あり、この点は年に一回である小晦日や大晦日と大きく違います。
ちなみに、晦日を「つごもり」と読むのは、「月ごもり」に由来しています。旧暦では、月末になると月が隠れて見えなくなるため、この名で呼ばれるようになりました。
小晦日
小晦日(こみそか)とは、大晦日の前日を言います。現在の暦(グレゴリオ暦)では、12月30日が小晦日にあたります。
日本では以前、暦として太陰太陽暦が用いられていました。これは月の満ち欠けの周期を基とする暦で、新月を1日とし、そこから月が隠れるまでがひと月(約29.5日)となります。前述のように、旧暦では月の最後の日を晦日(「晦」は「月が隠れる」という意味)と呼びますが、旧暦の晦日は毎月30日、あるいは29日のどちらかになります。
これに対し、現在は1年の終わりの日を指して大晦日(おおみそか)、その前日を小晦日と呼ぶようになっています。つまり、旧暦での小晦日は12月29日、あるいは閏12月29日になります(小の月は28日)。
現在では旧暦と違い、太陽暦が用いられているため少し分かりにくいですが、現在の暦で言うと小晦日は大晦日の前日にあたる12月30日ということになります。
大晦日
大晦日とは、先に述べたように、1年の最後の日を言います。現在の暦では、12月31日が大晦日になります。
晦日は、何度も述べているようにそれぞれの月の最後の日を言いますが、大晦日は1年の末日という特定の日を指します。最後の晦日ということから、「大」の字が頭につけられており、旧暦では12月30日、または29日にあたります。
ちなみに、晦日には「かいじつ」という読み方も存在しますが、大晦日にはありません。「おおみそか」、あるいは「おおつごもり」が大晦日の読みとなっており、この点は晦日との違いに挙げられます。

この記事が気に入ったら いいね!しよう