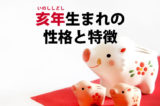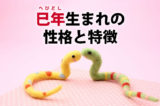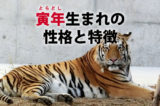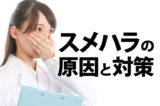スキルアップ・キャリアアップ
ロールモデルの意味とは?背景や人物像、効果など

スポンサーリンク
「アーティストの○○氏は、若者のロールモデルとして注目されている」といったように、最近「ロールモデル」という言葉をあちこちで聞くようになりました。ビジネスシーンでも使われる機会が増えていますが、一体この言葉は、どんな意味を表しているのでしょうか。漠然としたイメージはあっても、詳しい内容までは分からないという人も多いでしょう。
本記事では、「ロールモデル」という言葉の意味や注目される背景、当てはまる人物像やもたらす効果について解説していきますので、理解の参考にしてみてください。
ロールモデルの意味とは?
「ロールモデル」とは、「考え方や行動の模範となる人物」といった意味の言葉です。ある活動をする上で、自分が実践したいことの理想を体現しているような、見習うべき人物について言います。簡単に言えば、「こういう人になりたい」と思わせるような人物が、「ロールモデル」です。英語の「role model」から来た言葉で、「role」は「役割」を、「model」は「見本」を意味しています。
「ロールモデル」となる人物は、一般に高いスキルやリーダーシップを持っています。設定を1人に限る必要はなく、たとえば3人の「ロールモデル」の一部分ずつを手本にするといったことも可能です。
注目されている背景
近年「ロールモデル」が注目されている背景には、「多様な価値観や働き方の広がり」という現象が存在します。
たとえば一昔前まで、子供ができると女性は家庭で子育てに専念するという考え方が一般的でした。しかし、現在では子育てと仕事を両立させたいと考える人は多く、そうした際に具体的な両立法やキャリアの作り方で悩むといったケースも増えています。
その一方で、すでに同じことを経験して乗り越えている人物もいます。そうした人が「ロールモデル」となることで、後に続く者の悩みを減らし、働きやすくする効果が期待されているというわけです。
ふさわしい人物とは
「ロールモデル」は「模範とするべき人物」ということですが、具体的にはどういう人物像が当てはまるのでしょうか。ケースによってさまざまなタイプが考えられますが、ここでは「ロールモデル」として設定されやすいタイプの人物像を紹介していきましょう。
上司・先輩
「ロールモデル」は、その人の考えや行動に触れて学ぶ存在のため、身近であるほど手本として役立ちます。典型例が、直属の上司や、日ごろお世話になっている先輩などです。
その人物の働きぶりや人との接し方、問題への対処の仕方などを、日ごろからつぶさに観察することで、さまざまなことを吸収できます。もちろん、手本になる点ばかりとは限らないでしょうが、上記のように、「ロールモデル」は一部分にだけ設定しても構いません。
所属部署にそうした人物がいない場合は、他部署から見つけるのもOKです。
付き合いのある社外の人
社内で「ロールモデル」となる人物を見つけられない場合は、接点のある社外の人から探してみるという方法もあります。たとえば取引先の社員や、顧客などです。
身近な上司や先輩を「ロールモデル」にする場合、距離の近さがノイズになり、冷静な観察がしにくくなってしまう場合もあります。一方社外の人であれば、適度な距離があるので、ひいき目など余計な感情に邪魔される心配はありません。フラットな視点で観察でき、純粋に良い部分を見つけやすいという利点があります。
有名人・歴史上の人物
身の回りで「ロールモデル」にできそうな人物が1人も見当たらないという場合は、有名人や歴史上の人物の中から選定するのも有効です。
実際に、実業家やアクティビスト、政治家、学者、芸術家、芸能人、スポーツ選手などから「ロールモデル」を選ぶケースは多くなっています。こうした人々は強い憧れを喚起させる点で「ロールモデル」に向いていますが、その一方で目標が巨大化・抽象化されてしまうなどのリスクも付きまといます。
そのため、これらの人々を「ロールモデル」に設定する場合は、「強いリーダーシップ」などポイントを具体的に絞ることが、現実の活動に反映させる上で重要になります。
複数人
これは上でも述べましたが、「ロールモデル」は必ずしも1人である必要はありません。同時に複数人を設定してもOKとなっています。
どんな人も良い部分とそうでもない部分の両方を持ちますから、1人の人物から全てを学ぼうとするのは、そもそも無理があります。ですので、「ロールモデル」を複数人設定するのは、ごく自然な行為と言えます。
そうした場合は、ジャンルごとに別々の「ロールモデル」を選ぶやり方がおすすめです。たとえば、「スケジュール管理はAさん」「顧客対応はBさん」「プライベートとのバランスの取り方はCさん」といった具合です。
6つの効果
ここまで「ロールモデル」の意味や人物像について見てきましたが、そもそも「ロールモデル」を作ることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、「ロールモデル」の設定によって期待できる具体的効果をいくつか紹介していきましょう。
キャリアプランが立てやすくなる
「ロールモデル」の設定は、具体的なキャリアプランを想定する上で非常に役立ちます。
上でも述べた通り、現在は価値観が多様化しており、そのことが将来の設計を難しくしている側面があります。しかし、そうした時でも「ロールモデル」となる人物がいれば、その人を通じて将来的なビジョンを思い描くことができるので、モチベーションを維持しやすくなります。
ですので、社員にキャリアプランへの意識づけを図りたい場合は、各部署やチーム内に「ロールモデル」となり得る人物を配置しておくことがポイントとなります。
成長スピードが加速される
「ロールモデル」設定の効果としては、「成長のスピードを早められる」ということも挙げられます。
「ロールモデル」は上で説明したように、行動や思考の指針となる存在です。言わば目指すべきゴールであり、その人との比較を通して、自然に努力や研鑽を促されることになります。また、普段から立ち居振る舞いを観察することで、さまざまな気づきや反省を得ることもできます。
その結果、スキルが素早く身に付くなど、社員の成長の促進が期待できます。
社内コミュニケーションが活性化される
組織内に「ロールモデル」となる人物がいると、組織内部のコミュニケーションが活発になるというメリットがあります。
憧れの人物にはできるだけ近づきたいというのが、多くの人が持つ自然な心理です。社内の「ロールモデル」についても同様で、どうにかして接点を増やして、1つでも多くを吸収したいと願う社員が増えると考えられます。
「ロールモデル」を中心にそうした動きが生まれることで、自然に交流の波が広がり、結果として社内全体のコミュニケーション活性化に役立ちます。
組織の活性化にもつながる
「ロールモデル」の導入は、会社全体の活性化にも役立ちます。
そもそも「ロールモデル」は、十分なリーダーシップやコミュニケーション能力を持つ人物なので、元から慕われる要件は備えています。そうした人が身近にいれば、前述のようにコミュニケーションも密接になり、それに応じて職場の雰囲気も良くなると考えられます。
こうした風通しの良さは、当然会社に活気をもたらします。社員の仕事へのモチベーションも上がって、さらに雰囲気が良くなるという好循環も生まれやすくなります。
女性の活躍やダイバーシティを推進できる
上記のように、後続へ規範を示し、悩みの解消を手助けするのが「ロールモデル」の役割ですが、特にこの効果が期待されるのが、女性やマイノリティなどの存在です。
とりわけ家事や育児、介護と仕事の両立を図る人や、病気を抱えらながら働く人などには、未だに多くの壁が存在します。悩みや不安を抱えて消耗するケースも多くなっていますが、そうした時同じ境遇にあって活躍する人が身近にいれば、励みになる部分は小さくありません。
近年は女性の活躍やダイバーシティがよく話題になりますが、その点でも「ロールモデル」の設定は役立つと言えます。
離職の防止
「ロールモデル」の設定がもたらす効果としては、「離職防止」も挙げられます。
昨今は各業界で労働力不足が深刻ですが、さらに「若手社員の離職」という問題が、そうした状況に追い打ちをかけています。若手が早々に離職してしまうのは、会社での将来が思い描きづらいことや、成長が望めないと感じることに主な原因があります。
これに対し、「ロールモデル」を投入することで、若手社員に1つの理想を提示することができます。将来像が明確になり、成長へのモチベーションも生まれるので、離職率の低減に役立つと考えられます。

この記事が気に入ったら いいね!しよう