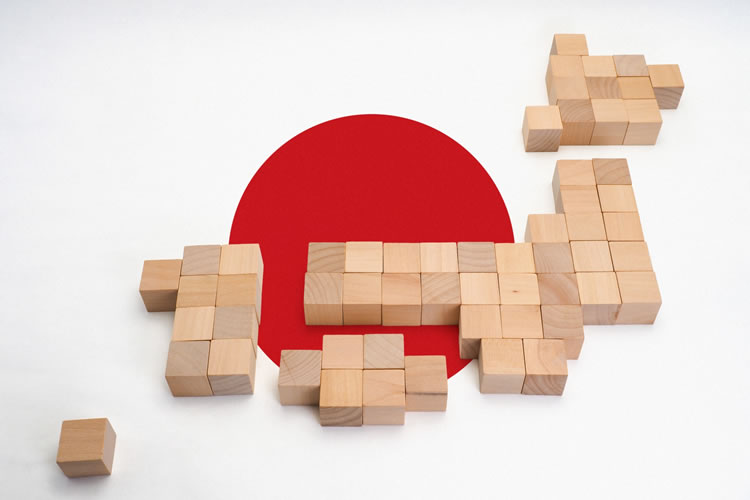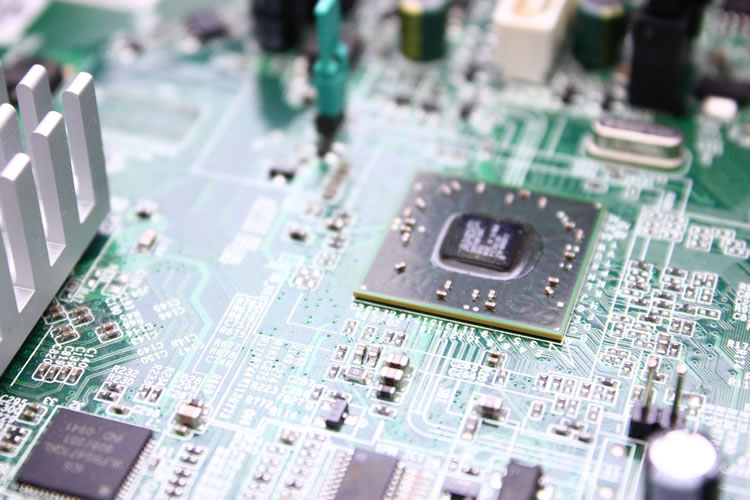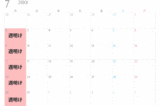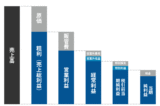ビジネス知識
日本における景気循環の歴史!好景気と不景気の種類31選

スポンサーリンク
日本における景気循環の歴史!好景気と不景気の種類
「景気」は、我々の生活にとって最も重要な話題の1つです。周知のように、活気のある場合は「好景気(好況)」、落ち込んでいる場合は「不景気(不況)」と呼ばれますが、景気はこの「好景気」と「不景気」を、交互に繰り返す性質があります。経済学ではこうした動きを指して、「景気循環」もしくは「景気の波」と呼んでいます。
もちろん日本においても、「景気循環」は現在まで連綿と続いてきました。その中には「いざなぎ景気」のように有名なものもあれば、「転型期不況」のようにほとんど聞いたこともないものもあります。それらについて知ることは、戦後以降の日本の歴史を学ぶことにもつながります。
そこでここでは、日本における「景気循環」について、戦後から現在に至るまでの流れを順に追って解説していきたいと思います。
好景気:朝鮮特需景気
日本における景気循環(第1循環)、最初に挙げるのは、「朝鮮特需景気」です。「朝鮮特需」とも呼ばれますが、これは朝鮮戦争をきっかけとして起こった好景気になります。
朝鮮戦争は、1950年に当時成立したばかりの大韓民国(韓国)と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の間で勃発しました。これに応じ、戦争開始直後の6月にアメリカ軍による在日兵站司令部が設けられ、大量の物資が日本の各企業へ発注されるようになります。その際調達された物資は、軍服や土嚢用麻袋などに使用する繊維製品や、陣地構築に必要な各種鋼材のほか、食料品やコンクリート材料、車両修理など多岐に及びました。
朝鮮戦争をきっかけとしたこの好景気は、50年から52年の3年間で10億ドルにもおよび、55年までの間接特需では、36億ドルにものぼるとされています。
不景気:反動不況
日本における景気循環、続いては不景気の局面ですが、こちらは「朝鮮特需」の最中に起こった不況(反動不況)です。
上記のように、朝鮮戦争は1950年に勃発し、その後しばらくは日本に好景気をもたらしました。結果としては、休戦協定が結ばれた後もさまざまな経済効果を生みますが、しかし、その間ずっと好況が続いていたわけではありません。戦争開始から1年ほど経つと、好景気は一変し、「反動不況」と呼ばれる不景気の時期が訪れます。「朝鮮特需」が最初のピークを迎えたのは、1951年の6月ですが、その後は公定歩合の引き上げもあって景気は後退期に入り、同年10月には谷間へと落ち込むこととなりました。その後は再び上昇に転じますが、約5カ月ほどは、日本は不景気を経験することとなりました。
好景気:投資・消費景気
続いての景気循環(第2循環)の局面は、「反動不況」後の「投資・消費景気」と呼ばれるものです。文字通り、活発な投資と消費がもたらした好景気になります。
「朝鮮特需」によって戦後の混乱から抜け出した日本では、それを契機として消費ブームが訪れました。やがてそれは投資ブームへ引き継がれることとなり、これによってもたらされた好景気は、「投資・消費景気」と呼ばれるようになります。
この好景気は、1954年の1月ごろにピークを迎えました。この時設備投資の中心となったのは、電力・海運・鉄鋼・石炭の4大重点産業です。また53年には、1人あたりの実質消費が戦前を上回るなど、戦後の本格的な復興へ向けた基盤が固まることとなりました。
不景気:昭和29年不況
続いての景気循環は不景気ですが、こちらは「昭和29年不況」と呼ばれるものになります。
前述のように、「朝鮮特需」から始まった好景気は、「反動不況」を経て「投資・消費景気」へと引き継がれました。しかし、特需景気も終了し、投資や消費のブームも一段落すると、今度は純輸入が増大して外貨危機が顕在化することとなります。いわゆる「国際収支の天井」と呼ばれる事態ですが、これを避けるために、政府は財政・金融による引き締め政策を行います。これはわざと景気を後退させ、外貨準備を保とうというものです。これにより、「投資・消費景気」は終息に向かい、10ヵ月の後退期を経て、景気は1954年(昭和29年)11月に谷間を迎えることとなりました。
好景気:神武景気
上記の「昭和29年不況」を経て、景気循環(第3循環)は好景気へと転ずることになりますが、この時の好況を指して、「神武景気」と呼んでいます。
前述の財政・金融の引き締め政策で国際収支が安定したことから、政府は引き締め政策を緩和します。これによって再び投資が上向いたのに加え、世界的な景気拡大の波もあって、輸出の下支えが働いたこともプラスとなりました。この時期の好景気は、「国際収支の改善」「物価の安定」「オーバーローンの是正」を同時に達成しており、日本経済の自立を証明するものでもありました。
こうした好景気は1957年6月ごろまで続きますが、56年(昭和31年)の経済白書に「もはや戦後ではない」と記されたことで、国内では戦後復興の完了が印象付けられることとなりました。
ちなみに「神武景気」の名称は、「神武(初代天皇)が即位して以来、例がないほどの好景気」という意味です。
不景気:なべ底不況
続いての景気循環は、「なべ底不況」と呼ばれる不景気です。
上記のように、「神武景気」は戦後の復興を本格化させる好景気として1957年6月ごろまで続きますが、その後は一転して景気が冷え込みます。その要因としては、輸入が急増したことによる国際収支の悪化と、それに伴う政府や日本銀行による金融引き締め政策が挙げられます。
この引き締め策により、産業界は軒並み減収・減益、資金不足に陥り、操業短縮による在庫調整が行われました。この不況については、当時景気の長期低迷は避けられないとする「なべ底論(中華鍋の底を這うような形で推移する)」と、不況は一時的なものとする「V字型論」の2つが唱えられましたが、58年の経済白書においては「なべ底論」が採用され、「なべ底不況」の名で呼ばれることとなりました。しかし、実際には不況は58年6月で収束したため、結果的にこの予測は外れています。
好景気:岩戸景気
「なべ底不況」の次の景気循環(第4循環)としてやってきたのが、「岩戸景気」と呼ばれる好景気です。
上記のように、「なべ底の形のように長期化する」と見られていた「なべ底不況」は、1958年の7月ごろに底を打ちます。さきに行われた金融引き締め政策によって輸入が減少したことで、国際収支が改善したことが要因でした。その結果、引き締め策は撤回され公定歩合が引き下げられたことから、消費需要や投資投資が急増することとなります。特に投資熱は大きく、ある民間企業の設備投資が別の企業の設備投資を招くといった状況で、「投資が投資を呼ぶ」と言われるほどでした。結果この好景気は、拡張期が42ヵ月と日本の経済史上でも屈指の長期に及び、「神武」の前のさかのぼる「天岩戸」の故事から、「岩戸景気」の名で呼ばれるようになりました。
不景気:転型期不況
前述の「岩戸景気」は、1958年の7月から1961年の12月まで続くこととなりましたが、その次に訪れたのが、「転型期(てんけいき)不況」と呼ばれる不景気です。
戦後空前の好景気だった「岩戸景気」を収束させたのもまた、国際収支の悪化による金融引き締め政策でした。1961年1月からは、国際収支改善対策として、財政支出の一部繰り延べや公定歩合の引き上げなどが行われます。これにより景気は冷え込み、62年のGDP成長率は、8.7%(59~61年は実質10~13%)にまで鈍化しました。この後退期は、1962年の10月まで続くことになります。
「転型期」の名前がついているのは、62年の経済白書で「設備投資主導型の高度成長は転機を迎え、以後の経済成長率の鈍化と成長パターンの変化は避けられない」とされたことによります。
好景気:東京オリンピック景気
続いての景気循環(第5循環)は、「東京オリンピック景気」です。
「転型期不況」は、前述のように1962年10月まで続きました。上で述べた金融引き締め政策によって輸入が減少したことと、堅調な輸出によって再び国際収支は改善します。これをもって引き締め策が解除されたことにより、62年の12月以降は景気が上向くこととなりました。
この好景気は、1964年の10月までおよそ24ヵ月続くことになりますが、64年夏には「東京オリンピック」が開催されたことから、「東京オリンピック景気」の名で呼ばれるようになっています。事実、オリンピックに向けた建設需要は活況を呈しましたが、実際にはそうした状況がそれほど長く続くことはありませんでした。また、輸出と個人消費は堅調に伸びたものの、設備投資の拡大テンポの伸びは鈍化したという面もあります。
不景気:証券不況
続いての景気循環の局面は、「証券不況」と呼ばれる不景気です。
上記の「東京オリンピック景気」による好景気は、オリンピック終了後の1964年10月に収束します。63年にはすでに国際収支は悪化しており、再び金融引き締め政策が実施されることとなりました。これにより、64年11月からは景気は低下局面に入ります。これにはまた証券市場の動きも絡んでいました。
それまでの好景気で、日本の証券市場は急成長していましたが、「東京オリンピック景気」の収束で企業の業績が低迷すると、その影響が証券市場にも及びます。大手証券会社は軒並み赤字に陥り、日銀は公定歩合を引き下げるなどしましたが、実質的な効果はありませんでした。「証券不況」は、1965年10月まで続くことになります。
好景気:いざなぎ景気
「証券不況」を経て、景気循環(第6循環)は好景気へ移ります。今度の局面は、「いざなぎ景気」と呼ばれるものです。
上記のように、「証券不況」収束のために公定歩合の引き下げが行われますが、効果はほとんどありませんでした。そこで次の策として、1965年5月に山一証券への日銀特融を、7月に戦後初となる赤字国債発行を決めたことにより、同月を底値として株価は上昇に転じます。これを契機として始まった好景気は、その後1970年の7月まで、57ヵ月にもわたって続くこととなりました。
「いざなぎ景気」の名前は、やはり日本神話に由来しています。「いざなぎ」は国生み神話で知られる「伊弉諾尊(いざなぎのみこと)」のことで、「神武」や「岩戸」を越える古い存在ということで名づけられました。
不景気:ニクソン不況
「いざなぎ景気」の次の局面は、「ニクソン不況」と呼ばれる不景気です。
57ヵ月の長期に及んだ「いざなぎ景気」により、日本経済はGNP世界2位にまで上昇します。
その「いざなぎ景気」は、1970年の7月をピークに収束しますが、これには国内景気の好況によるインフレ圧力が関係していました。長期の好景気によって商品や労働の供給がひっ迫し、コストプッシュインフレが囁かれるようになったことから、戦後初めて国際収支黒字の下での金融引き締め政策が取られます。さらに71年には、「ニクソンショック(固定比率での米ドル紙幣と金の兌換の一時停止による、世界的な経済ショック)」が起こったこともあり、景気後退の局面は71年12月まで17ヵ月間続くこととなりました。
好景気:日本列島改造景気
続いての景気循環(第7循環)は、「日本列島改造景気」と呼ばれる好景気です。
この景気拡大のきっかけとなったのは、金融緩和と政府の公的投資でした。1971年の「スミソニアン協定」による円の切り上げで生じたデフレ圧力を相殺するため、日本政府は積極的な金融・財政政策に舵を切ります。これにより、72年ごろから景気拡大の速度が急速に上がり始めました。さらに、田中角栄氏による「日本列島改造論」に触発され、日本各地で大規模な土地開発ブームが沸き起こったことも、こうした好況に拍車をかけることとなります。「日本列島改造景気」という呼び方は、このような状況に由来しています。
この好景気は、71年12月から73年11月まで、およそ23ヵ月にわたり続くこととなりました。
不景気:第1次オイルショック不況
「日本列島改造景気」に続くのは、「第1次オイルショック不況」と呼ばれる不景気の局面です。
「日本列島改造景気」のころから、日本では物価上昇の速度が加速し、インフレが問題化してきました。それを抑えるため、政府は1973年の春に金融引き締め政策に乗り出します。
しかし、これに73年秋に発生した第1次オイルショックが重なったことで、「狂乱物価」と呼ばれる大インフレが発生しました。国内の消費は落ち込み、政府もインフレ対策で大型公共事業を凍結・縮小するなど、不況が拡大します。また国際収支も赤字となり、「スタグフレーション」「トリレンマ」などの新語が誕生することとなりました。
この「第1次オイルショック不況」は、1975年3月ごろまで続くこととなります。
好景気:省エネ景気
続いての景気循環(第8循環)は、「省エネ景気」と呼ばれる好景気です。
前述の「第1次オイルショック不況」は、1975年の3月をピークとして一段落します。これは、これまでの建設国債に加えて赤字国債の発行を行ったことや、公定歩合の引き上げといった財政金融政策が、一定の成果を上げたことも影響していました。また、前年までで大きく落ち込んでいた需要にも反動が起こり、景気はやや持ち直します。さらに、各企業が不況を受けて大幅な「減量経営」に乗り出したことで、76年には企業の対前年度比経常利益が74.3%と、戦後最高を記録することとなります。
インフレも収束に向かい、経常収支も黒字化するなど、好景気は77年1月ごろまで続くこととなりました。
不景気:円高不況
「省エネ景気」の後に来た不景気は、「円高不況」と呼ばれるものです。
「省エネ景気」は、前述のように1977年初めまで続きますが、その後景気は下降局面に入ります。これは、77年にニクソンショック以来2回目の円高になったことが影響していました。これによりレートの模様眺め気配が強まったことで、企業マインドが沈静化されることとなります。
インフレが収まって物価が安定し、国際収支も改善したとはいっても、それまでの好景気は企業の減量経営によるものというのが実情でした。そのため、これまでのように公定歩合の引き上げが行われたわけではなく、また公共事業の促進等も行ったにもかかわらず、不景気は77年10月ごろまで続くこととなります。
好景気:公共投資景気
続いての景気循環(第9循環)は、「公共投資景気」と呼ばれる好景気です。
この好景気のきっかけとなったのは、公共投資の増加と金融の緩和政策でした。「経済白書」では、「78年をもって第1次石油危機の調整過程は完了した」と述べていますが、国内の消費も回復し、減量経営が続いていた企業の設備投資も、増加に転じることとなります。円高は78年78年8月にピークを迎えるなど依然続いていましたが、「Jカーブ効果(為替レートの変動から予測されるものとは別方向に、短期的な貿易収支が振れる現象)」のために、貿易収支は大幅な黒字を記録します。
この「公共投資景気」は、1980年2月ごろまで、約28ヵ月にわたり続くこととなりました。
不景気:第2次オイルショック不況
「公共投資景気」に続いての景気局面は、「第2次オイルショック不況」と呼ばれる不景気です。
1979年に起こった「イラン革命」により、イランでの石油生産が一時ストップします。このため、イランから大量の原油を輸入していた日本は、需給がひっ迫することとなりました。これによって原油価格は、第1次オイルショック時よりも上昇する事態となります。
ただ、公定歩合の引き上げもあって消費者物価の上昇が相対的に低く収まったため、混乱は前回ほど大きくありませんでした。それでも、この石油危機を契機とした金融引き締め政策により、景気は後退局面に入ることとなります。
さらに公的投資の抑制や、世界的な不況なども重なり、「第2次オイルショック不況」は83年2月まで36ヵ月にわたり続くこととなります。
好景気:ハイテク景気
続いての景気循環(第10循環)は、「ハイテク景気」と呼ばれる好景気になります。
「第2次オイルショック不況」は、戦後からそれまでで最長の不景気でした。その空気を変えたのは、財政・金融政策とアメリカの景気回復です。「レーガノミクス」と呼ばれる経済政策により、アメリカに好景気が到来したことで、日本の対米輸出が急増します。この時期の経済成長への輸出寄与率は、実に48%にも上りました。さらにその結果、こうした輸出関連の半導体やコンピュータといった、ハイテク産業が拡大することとなります。
この好景気に対し、一部で「ハイテク景気」の名称がつけられているのは、このためです。
結局この「ハイテク景気」は、85年6月まで続くこととなりました。
不景気:円高不況
「ハイテク景気」に続く不景気は、「円高不況」と呼ばれるものです。
「ハイテク景気」により、対米輸出が急増したことは上でも述べました。しかしその結果、アメリカとの間に深刻な貿易摩擦を引き起こすこととなります。これにより、1985年に行われた「プラザ合意(先進国による為替レート安定に関する合意)」で、アメリカの対日貿易赤字解消を目的として、円高が誘導されることとなりました。その後、実際に市場為替レートは大幅な円高に振れ、輸出に頭打ち傾向が出始めることとなり、景気は後退局面に入ります。「円高不況」の名がついているのは、こうした状況によります。
この「円高不況」は、85年6月まで28ヵ月にわたって続くこととなりました。
好景気:バブル景気
「円高不況」に続いて訪れた景気循環(第11循環)は、「バブル景気」です。
「バブル」の名称でも有名なこの好景気は、1986年12月から1991年2月までの間に起こりました。このきっかけとなったのは、公定歩合の史上最低への引き下げと、公共投資の拡大などです。
これによって「円高不況」を抜けたことに加え、積極型の財政・金融政策や逆石油ショック(石油相場の急落)も重なって、良好な内需主導型の景気拡大が長期にわたり続くこととなりました。この好景気を受け、1989年12月29日には、日経平均株価が史上最高の38,957円の高値をつけるに至っています。
後に知られるように、この空前の好景気は一気にはじけたことから、「バブル景気」の名で呼ばれることとなりました。
不景気:バブル崩壊不況
日本の経済史上でも類をみない「バブル景気」が終わった後には、「バブル崩壊不況」という不景気がやってきました。
「バブル景気」の実態は、1986年からの「円売りドル買い」政策でマネーサプライが急増し、国内に「カネ余り現象」が発生したことで、これを資金とした金融機関による株や土地の投棄が横行し、地価や株価が高騰したというものでした。さらに大幅な金融緩和政策が続いたこともあってバブルが膨らみましたが、89年5月の公定歩合引き上げや、90年3月の「総量規制(不動産向け融資の伸び率を、総貸出の伸び率以下に抑えるという行政指導)」などをきっかけとして、バブルは崩壊することとなります。
「平成不況」とも呼ばれる「バブル崩壊不況」は、91年3月から93年10月まで続くこととなりました。
好景気:カンフル景気
続いての景気循環(第12循環)は、「カンフル景気」と呼ばれるものです。
「カンフル景気」は、1993年11月から97年5月まで続きました。「カンフル」の名は、政府による数度の経済対策が、景気に対しカンフル剤の役目を果たしたことに由来します。日本政府は、93年4月に総合的な経済対策として13.2兆円を、さらに9月には、緊急経済対策として5.9兆円の支出を行っています。さらに、94年2月にも15.3兆円の経済対策を行い、93年には公定歩合を2.5%から1.75%に引き下げるなどしました。こうして94年からはGDP成長率や企業収益も改善しますが、その実態は強引な景気浮上策や大幅なリストラによるところが大きく、完全失業率などの数字で見ると、本物の好景気とは言い難い側面もあります。
不景気:日本列島総不況
「カンフル景気」に続く不景気は、「日本列島総不況」と呼ばれるものです。これは、1997年6月から99年1月まで、20ヵ月にわたって続きました。
「カンフル景気」が本当の好景気とは呼びにくいことは、上で述べた通りですが、その後の不況はかつてないほど厳しいものでした。その厳しさは、失業と倒産の数の多さに表れています。
98年には、国内の全地域で完全失業率が過去最悪の水準(全国4.1%)に達し、有効求人倍率も0.53倍と、過去最低の水準を記録しました。企業倒産で見てみると、戦後3番目に多い18,988件を記録しています。また負債総額においても、13兆7,500億円という戦後2番目に悪い数字を記録しました。こうした最悪の状況から、この時期の不景気は「日本列島総不況」の名が冠されています。
好景気:ITバブル景気
「日本列島総不況」に続く景気循環(第13循環)は、「ITバブル景気」と呼ばれるものです。「インターネット・バブル」とも呼ばれるこちらの好景気は、1999年2月から2000年11月まで続きました。
名前の通り、背景にはインターネットやIT(情報技術)の発達が関連しています。アメリカではこうした分野の企業に投資が集中し、多くのベンチャー企業が誕生して、株式市場も活況を呈しました。日本でも、この時期に多くのIT関連の企業が誕生し、興隆するといった状況が生まれています。また、アメリカのハイテク株への投資を謳い文句とした投資信託商品が組成されるなどもしました。日本において投資の対象となったのは、主に既存の通信・携帯電話関連株や、コンピュータ関連株、半導体、通信ケーブルなどでした。
不景気:ITバブル崩壊不況
「ITバブル景気」に続いて訪れたのは、「ITバブル崩壊不況」と呼ばれる不景気です。
「ITバブル」は、上記のように2000年の終盤まで続きましたが、期間としてはおよそ14ヵ月と、それほど長いものではありませんでした。2000年の3月には、光通信による携帯電話売買の不正が明るみに出た結果、それを引き金として、関連銘柄も大きく値を下げるなどしています。こうして日本のネットバブルは崩壊しますが、アメリカでもまた、ドルの利上げや同時多発テロ事件などもあり、ネットバブルは崩壊します。しかし、日本では依然平成不況や就職氷河期が続いており、IT関連投資が部分的だったことから、アメリカのバブル終焉の影響は限定的なものでした。「ITバブル崩壊不況」は、2000年12月から2002年1月まで続くこととなります。
好景気:いざなみ景気
続いての景気循環(第14循環)は、「いざなみ景気」と呼ばれる好景気です。こちらは2002年2月から、2008年2月まで73ヵ月にわたって続きました。
好景気のきっかけとなったのは、2001年からのゼロ金利政策に代表される、一連の金融緩和政策です。大幅な為替介入によって生じた円安や、北米などの好調な需要の牽引もあって、輸出関連産業を中心とした多くの企業が、過去最高の売上高・利益を記録しました。また、大企業の積極的な設備投資もあり、国内の雇用も拡大します。企業倒産件数もこの間大幅に減少し、96年以来の水準まで下がることとなりました。
「いざなぎ景気」を上回る期間に及ぶことからこの名で呼ばれていますが、その一方で景気の恩恵が一部に偏ったことや、経済成長が緩やかであったことから、一般には実感が湧きにくい好景気だったとされています。
不景気:リーマン不況
「いざなぎ景気」に続く局面は、「リーマン不況」と呼ばれる不景気です。「リーマンショック」の名でも知られており、2008年3月から2009年3月まで続きました。
「リーマン」の名がつけられているのは、アメリカの投資銀行「リーマン・ブラザーズ・ホールディングス」の経営破綻に端を発しているためです。2007年の時点で、すでにアメリカにおける住宅バブルは崩壊しており、「サブプライム住宅ローン危機」が起こっていました。これによって多額の負債を抱えたリーマン・ブラザーズは、2008年9月に経営が破綻しますが、その影響はアメリカ国内だけでなく、世界中へ波及することとなります。
日本は直接的な被害こそ軽微でしたが、この件をきっかけとした世界的な需要の落ち込みにさらされ、輸出産業などが大きなダメージを受けることとなりました。
好景気:エコ景気
「リーマン不況」に続く景気循環(第15循環)は、「エコ景気」と呼ばれる好景気です。こちらは2009年4月から、2012年3月まで続きました。
「エコ」の名がついているのは、いわゆる「家電エコポイント事業」によって刺激された好景気のためです。「家電エコポイント事業」とは、日本政府がリーマンショックを機として、2009年度の補正予算などにおいて行った経済・景気対策の1つになります。これは、地球温暖化の防止や経済の活性化、地上デジタル放送テレビの普及などを目的に、省エネ機能の高いエアコンや冷蔵庫などの購入者に対し一定のエコポイントを付与するという制度で、エコポイントは事務局が選定するさまざまなエコ商品と交換することが可能でした。
このエコポイントの制度は、最終的に2010年度いっぱいまで延長されています。
不景気:円高不況
「エコ景気」に続いて到来したのは、「円高不況」による不景気です。「円高不況」は、2012年4月から2012年11月まで続きました。
名称の由来は、もちろん円高にあります。円高自体は、2007年のサブプライムローン危機のころから進行していました。この時期1ドル=100円を突破すると、その後も勢いは止まらず、2008年以降は1ドル80円代後半~90円台で推移するようになります。2010年代に入ってもその傾向は続き、アメリカ連邦準備制度理事会による金融緩和政策の実施や、東日本大震災による円資金需要の高まりなどもあって、円高はますます進行することとなります。2011年3月17日には、一時76円25銭をつけるにいたりました。こうした円高は、日本の製造業にかなり悪影響を与えています。
好景気:アベノミクス景気
「円高不況」に続く景気循環(第16循環)は、「アベノミクス景気」です。
「アベノミクス」とは、第二次安倍内閣で掲げられた、一連の経済政策を総称したものです。これは、かつてロナルド・レーガン米大統領が行った「レーガノミクス」にちなんで名付けらています。
「アベノミクス」の概要は、デフレ経済の克服を目的としてインフレターゲットを設定し、その達成がはかられるまで、日本銀行法改正も視野に入れた大胆な金融緩和措置を取るというものでした。
2012年末の「アベノミクス」施行後、日本の名目総生産は、2012年の494兆円から2017年までの5年間で、過去最大となる549兆円に増加しています。こうした景気拡大局面は、2019年1月時点で74ヵ月となり、「いざなみ景気」を抜いて戦後最長を記録したとされています。

この記事が気に入ったら いいね!しよう