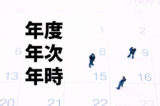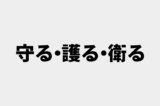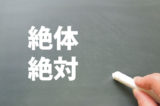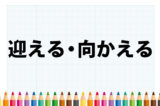一般常識
作る・造る・創るの違い
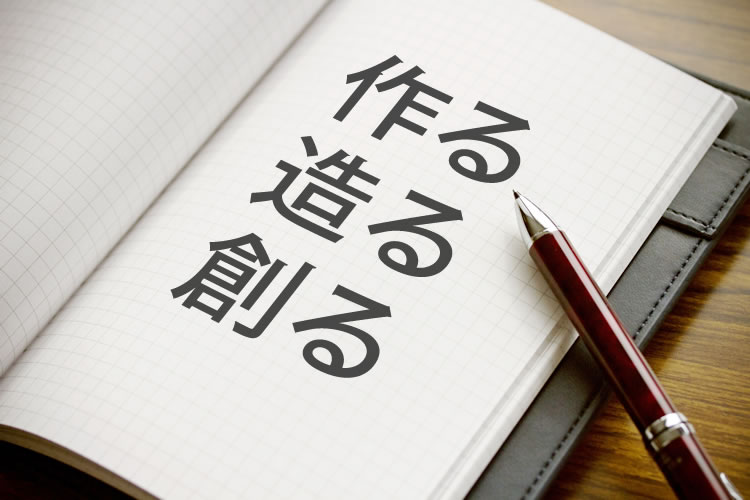
スポンサーリンク
作る・造る・創るの違いとは
作るとは
作るは、「つくる」の最も一般的な表記になります。「作」という字は、人が木の枝を刃物で取り払っている様を表しています。つまり、木という素材に対し手を加えることで、別のものを「つくる」作業を表しているわけです。
意味としては、何かしらの素材を用いてある物を組み上げたり、今までにないものを新しく生み出す際などに用います。具体的には、「料理を作る」「新曲を作る」といった具合です。
一般的に作るという表記をする場合は、比較的規模の小さなものや、形の無いもの、抽象的なものに対して用いることが多くなっています。例えば、家庭で調理した料理を「手作り料理」、日曜大工で手掛けた椅子を「手作りの椅子」と表現するといった具合です。
また、会社などの組織やスポーツの記録など、無形のものについても、作るという表記が主に使われます。
造るとは
造るもまた、何かを生み出す際に使われますが、「作る」とはニュアンスに違いがあります。
作るが前述のように、比較的小さなものを生み出す際に使うのに対し、造るはよりサイズの大きなものを生み出す際に使うことが多くなっています。
例えば、自動車や船、建物や庭園、広場といったものなどです。また、サイズは小さくても製造の規模が大きいものに対しては、やはり造るという字で表現するのが一般的です。具体的には、工場生産の食品や家具、日用品などです。
作るとのもう1つの違いは、無形のものにはほとんど使われないという点です。これも前述のように、作るは形の無いものや抽象的な概念にも使われますが、造るはほぼ有形のものに限られます。この点は、両者を使い分ける上でも重要です。
創るとは
創るは常用外の読み方ですが、やはり「つくる」と発音します。大まかな意味としては、「作る」や「造る」と同じく、ある物を生み出す際に使います。
創るという表記を用いるのは、作るや造るとは違い、場合がかなり限られます。すなわち、何か新しいモノやコトを生み出す時に使うことが一般的です。
例えば、「創作料理」などと言うように、これまでなかった料理を案出した際には、「創る」の表記が用いられます。料理などの実際に存在するものだけでなく、言葉やアイデアなど、無形のものに対しても使われます。
まとめ
以上、「つくる」という言葉に対する「作」「造」「創」の3つの表記について、それぞれの違いを説明しました。
「作る」という表記は最も一般的な形で、大抵の場合に用いることができます。しかし、どちらかというとサイズが小さく、小規模なものに対して使われる傾向があります。
それに対し「造る」は、比較的サイズや製作規模が大きいものに対して使われるという特徴があります。また、「作る」と違って無形のものにはあまり使われません。
一方、「創る」という表記を用いる場合は、新しいモノ・コトを創造する際が多くなっています。ただ、こちらは常用漢字外の読み方のため、公文書などでは、「作る」あるいは「造る」を使った方が良いでしょう。
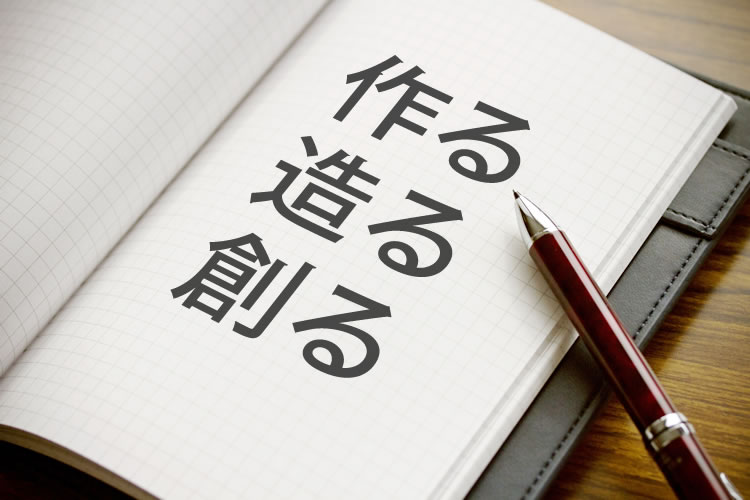
この記事が気に入ったら いいね!しよう